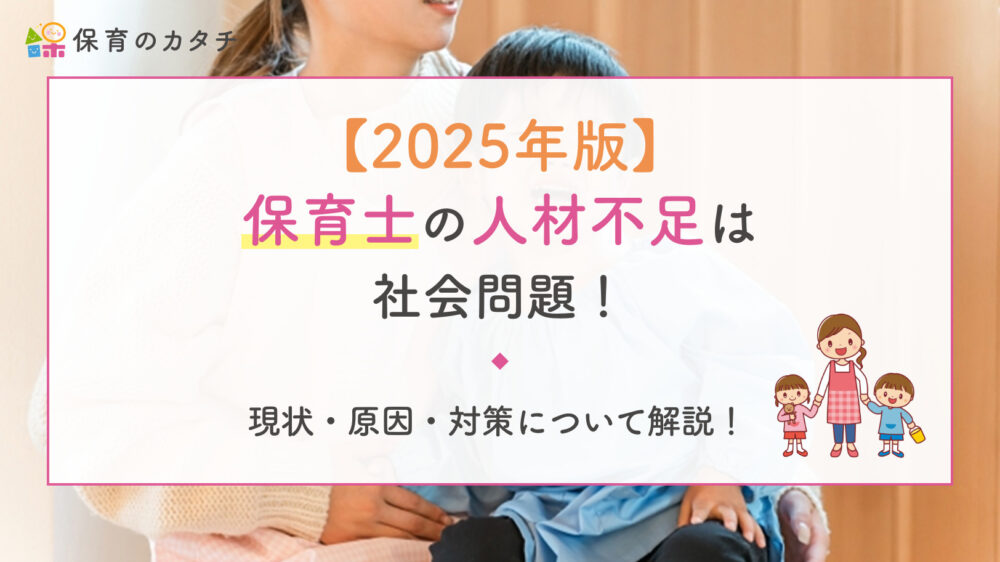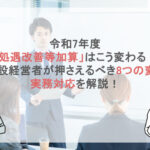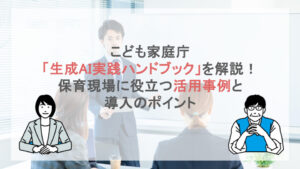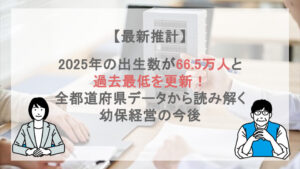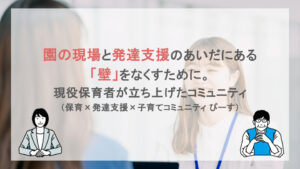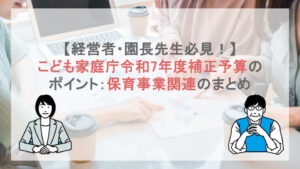保育士不足は、子どもたちの未来を担う保育士にとっても、保護者や社会にとっても深刻な社会問題です。保育園や幼稚園などで働く保育士の数が不足し、待機児童問題が深刻化しているのが現状です。
そこで今回の記事では、保育士不足の現状やその原因、その対策について解説します。保育士の人材不足について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/
保育士の採用をするなら保育のカタチがおすすめ
引用元:保育のカタチ
保育士の採用をするなら保育のカタチがおすすめです。
保育のカタチは日本で唯一、幼保業界の「人」に関する問題解決に特化した専門家集団です。採用から社員教育、それらの仕組み化まで幅広く取り組んでおり、人手不足の保育業界の中で、幼保施設にとって最善のパートナーが見つかるようなお手伝いをしています。
採用がうまくいかず悩んでいる方はぜひ一度保育のカタチにご相談ください。
| 住所 | 〒550-0004大阪府大阪市西区靱本町1-7-22 SKKビル201 |
| 許可番号 | 厚生労働大臣許可番号有料職業紹介事業:27-ユ-303764労働者派遣事業:派27-304996 |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員、パート |
| 求人施設 | 保育園、幼稚園、認定こども園、病児保育、事業内保育、学童保育、託児所など |
| 対応エリア | 全国 |
| 連絡手段 | 電話番号:06-6210-5326 |
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/
最新データから見る保育士不足の現状

保育士不足の現状は、厚生労働省が公表している統計からも明らかです。ここでは、厚生労働省のデータから見る保育士不足の現状について解説します。
保育士不足はすべての都道府県で起きている?
保育士不足は全国的な課題となっており、2024年にはすべての都道府県で保育士の有効求人倍率が1.0を超えています。これは「求職者1人あたりに複数の求人がある」状態を示しており、全都道府県で人手不足が発生していることを意味します。
この現象は都市部に限らず、地方圏にも広がっているのが現状です。地方ではそもそも保育士のなり手が少なく、人口減少の影響を受けて就職希望者が激減している自治体もあります。地域を問わず、保育現場が慢性的な人手不足に悩まされていることがわかります。
有効求人倍率から見る人手不足の現状
2024年7月時点の全国の保育士有効求人倍率は、2.69倍と高い数値を示しております。これは、求職者1人に対して約2.7件の求人があることを示しています。以下は、都道府県別の有効求人倍率を高い順に並べたものです。
- 栃木県:6.39
- 広島県:4.35
- 東京都:4.02
- 静岡県:3.98
- 福井県:3.95
一部の地域では求人票が出されても応募がまったくない状態が続き、採用活動が長期化しているケースもあります。保育業界の有効求人倍率は他職種と比較しても高水準で、人手不足の深刻さを裏付けています。
保育士の早期退職や潜在保育士の人数増加が見られる

保育士不足は、早期退職や潜在保育士の人数増加も原因の1つです。厚生労働省の「保育分野における人材不足の現状②」によると、保育士の6割が5年以内に退職しているとのことです。
早期退職者の大部分が女性であることから、女性の働き方改革の必要性が浮き彫りになっているといえます。保育士の資格を持ちながら現在は保育士として働いていない「潜在保育士」の増加も人手不足の要因の1つです。
保育士不足の背景

保育士不足が深刻化している背景には、社会構造の変化や労働市場の影響が複雑に絡み合っています。保育士不足の要因は、以下の3つが考えられます。
- 少子高齢化による生産年齢人口の減少
- 採用難易度の高さ
- 離職者の多さ
それぞれ順に紹介します。
少子高齢化による生産年齢人口の減少
日本では少子高齢化が進み、現役世代の人口が年々減少しています。これはさまざまな業界で人材確保を難しくしており、保育士も例外ではありません。
かつては、子どもが好きな人を中心に人気の就職先として注目されていた保育職ですが、労働条件の厳しさや将来性への不安から敬遠される傾向が強まり、若年層を中心に他業種へ流出するケースが目立っています。
採用難易度の高さ
保育士の採用は、保育士資格を持っていることが前提であるため、そもそもの採用母集団が限定されています。また、採用にあたっては実務経験や一定の適性も求められるため、保育士資格があるからといって、即採用できるとも限りません。
結果として、「求人はあるのに採用できない」「面接しても辞退される」などの採用難が発生し、園運営に支障をきたしている保育施設が多いのが現状です。
離職者の多さ
離職率の高さも保育士不足の大きな背景要因です。厚生労働省によると、約半分の現役保育士は経験年数が6年未満の保育士だとわかります。せっかく採用しても早期に離職する保育士が多いのが現状です。
離職理由の多くは「人間関係」「業務量の多さ」「体力的な負担」「給与が見合わない」などが挙げられており、環境が改善されなければ、人材の定着は難しいでしょう。
保育士不足の原因は?

保育士不足が起こる主な原因は、以下のとおりです。
- 業務量に対して給料が低い
- 責任感の重さと事故への不安
- 休暇の取りにくさ
- 人間関係の悩み
- 幼保施設以外への就職を希望している人の多さ
それぞれ順に解説します。
業務量に対して給料が低い
保育士の仕事は、子どものお世話だけにとどまりません。保護者対応や書類作成、行事準備、会議など多岐にわたり、ときには休日出勤を要することもあります。
しかしながら、その業務量に対して賃金水準は依然として低く、2023年度の平均月収は約26万円(厚生労働省調査)と、全職種平均の約34万円を大きく下回っています。この賃金と業務量のギャップが離職の一因となっています。
責任感の重さと事故への不安
保育士は、子どもたちの安全を守る重要な役割を担っています。そのため、保育士は常に責任感をもって指導にあたらなければなりません。子どもと接する業務における責任感の重さと事故への不安も保育士不足を引き起こしています。
休暇の取りにくさ
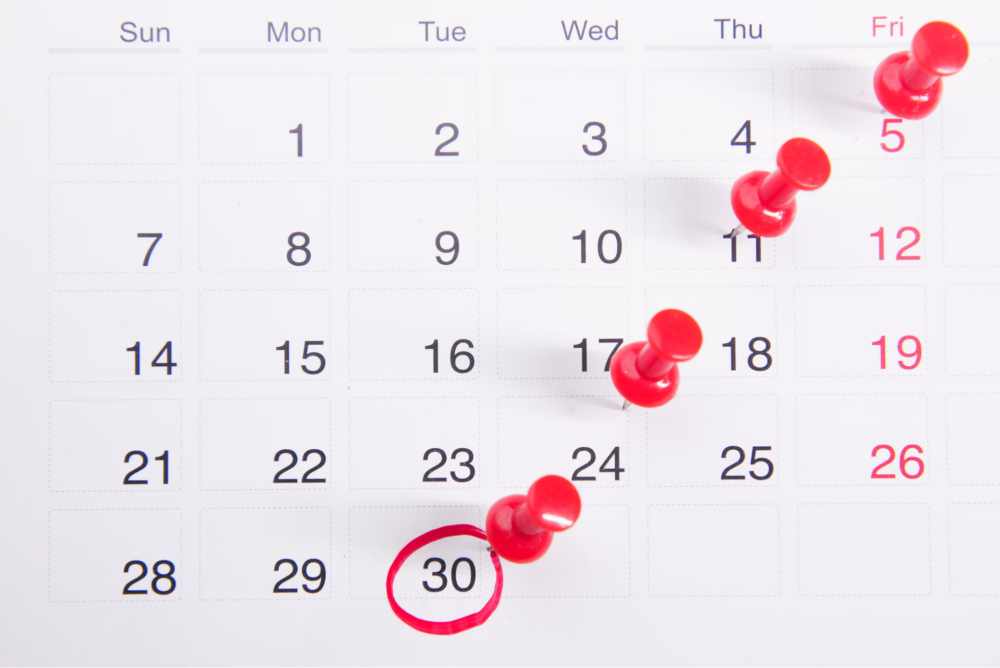
土曜日に開所する保育園も多く、保育士は休暇を取りづらい傾向にあります。リフレッシュするための時間を十分に確保できず、不満を募らせる保育士も多いです。休暇の取りにくさも保育士不足や退職率の増加を招いています。
以下の記事では、保育士の年間休日について解説しています。
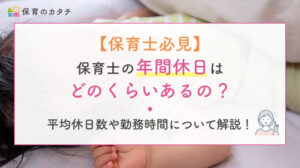
人間関係の悩み
保育園や幼稚園では、保育士同士が密に連携して働くことが求められます。しかし、保育士のなかには、人間関係に悩む方もいます。
保育士には女性が多く、女性特有の人間関係の難しさに悩まされる保育士の方も多いです。このようなストレスから退職する保育士の方もおり、保育士不足につながっています。
幼保施設以外への就職を希望している人の多さ
保育士資格を持っている人のなかには、保育園や認定こども園ではなく、企業内保育所や放課後児童クラブ、事務職などへの転職を希望する人も増えています。
また、保育士として働いた後に、福祉系や教育系の別職種に転身するケースも多くあります。結果的に、保育施設での就労希望者が減少していることも人材不足の一因です。
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/
保育士の人手不足によって起こる問題

保育士不足が深刻化すると、直接的な影響を受けるのが「保護者」と「子どもたち」です。都市部では保育施設に入りたくても入れない「待機児童」の増加が顕著になります。待機児童の問題は、保護者の就労継続を妨げ、家庭の収入や社会全体の労働力確保にも悪影響を及ぼす可能性があります。
保育士の人手不足とその影響

保育士不足は、単なる「人材難」にとどまらず、社会全体に影響を与える深刻な問題へと発展しています。以下では、具体的な2つの影響を紹介します。
社会問題が起こる
保育士不足によって保育園の定員を確保できず、待機児童が増加すれば、共働き家庭やひとり親家庭が仕事を続けられなくなります。都市部では、保育園に入れないことが原因で、女性のキャリアや家庭の収入にも大きな影響を及ぼす可能性があります。
また、保育士の人手不足による影響は、家庭内の問題だけではありません。子どもを安心して預けられないことへの不安から、出生自体をためらう若年層も少なくなく、結果的に出生率の低下にもつながると懸念されています。
保育の質が低下する
人手が足りない保育園では、保育士一人ひとりの業務負担が増加します。その結果、子どもたちに十分な目が行き届かなくなり、細やかな保育や個別対応が困難になります。特に乳児保育では、食事・排泄・睡眠など日々のケアを丁寧にする必要があるため、十分な職員配置が不可欠です。
また、時間外労働が増えることで、職員の疲弊やストレスが蓄積し、保育の質そのものが下がる可能性があります。結果として、保育の質が下がれば、保護者からの信頼低下や職員のさらなる離職につながる可能性があることから解決策を講じる必要があります。
保育士不足解消のために保育園が取り組める解決策

保育士不足は、日本全国で深刻な問題となっています。各地の自治体や保育園・幼稚園などでさまざまな取り組みがされていますが、未だに解決されていません。そこで、保育士不足解決のために幼保施設が取り組める対策を4つ紹介します。
給料を上げる
保育士の給料は、他の業種よりも低い水準にあります。そのため、保育士はさまざまな業種に流れてしまいます。給料を上げることで、保育士のやりがいやモチベーションを向上させることができるでしょう。
残業時間や休暇の少なさを改善する
保育士は業務の忙しさから休暇を取ることが難しく、残業時間も長くなりがちです。そのため、保育園は、保育士の負担を減らすために残業時間や休暇の少なさを改善する必要があります。必要に応じて職員を増やすことで、一人ひとりに負担を軽減することが可能です。
職場の雰囲気を良くする

保育園の職場は、子どもにとっても保育士にとっても長時間過ごす場所です。そのため、職場の雰囲気が悪いと保育士のストレスが蓄積し、退職につながることもあります。保育園は、職員同士のコミュニケーションを促進するなど、職場の雰囲気を良くするための対策をする必要があります。
ICTを導入する
連絡帳や出席簿、日誌などの事務作業をICT化することで、保育士の業務負担を大幅に軽減できます。保護者との連絡もアプリで完結できれば、書類作成や情報共有の効率が高まります。また、写真整理や献立表の管理、園内掲示物の作成もデジタル化することで、業務効率を改善することが可能です。
以下の記事では、ICTを導入するメリットを詳しく解説しています。ICT導入について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
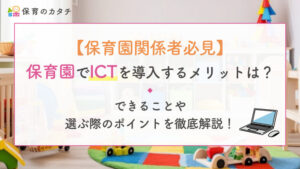
保育士不足を解消するための国による対策

国も保育士不足の深刻さを受け、さまざまな政策を打ち出しています。なかでも、以下の3つの取り組みは今後の保育業界を支える上で重要な柱となる施策です。
- キャリアアップ研修・処遇改善
- 子ども未来戦略
- 潜在保育士の再就職支援事業
それぞれ順に紹介します。
キャリアアップ研修・処遇改善
保育士不足を解消するための柱として、「キャリアアップ研修」と「処遇改善等加算」が制度化されています。これは、保育士が職務に応じた役割を担いながらスキルを高め、その貢献度に応じた給与加算を得られる仕組みです。
長時間労働の是正や事務作業の軽減を目的とした配置基準の見直し、保育士1人あたりの子ども数の適正化など、負担軽減と待遇改善の両立を図っています。
2025年度以降は、子ども家庭庁によって新たな処遇改善補助制度の導入も予定されており、より柔軟に各園の事情に対応できる運用が模索されています。
子ども未来戦略
「子ども未来戦略」とは、政府が掲げる少子化対策の中核であり、保育士不足の解消にも大きく関わる国家的取り組みです。子ども家庭庁が中心となり、子育て支援・保育制度改革・人材確保を3本柱として推進しています。
この戦略は、保育士の配置基準の見直しや処遇改善にとどまりません。保育現場でのICT導入促進や労働時間の適正化、育児と仕事の両立支援など、働き続けやすい環境整備に重点が置かれています。特に、時間外労働を抑える体制づくりや代替職員の確保など、園運営全体に関わる支援が強化されつつあります。
潜在保育士の再就職支援事業

保育士資格を持ちながら現場から離れている「潜在保育士」は、全国に約100万人いると推定されています。国や自治体では、こうした潜在人材を再び保育の現場に戻すための再就職支援事業を展開しています。
主な支援内容は、ブランク期間を補う研修や職場体験、ハローワークや就業支援センターでの相談対応などです。最近では、eラーニングによる研修や保育施設見学会などのサポートもあり、再就職への不安を払拭するための体制が整備されています。
以下の記事では潜在保育士について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
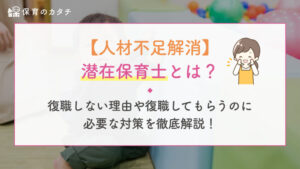
【まとめ】保育士不足は対策が必要

この記事では、保育士不足について解説しました。保育士不足は、日本社会が抱える深刻な問題です。国は保育士不足を解決するための対策に取り組んでいますが、保育園側も対策する必要があります。
保育園が保育士不足を解消するための対策としては、給料の上昇や残業時間・休暇の少なさの改善などが挙げられます。また、保育士の待遇改善や福利厚生の充実、働きやすい環境の整備など、保育士が長く仕事を続けやすい保育園を目指すことも重要です。
保育士不足に悩まされる保育園の採用担当者の方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/
保育士の採用をするなら保育のカタチがおすすめ
引用元:保育のカタチ
保育士の採用をするなら保育のカタチがおすすめです。
保育のカタチは日本で唯一、幼保業界の「人」に関する問題解決に特化した専門家集団です。採用から社員教育、それらの仕組み化まで幅広く取り組んでおり、人手不足の保育業界の中で、幼保施設にとって最善のパートナーが見つかるようなお手伝いをしています。
採用がうまくいかず悩んでいる方はぜひ一度保育のカタチにご相談ください。
| 住所 | 〒550-0004大阪府大阪市西区靱本町1-7-22 SKKビル201 |
| 許可番号 | 厚生労働大臣許可番号有料職業紹介事業:27-ユ-303764労働者派遣事業:派27-304996 |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員、パート |
| 求人施設 | 保育園、幼稚園、認定こども園、病児保育、事業内保育、学童保育、託児所など |
| 対応エリア | 全国 |
| 連絡手段 | 電話番号:06-6210-5326 |