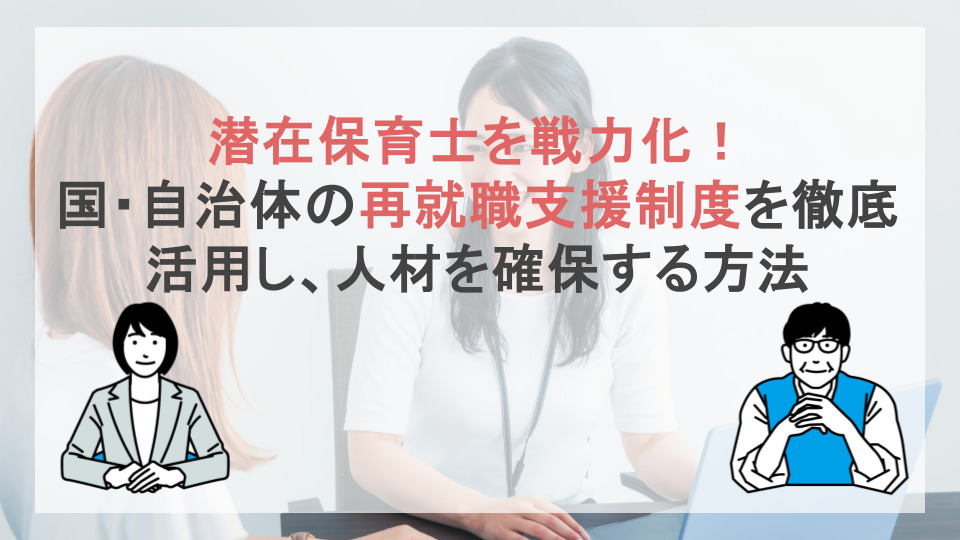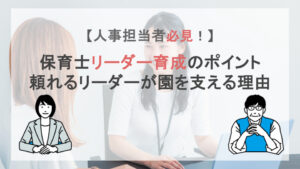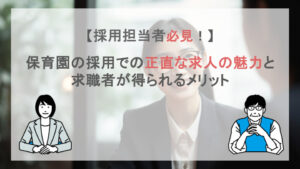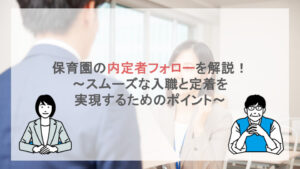保育士不足が深刻化するなか、保育士資格を持ちながら現場を離れている“潜在保育士”の活用は有効な手段のひとつとなっています。本記事では、潜在保育士が職場復帰をためらう背景と、国や自治体が提供する支援制度を踏まえた人材確保の方法を解説します。
また、保育士の就業環境改善に不可欠な雇用管理の見直しや職場体制の整備など、対象者が安心して働ける具体策についても紹介します。保育人材の不足解消と質の向上を図るために活用できるポイントを網羅していますので、ぜひご覧ください。
近年、潜在保育士の数は全国的に増加傾向にあるとされ、さまざまな要因が復職の壁になっています。そこで、現状把握と具体的な活用策を知ることが、保育業界を支えるための大きなカギとなるでしょう。
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/
潜在保育士とは?活用の重要性と背景

潜在保育士とは、保育士資格を保有しながら保育の職に就いていない人々を指します。この存在が注目されている背景と、活用の意義について見ていきましょう。
潜在保育士は、保育士資格を取得しても別の職種で働いていたり、家庭事情などで保育現場に復帰できていない人々のことを指します。保育士不足が続く中、こうした人々の活用は人材確保における大きな可能性として注目されています。しかし、実際にはブランクや労働条件などの壁があり、十分に活躍できていないケースも少なくありません。
この潜在保育士を有効に戦力化できれば、待機児童問題の解消や保育の質向上に大きく貢献できるでしょう。政府や自治体も予算を投じて再就職支援制度や雇用管理改善を進めており、保育現場の人材不足を解消する手がかりとしています。こうした背景から、潜在保育士活用は保育業界だけでなく、社会全体の課題解決に結び付く重要なテーマとなっています。
保育人材の需要と供給の現状
保育の現場では引き続き人材不足が課題となっています。その需要・供給構造を理解することで、潜在保育士が活躍できる場面が見えてきます。
保育業界における人材需要は、少子化が進む一方で保育サービスの多様化や女性の社会進出の後押しなどにより依然として高まっています。特に都市部では待機児童問題が深刻化しており、保育施設側は人手不足による保育の質低下を懸念する声が強まっています。こうした背景から、国や自治体は施設拡充や保育士の処遇改善を進めているものの、供給面では依然として課題が山積みです。ここで役立つのがすでに資格を持つ潜在保育士の存在であり、早期の戦力化が求められています。
慢性的な保育士不足と社会的影響
保育士不足は子どもを預けたい保護者に多大な影響を与え、待機児童の増加や保育の質の確保が大きな課題となっています。この不足問題が長期化すれば、親の就労や地域の経済活動にも影響が及び、社会全体の活力低下につながりかねません。保育士一人ひとりの負担が増えると、離職率の上昇や現職者のモチベーション低下を招く恐れも出てきます。よって、潜在保育士の力を活用する意義は非常に大きいといえるでしょう。
潜在保育士数の推計と就業意欲の現状
厚生労働省の推計によれば、保育士資格を持ちながら働いていない潜在保育士は全国で100万人を超えるともいわれています。その中には、出産や子育て、介護などさまざまな事情で職場を離れたものの、再就職への関心を抱く人も少なくありません。ただし、復職に対する不安や条件面の折り合いがつかず、実際に保育現場へ戻るまでには至っていないケースが多く見られます。こうした潜在保育士の就業意欲を喚起し、現場とマッチングさせる仕組みづくりが今後の鍵となるでしょう。
潜在保育士が再就職をためらう理由
保育資格を持ちながら現場を離れたままの人々には、復職を阻むさまざまな要因が存在します。それらを具体的に把握することが第一歩です。
潜在保育士は保育士としての能力を持つにもかかわらず、さまざまな理由で職場復帰を選択できていません。これには、保育の現場から長く離れていたことによるスキル面での不安や、依然として問題視される労働環境の厳しさなどが挙げられます。また、家庭との両立や働き方の柔軟性が確保されないと、再就職を踏みとどまる人も少なくありません。こうした要因を理解し、解消に向けた方策を講じることで、潜在保育士の再就職を促進できる可能性があります。
資格や実務経験への不安
ブランクが長い場合、最新の保育指導法や子どもの発達段階に合わせたケアに自信を持てない潜在保育士も多いです。特に、医療的ケア児や外国人児童の受け入れなど、保育現場が多様化していることへの戸惑いも増えています。一方で、研修やOJTを通じて十分に復職をサポートしている施設もあるため、不安を解消する環境さえ整えばスムーズな職場復帰が可能だといえます。そのためにも、事業者側は復帰前の研修制度などを整備し、不安を先回りして取り除くことが大切です。
労働条件や職場環境への不満
保育士の給与水準や長時間労働の問題は、長く業界全体の課題とされてきました。実際に、保育士の平均賃金が他の職種に比べて依然として低い水準にあることは、復職をためらう理由の大きな一つです。また、職場の人間関係や時間外労働の多さも、現場に戻ることを躊躇させる要因になります。こうした環境の改善が進まなければ、潜在保育士が再就職しても短期間で離職するリスクが高まります。
家庭との両立やライフステージの変化
子育てや介護を抱える保育士にとって、フルタイム勤務が難しいケースも多く見受けられます。出産や育児などでライフステージが大きく変化すると、勤務時間の制約やシフトが合わなくなることも再就職をためらう大きな理由です。保育現場では人手不足が続いているため、柔軟な勤務形態を提供できない施設も少なくありません。これらの事情から、家庭との両立を支える体制づくりが求められています。
事業主が利用できる支援策と取り組み
潜在保育士を雇用するために、事業主が活用できる国や自治体の支援制度について、具体的な例を挙げながら紹介します。
保育施設経営者にとって、潜在保育士の活用は人材不足の解消だけでなく、保育サービスの質を高める上でも大きなメリットがあります。再就職支援策や補助制度を上手に組み合わせれば、財政的負担を和らげつつ長く働きやすい環境をつくり出すことも可能です。実際に多くの自治体では、設備投資や人材育成の費用をサポートする制度を設けており、潜在保育士とのスムーズなマッチングを後押ししています。こうした支援の存在を知り、積極的に利用することで、より魅力的な就業環境を整えられるのです。
支援策全般~国や自治体の補助制度
国や自治体は、保育士の再就職を促進するためにさまざまな補助制度を用意しています。例えば、再就職準備金貸付制度では、一定期間働いた後に貸付金の返済を免除する仕組みが整備されており、復職の経済的負担を軽減できます。さらに、一部の自治体では、施設整備費や研修費用を補助する制度など、施設側が負うコストの負担を軽減する施策も展開されています。こうした援助を最大限活用することで、事業主と潜在保育士の双方が安心して再就職へ踏み出せると言えるでしょう。
雇用管理改善による働きやすい職場づくり
長く働き続けるためには、賃金や福利厚生などの雇用管理の見直しが不可欠です。処遇改善加算などを有効に活用し、給与水準の底上げを図ることは、潜在保育士の復職意欲を高める大きな要素となります。また、職員同士のコミュニケーション活性化やチームワークの推進など、職場環境の改善も重要なポイントです。結果的に、定着率が上がり、安定した保育サービス提供につながるでしょう。
求人と求職のマッチング支援~再就職の具体的な方法
ハローワークや保育士バンクなどの専門求人サイトを活用すれば、潜在保育士と保育施設の間でスムーズなマッチングが期待できます。自治体によっては、専用の相談窓口や就職フェアを定期的に開催し、人材確保と保育士の職域復帰を実現する仕組みを整えています。また、実際の職場見学や職員とのコミュニケーション機会を設けることで、求人情報だけではわかりにくい職場の雰囲気を伝えられるでしょう。こういった取り組みによって、採用後のミスマッチを防ぎ、定着率の向上が図れます。

能力開発支援~人材育成と就業継続の重要性
潜在保育士が安心して働き続けられるように、研修費用の補助やOJTの充実などが各地で検討・実施されています。実務能力を着実に高める機会が確保されれば、自信を持って保育現場に戻る働き手が増えるでしょう。さらに、企業内研修や外部研修への参加を促進することで、スキルアップだけでなく職場内でのコミュニケーション促進にもつながります。人材を育成し続ける風土を作ることが、潜在保育士の定着と保育の質向上に直結するのです。
潜在保育士が安心して働ける具体策

実際に職場に復帰するうえで必要なサポート体制を整えることで、潜在保育士が安心して就業を継続できます。
潜在保育士が復職した後に長く活躍するためには、受け入れ体制の整備や個々の事情を考慮した制度設計が欠かせません。ブランクを埋める研修機会の提供や、働き方の柔軟化といった具体的な仕組みを整えることで、復職への心理的ハードルを下げる効果が期待できます。また、メンターによるフォローやチームでのサポート体制を整えることで、トラブルや不安の芽を早期に発見・対応することができます。結果として、職場環境の改善が保育サービス全体の質向上にも大きく寄与するのです。
職場復帰研修やスキルアップ制度の導入
保育に関する最新の理論や実践を学び直せる研修プログラムは、ブランクがある潜在保育士にとって大きな助けになります。専門性の高い研修のほか、育児中の人でもオンラインで受講できる講座を用意するなど、多様なニーズにあわせたスキルアップ制度を導入することが大切です。こうした学習機会を確保すれば、保育の現場に戻る自信をつけられるだけでなく、子どもの成長に応じた質の高い保育を提供しやすくなります。定期的な研修制度を定着させることで、保育士のモチベーション維持にもつながるでしょう。
短時間勤務制度やシフトの柔軟化
家庭の事情やライフステージの変化でフルタイム就業が難しい保育士にも働き続けてもらうには、短時間勤務やフレキシブルなシフト設計が欠かせません。保育業界では朝晩など特定の時間帯をカバーできる人員が不足しがちなため、日中のみの短時間勤務でも戦力として期待される場面は多くあります。こうした制度が整備されることで、潜在保育士の働き方と施設ニーズの両立が可能となり、離職を未然に防げるでしょう。結果的に、保育サービスを安定して提供しやすくなるメリットも大きいのです。
メンター制度やチーム体制によるフォロー
経験豊富な先輩保育士が定期的に相談に乗るメンター制度は、復職者にとって大きな支えとなります。チーム体制を敷くことで個々の保育士の業務負担が偏らず、困ったときにすぐフォローを受けられる安心感が生まれます。特に、保育方針や保護者対応など現場特有の課題共有はメンターやチーム間のコミュニケーションが不可欠です。このような仕組みを整えておくことで、潜在保育士が抱える不安を軽減させ、長期就業につながります。
保育士の就業の実態と見通し
保育現場の変化や将来的な需要など、保育士として就業を考えるうえで知っておきたいポイントを整理します。
これからの保育現場は、多様な保育ニーズに応えるためにさらなる改善と拡充が進められる見通しです。共働き世帯の増加や子育て支援への意識の高まりにより、新設の保育施設や自治体の取り組みが増え続けています。一方で、保育の質を維持・向上させるためには、十分な人材の確保とスキルアップが不可欠です。そうした流れのなかで、潜在保育士の活用は将来にわたる保育サービスの安定供給にとって大きなカギとなるでしょう。
保育需要の拡大と現場の変化
待機児童対策として建設された保育施設の増加に伴い、現場では新たな雇用ニーズが高まっています。同時に、子どもの多様な背景や特別な支援を要するケースの増加により、保育士の専門知識やスキルのアップデートが求められています。さらに、ICTの導入や事務作業の効率化なども進展し、保育の在り方そのものが変化を続けています。これらのトレンドに対応できる体制を整えることで、より安心・安全な保育が実現できるでしょう。
保育現場におけるキャリアパスと将来性
保育士は一定の経験を積むことで、主任保育士や施設長などキャリアアップを目指すことが可能です。また、子育て支援センターや企業内保育所など、多様な就業形態にも活躍の場が広がっています。さらに、近年は保育と福祉を連携させた新しいサービスも増え、潜在保育士が新たに能力を発揮できるフィールドが拡大傾向にあります。将来性のある職種として魅力を高めるためにも、継続的なスキル研さんとキャリア形成の支援が重要です。
保育人材確保対策の基本方針
国や自治体はどのような方針で保育人材を確保しようとしているのでしょうか。今後の対応指針を見ていきます。
近年、保育士の離職率を下げるための取り組みが加速しており、資格取得者の定着と復職支援に注力する方針が示されています。具体的には、給与改善や研修費補助のほか、人員配置の基準見直しなど段階的な規制緩和も含まれています。これらの取り組みは保育現場の負担軽減だけでなく、質の高い保育サービスを提供する基盤づくりにもつながります。潜在保育士活用という視点が、今後の人材確保策において特に重要視されるでしょう。
政策動向と今後の方向性
国が推し進める保育士処遇改善制度は、潜在保育士にとっても大きな魅力となる可能性があります。加えて、高まる保育ニーズに応えるため、施設や事業主が柔軟な働き方を取り入れやすいように環境を整える動きも進行中です。これらの政策動向を受け、待遇と職場環境の両面から保育士の復職を後押しする施策がさらに拡充される見込みです。今後は、自治体・民間の枠組みを超えた連携強化も注目されるでしょう。
多様な保育サービスとの連携強化
認可外保育施設や企業内保育所、さらには地域子育て支援拠点との連携を強化することで、保護者の多様なニーズに応えやすくなります。地域全体で子育てをサポートする体制を構築するには、潜在保育士を含む人材の確保と適切な配置が不可欠です。複数のサービスと連携することで、働き手にとってもさまざまなキャリアアップや就業形態が選択肢となり、やりがいを持って長く働ける場が広がります。実際の事例として、自治体主導の複数施設合同研修や情報共有会が実施され、相互に力を補い合う動きが加速しています。
まとめ・総括
ここまで紹介してきた潜在保育士の活用と支援策を総括し、今後の方向をまとめます。
潜在保育士は、深刻化する保育人材不足解消の大きな可能性を秘めた存在です。再就職をためらう要因を明確に把握し、職場環境の改善や支援制度の活用を進めることで、多くの有資格者を現場に呼び戻すことができます。その結果、待機児童問題の改善や保育サービスの充実といった社会的課題の解決にもつながります。
今後は、国や自治体による処遇改善や多様な保育サービスとの連携がさらに推進され、保育施設と潜在保育士双方がメリットを得られる環境が整うことが期待されます。人材確保の取り組みを単なる補助や支援策にとどめず、組織運営やキャリア形成の視点から継続的に取り組むことが大切です。潜在保育士を活用していくことで、保育の質を高めながら社会全体で子育てを支える土台をより強固にしていきましょう。

\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/