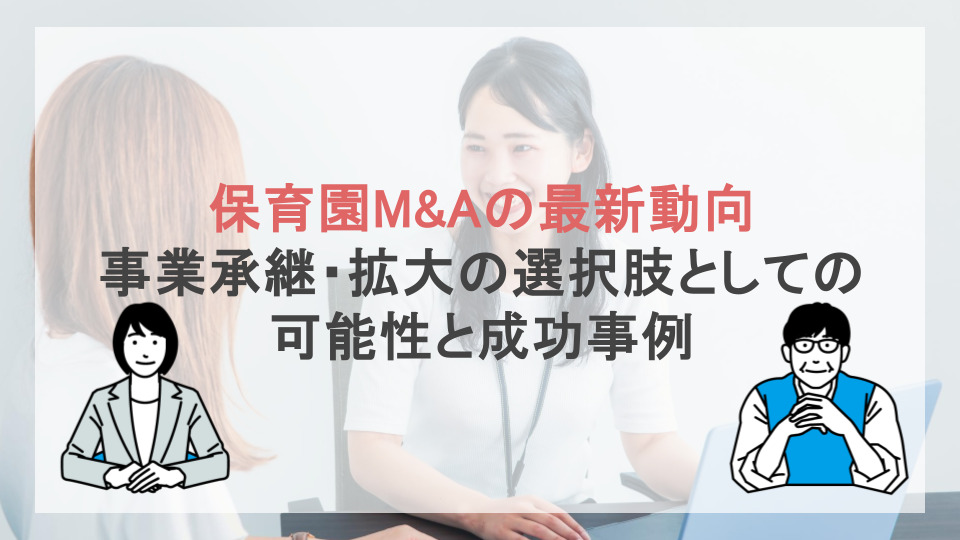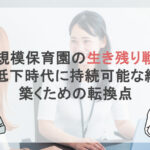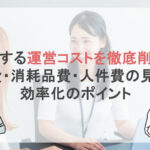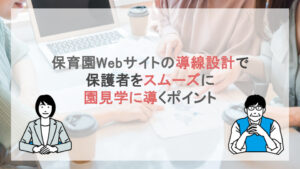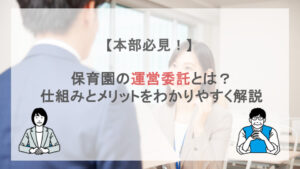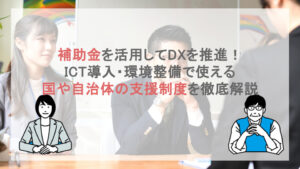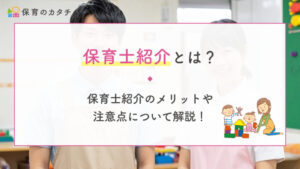保育園業界では、少子化や事業承継問題などを背景にM&Aの動きが活発化しています。本記事では、保育園M&Aの基本的な概要から主要なステップ、社会福祉法人特有の手続きや成功事例まで網羅的に解説します。今後の展望も含め、保育園M&Aがどのような選択肢を提供するのかを考察します。
ここ数年は待機児童の解消を目指す国の施策が続けられてきましたが、地域によっては定員割れが生じるケースも増え、保育園の経営環境は二極化しつつあります。その一方で、現場では保育士不足が依然として大きな課題となっており、経営の安定や運営効率化を求める声が高まっています。こうした背景が、保育園業界におけるM&Aをより現実的な選択肢として押し上げていると言えるでしょう。
本記事を読むことで、保育園M&Aの基礎から具体的な進め方、売却価格の算定や社会福祉法人特有の手続きまでを幅広く理解できます。特に、保護者や職員への対応、自治体との連携など、実務面でのポイントにも触れるので、保育事業の将来を考える方々にとって有益な情報となるでしょう。

\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/
保育園・保育所の定義と分類

まずは保育園・保育所の仕組みや分類を整理し、それぞれの特徴を理解しましょう。
保育園・保育所は、0歳児から就学前の子どもたちを対象に、保護者の仕事や育児状況に応じて保育を提供する施設です。基本的に子どもの発達を促し、安心・安全な環境で社会性を育むことが大きな役割とされています。自治体からの補助金を受ける認可施設もあれば、比較的独立した形で運営される認可外施設もあり、実態は多様です。
保育能力や設備、地域ニーズによって施設の魅力は大きく変わるため、その分類を把握することは重要です。保育園・保育所の性格を理解しておくと、M&Aの際に施設の強みや課題を把握しやすくなります。また、経営する法人形態によっても手続きや規制の対象が変化するため、事前に全体像を理解することが欠かせません。
多様な保護者や子どものニーズを満たすために、認可か認可外か、企業内設置なのか公的認可なのかといった形態の違いが生まれています。それぞれの施設が持つ特色や強みを正しく認識すれば、M&Aの際にも売り手・買い手双方がスムーズに検討を進めることが期待できるでしょう。
認可保育園と認可外保育園の違い
認可保育園は、行政から運営基準や施設基準の承認を受けた施設であり、補助金を受け取ることができるのが大きな特徴です。その分、施設の広さや保育士の配置基準などを厳格に守る必要があり、運営コストが比較的高くなることも多いです。
一方、認可外保育園は基準の制約が比較的少なく、保育時間の延長やサービスの独自性などを打ち出しやすい利点があります。最近では多様な子育てニーズに応えるため、夜間保育や一時保育などを積極的に取り入れる認可外保育園も見られます。
こうした違いはM&Aの際の評価ポイントにも直結します。行政の補助事業で安定収益を得やすい認可保育園が高く評価される一方、認可外保育園でも独自性や立地面の強みを活かし、魅力をアピールすれば買い手の関心を集められる可能性があります。
企業主導型保育園と認定こども園の特徴
企業主導型保育園は、企業が従業員や地域の子どもを受け入れるために設置する保育施設で、国の補助金を活用して運営することが多いです。企業にとっては従業員の福利厚生を充実させ、定着率を高めるメリットがあるため、近年利用が拡大しています。
認定こども園は保育園と幼稚園の機能を併せ持つため、長時間保育や幼児教育を同時に行うことが可能です。子どもたちに連続した教育・保育環境を提供できる点が保護者から評価されるだけでなく、自治体の施策上も重宝される施設形態です。
企業主導型保育園や認定こども園を含む幅広い運営形態が、保育園M&Aの選択肢を増やしています。買い手側は既存の法人形態に合った施設を取り込むことで事業規模を効率よく拡大でき、売り手側は企業主導型などの魅力的な運営形態を提示することで、より高い譲渡条件を期待できるでしょう。
保育園M&Aが増えている背景
保育園の売買や合併が進む背景には、社会的・経済的な要因が存在します。
保育園市場は待機児童の問題を抱えつつも、少子化による定員割れが地域によって生じるなど、需要と供給のバランスが著しく変動しています。特に都市部では保護者の就業率が高いため待機児童が依然として課題になる一方、地方では園児数の減少や後継者不足が深刻です。
こうした状況から、複数の法人が相互に協力し合って保育サービスを提供する動きが活発化しており、M&Aはその一つの手段として注目を集めています。法人同士の統合により、経営効率化やスケールメリットを得ることができ、職員の確保や育成を共同で行う例も増えています。
また、保育士不足や人件費の増大などが原因となり、赤字経営に苦しむ保育園が多いのも事実です。これらの課題を根本的に解決するために、M&Aを選択して事業基盤を強固にしようとする動きが目立つようになってきました。
少子化・待機児童数の変化と市場構造
少子化が進む一方、働き方の多様化によって保育ニーズは高まり続けています。その結果、特定エリアでは待機児童が解消されない状況もある反面、子どもの数が減るエリアでは定員数を大きく下回る保育園が増加しました。
このアンバランスな状況は、単に施設数を増やすだけでは解決が難しく、保育サービス全体の再編が求められています。M&Aによって自主的にエリア撤退や事業集約を進める例もあり、限られた保育士のリソースを有効活用する動きが起こっています。
結果として、保育園同士がネットワークを組むことで人材をシェアしたり、運営コストを分担したりする事例が見られます。こうした流れは保育園M&Aを利用した業界再編の背景の一つといえるでしょう。
後継者不足への対応
保育園を長く運営してきた経営者が高齢化する一方で、組織を引き継ぐ後継者が不足する問題があります。社会福祉法人であっても、理事や管理者を担う人材の確保が難しくなると、将来的な存続が危ぶまれます。
そこで、後継者を内部で育成するだけでなく、他法人との合併や譲渡といった方法で事業承継を図る動きが活発化してきました。特に、保育事業におけるノウハウや経営資源を外部から取り入れられる点が、M&Aを選択する大きな理由となっています。
後継者不足の課題を解決するには、事業の安定や職員・保護者への信頼維持が欠かせません。M&Aの計画段階から職員や保護者への周知・説得を丁寧に行うことで、円滑な事業承継を実現するケースが増えています。
社会福祉法人のM&Aとは
保育園の多くが社会福祉法人によって運営されるため、法人特有のM&A手続きを理解することは重要です。
社会福祉法人は、非営利性を重視する法律の下で運営されているため、一般企業のM&Aとはステップが異なります。例えば法人合併や事業譲渡の可否について、所轄庁の認可や許認可が必要になるケースが多く、手続きが複雑化しやすいです。
その一方、社会福祉法人同士のM&Aが進むことで、財務基盤の安定化や運営効率の向上を狙えるメリットもあります。施設の統合によるスケールメリットを活かすことで、保育士の待遇改善や保育の質向上に取り組む法人も増えています。
合併や譲渡の際には、職員や保護者の理解と協力が不可欠です。非営利法人であっても、事業承継や拡大の手段としてM&Aを活用するケースが増えており、行政との連携をしっかりと図ることが成功のカギとなります。
社会福祉法人におけるM&Aスキーム
社会福祉法人のM&Aには、合併や事業譲渡、運営権の移管などさまざまな形態があります。合併では複数の法人が統合されることで法人格が一体化し、資産や負債を包括的に引き継ぐ点が特徴です。
事業譲渡の場合は、保育事業のみを切り出して譲渡する形になるため、それ以外の事業を持つ社会福祉法人にとっては負担を最小化しやすい方法と言えます。ただし、譲渡先が同じく非営利法人である必要がある場合が多く、公益性の確保が大前提です。
いずれのスキームを選択するにしても、法的手続きや所轄庁への申請などクリアすべき課題が多いため、専門家のサポートが非常に重要になります。
重要な許認可と留意点
社会福祉法人の合併や事業譲渡には、厚生労働省や自治体の許可が必要です。許認可の取得には事前協議や書類作成、審査期間の確保などが必須であり、通常の企業間M&Aよりも時間と手間がかかりやすい点に注意が必要です。
特に保育園は子どもの安全と健全な発育に責任を負う施設であるため、自治体との連携を密にすることが求められます。事業譲渡後の運営体制や施設の継続性についても厳しくチェックされることが多く、計画段階から入念な準備を行うことが重要です。
また、職員の雇用継続や給付金の取り扱いなど、非営利法人ならではの留意点も多岐にわたります。M&A後に混乱が生じないよう、あらかじめ合意内容や運営方針を明確にしておくことが成功への鍵となります。
保育園M&Aの進め方と主要なステップ

円滑なM&Aのためには、計画立案から契約締結・統合までのプロセスを段階的に進めることが大切です。
保育園M&Aでは、最初に売り手の事業内容や体制を把握し、買い手のニーズに合致するかを見極める事前準備が重要です。保育士の確保状況や施設の立地条件などに加えて、保護者からの評判も評価ポイントとなるため、事前に情報を整理しておく必要があります。
また、法的手続きや資金調達の面では、M&Aに精通した専門家のサポートが欠かせません。デューデリジェンスや契約書の作成などで手戻りを防ぐには、早期の段階から税理士・弁護士などとの連携を図ることが望ましいでしょう。
最終的にPMI(統合後のマネジメント)まで視野に入れた計画を練ることで、組織文化の違いや職員の不安を最小限に抑えられます。特に保育園の場合、保護者からの信頼は大切なので、M&A後も円滑に園運営を行えるよう、具体的な対応策を準備することが成功へとつながります。
事前準備とアドバイザー選定
M&Aを検討する際には、まず自園の経営状況や課題を明確化することが第一歩です。具体的には、財務データや経営計画、職員の離職率や保育質の評価などを整理し、改善すべき点を把握しておくことが大切です。
その上で、M&Aの経験を持つアドバイザーや仲介会社を選定します。保育業界に特化した専門家であれば、保育士確保の困難さや自治体対応の重要性など業界独自の事情を熟知しているため、スムーズにマッチングを進めやすいでしょう。
アドバイザー選定時には、手数料体系や過去実績、ネットワークの広さなどを比較検討し、信頼できるパートナーを見つけることが成功への近道になります。
トップ面談・基本合意の締結
売り手と買い手のトップ同士が実際に顔を合わせるトップ面談は、お互いの経営理念や方針が合致するかを確認する大切なステップです。保育の価値観が食い違うと、譲渡後の運営に支障を来す恐れがあるため、入念なコミュニケーションが求められます。
面談で一定の合意が得られたら、基本合意書を結ぶことが多いです。ここでは、譲渡価格やスケジュールの大枠、保育士の雇用継続方針など、M&Aの基本条件を取り決めます。後の交渉を円滑に進めるためにも、互いの意向を明確化しておくことが重要です。
保護者や職員へ初期段階から情報を伝える場合には、混乱を招かないようタイミングと内容に配慮する必要があります。社会福祉法人の場合は行政にも報告が必要なケースが多いため、適切なコミュニケーション体制の構築がポイントとなります。
デューデリジェンスと最終契約締結
デューデリジェンスでは、売り手の施設運営状況や財務状態、労務管理、許認可の実態などを詳細に調査します。特に保育園の場合、自治体から交付される補助金の扱いや、職員の資格状況なども重要な確認ポイントです。
このプロセスを通じて、M&A後のリスクや改善余地が洗い出され、買い手にとっての最終的な投資判断材料となります。また、売り手側にとっても適正な評価を得る機会となり、不明点があれば契約前に解消することができます。
互いに納得した上で条件が固まったら、最終契約を締結します。契約書には譲渡対象や対価、今後の統合プロセスなど詳細事項が記載されるため、弁護士などの専門家の助言を得ながら慎重に締結することが重要です。
PMI(経営統合後の課題)
PMIとは、経営統合後に起こるさまざまな課題と向き合い、組織を円滑に運営していくフェーズを指します。保育園では、職員の配置転換や給与体系の変更などが保護者の不信感を招かないよう、丁寧な説明と段階的な導入が求められます。
また、保育理念や教育方針のすり合わせは、園のアイデンティティを左右する重要なポイントです。買い手法人の経営スタイルと売り手園のカルチャーを統合するには、互いに歩み寄る姿勢が必要であり、時間をかけて調整を行います。
さらに、経理・会計システムやITシステムの統合も対応が必要です。特に補助金の申請や自治体への報告など、公的手続きが多い保育園だからこそ、円滑な情報共有と運営管理の仕組みづくりが統合後の成功を左右するでしょう。
保育園の売却価格と算定方法
適切な評価額の算出は、買い手・売り手双方が納得のいくM&Aのために不可欠です。
保育園の売却価格を算定する際には、財務諸表だけでなく、保育士の人員配置や施設の損耗状況、保護者の満足度といった定量・定性両面の評価が行われます。公的補助金の安定性なども評価額に大きく影響するポイントです。
DCF法(割引キャッシュフロー法)は将来のキャッシュフローを分析する手法であり、保育士不足による採用コスト増や、少子化による入園児数の見込みなどを織り込まなければなりません。マルチプル法では、同業他社の売却事例や収益指標をベースに比較し、相対的に評価する方法が用いられます。
適正価格の算定には、第三者の専門家や公認会計士などによる客観的な視点も必要です。ネガティブ情報を隠すのではなく、双方が透明性をもって情報提供することで、結果的に納得度の高いM&Aを実現しやすくなります。
株価算定の代表的手法(DCF法・マルチプル法など)
DCF法では、将来の運営計画やキャッシュフローの見通しから現在価値を算出するため、長期的に安定した入園者数を維持できるかが重要なポイントとなります。保育士の確保や自治体施策など、不確定要素を考慮する必要があります。
マルチプル法は、既存のM&A実績や同業他社の指標と比較するため、業界の相場感を把握する上で有用です。ただし、保育園の運営形態は多様であり、単純比較が難しいケースもあるため、複数の手法を組み合わせることが推奨されます。
数字だけに頼るのではなく、園の社会的評価や独自の教育方針も評価に影響します。他の企業や法人が参入を検討する際、こうした独自性が大きな魅力となるため、売り手としては積極的にアピールすることが有効です。
価格に影響する要素(立地・運営規模・許認可など)
好立地で通園アクセスが良い保育園は、保護者の満足度が高く、定員が埋まりやすい傾向にあります。そのため、都心部や公共交通機関が充実しているエリアの園は高い評価を得やすいです。
運営規模が大きいほど収益も期待しやすい反面、保育士数を確保する難易度も上がるため、買い手にとってはリスクを吟味する必要があります。施設の老朽化や改修費用の見込みも、売却価格に大きく影響します。
さらに、認可保育園や企業主導型保育園などの許認可ステータスも評価に反映されます。補助金の額や行政との関係性は、事業の安定性を測る指標となり得るため、売り手は許可取得の履歴や実績をしっかり整理しておくことが望ましいでしょう。
保育園M&Aのメリットとデメリット
M&Aには多くの利点がある一方で、注意すべきリスクも存在します。
保育園M&Aには、事業承継をスムーズに進められるという大きなメリットがあります。特に後継者難に直面している場合、法人同士の合併や譲渡で組織を存続させることが可能です。また、買い手にとってはエリア拡大やノウハウの取得を比較的短期間で実現できる点が魅力といえるでしょう。
しかし、経営方針の違いが大きい場合、譲渡後に職員の離職が相次いだり、保護者からの信頼を失ってしまうリスクがあります。特に保育園は子どもの教育・保育を担う機関であるため、社会的責任が重く、トラブルの影響は大きくなりがちです。
これらのメリットとデメリットを把握しておけば、M&Aを検討するうえで適切な判断材料となります。十分な情報収集と事前準備を行い、双方が納得できる条件で取引を進めることが重要です。
売り手にとっての利点とリスク
売り手の最大の利点は、退任や事業引退をスムーズに進められる点です。大切に育ててきた保育園を閉園することなく、新たな運営主体が継続することで地域貢献を続けることができます。
一方で、法人の名称変更や運営方法の違いから、職員や保護者の反発を招く可能性も無視できません。特に社会福祉法人の場合は非営利性や公益性の観点で外部の scrutiny を受けるため、透明性ある説明と合意形成が必須となります。
また、譲渡益によって新事業や個人の引退資金を確保できるメリットもあるものの、適正な価格で譲渡できるかは交渉次第です。事前に園の資産価値を把握しておくことで、リスクを最小化しつつ交渉を有利に進めることが可能になります。
買い手にとっての利点とリスク
買い手側にとっては、既に稼働している保育園を取得することで、ゼロから施設を建設・開設する手間や期間を圧縮できるメリットがあります。待機児童問題が深刻なエリアへ進出したい場合などには、特に有効な選択肢です。
しかし、職員の技術力や経営者のノウハウをうまく継承できないと、運営の質が低下してしまうリスクがあります。また、地域住民や行政との信頼関係を一から構築し直す必要があるケースもあるため、買収後のマネジメントが非常に重要です。
さらに、認可保育園であれば特有の補助金や規制の理解が不可欠で、手続きに誤りが生じると行政からの信頼を損ねる恐れもあります。買い手側は、M&A前から十分に運営体制や補助金制度の調査を行い、適切にリスクを管理することが求められます。
保育園M&A成功事例・事例研究

具体的な事例を通じて、保育園M&Aを成功へ導く要因について考えます。
保育園M&Aで成功を収めるには、行政との連携、職員の雇用、保護者への理解など、複数のステークホルダーとの協力体制が不可欠となります。実際の事例を参照することで、成功要因を具体的に把握できるのがメリットです。
認可保育園の事業譲渡や企業主導型保育園の統合、社会福祉法人同士の合併など、多種多様なケースが存在します。いずれも基本的には入念な準備と長期的視点でのメリット・デメリットの見極めが成功の鍵となります。
ここでは代表的なパターンを3つ取り上げ、それぞれのケースから学べるポイントについて解説します。
認可保育園の事業譲渡事例
ある都市部の認可保育園の事業譲渡事例では、自治体との事前協議がスムーズに進んだ点が成功要因となりました。行政担当者との信頼関係を構築することで、許認可の取り扱いが迅速に行われ、譲渡後の運営もスムーズに移行できたといいます。
また、譲渡先の法人が、既に同地域で複数の保育園を運営していたことも大きな利点でした。圧倒的な知名度や地域の人材ネットワークを活用し、職員の離職がほとんど起きず、保護者からの評価も高い状態をキープできました。
この事例からは、自治体をはじめとする関係各所との連携がM&A成功の要であることが分かります。また、地域に根差した運営実績がある法人にとっては、他の保育施設を取り込むことで運営効率をさらに高める好機になることが再確認されました。
企業主導型保育園の統合事例
企業主導型保育園では、企業が福利厚生として保育サービスを従業員や地域向けに提供します。ある大手企業が中小の企業主導型保育園を統合するケースでは、運営コスト削減と人材共有を同時に達成できた例があります。
企業主導型保育園は一定の国からの補助金を得られるため、財務基盤の安定に寄与しますが、その反面、独自の運営基準や職員配置の考え方が存在します。統合にあたっては、雇用契約や保護者との契約関係を整理する作業がポイントでした。
この事例では、企業内の専門チームと外部アドバイザーが共同で作業し、短期間のうちに統合が完了しました。統合後は保育士の派遣やキャリアパスを一本化し、職員のモチベーションとサービス品質を維持できたことが成功の決め手となっています。
社会福祉法人同士の合併事例
社会福祉法人同士の合併では、非営利性を維持しながら経営基盤を強化できるメリットがあります。ある事例では、複数の小規模法人が合併することで役員や理事の負担を分散し、より効率的な組織運営を実現しました。
また、資産や人材を統合した結果、保育士の待遇改善や研修制度の充実が可能となり、保育の質そのものを高めることにも成功しています。複数法人が共同で行動することで、地域社会からの信頼度を一層高められたという点も特徴的です。
非営利組織としての理念を共有し合い、共通の目標を掲げて合併を進めたことが円滑な統合作業につながりました。結果的に行政からの評価も高まり、追加の補助金や支援策を得るなど、好循環を生み出したケースとして注目されています。
【まとめ】保育園M&Aの動向と今後の展望
保育園M&Aは業界再編の一翼を担いつつあり、規模や地域を問わず多様な法人が参入を検討しています。今後は運営効率化や質の向上に向けたM&Aがさらに重要性を増すでしょう。
保育園業界では、少子化や保育士不足、後継者難といった課題が同時に進行しています。それらを打開する手段として、事業規模の拡大や効率的な運営を可能にするM&Aが、ますます注目を集めると考えられます。
今後は行政施策の変化や社会的ニーズの多様化に伴い、保育サービス自体のイノベーションが求められる時代です。M&Aによって組織力や専門性を強化し、新たな付加価値を提供する動きが広がることで、業界全体が進化していく可能性があります。
ただし、保育園は子どもの安全と成長を保障する重要な社会インフラであるがゆえに、M&Aには慎重さが求められます。行政との連携や透明性のある交渉を重ね、保育の質を最優先する姿勢を忘れなければ、M&Aは活発な市場再編の一助となるでしょう。

\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/