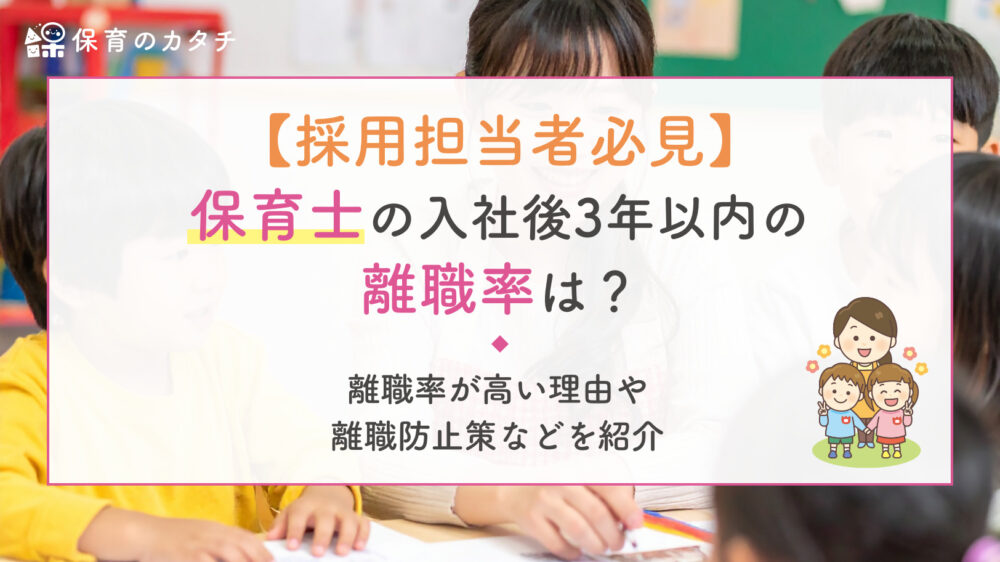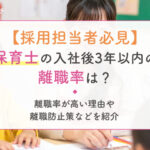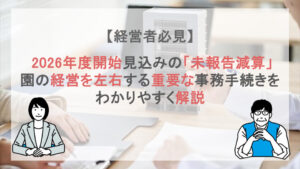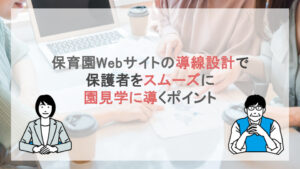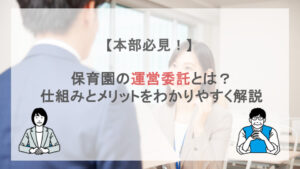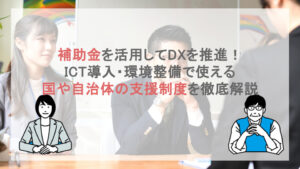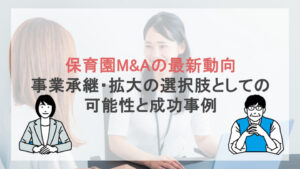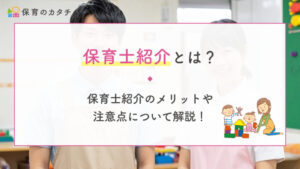保育士は長期間勤務する人がいる一方、僅か数年で退職する人も珍しくありません。「採用しても辞める人がいるのはなぜか」と気になっている方もいるでしょう。
そこで、この記事では保育士が辞める理由や入社後3年以内の離職率について解説します。保育士の離職率を下げるための改善策も紹介していますので、あわせて確認してみてください。
\支援実績1000社以上!園の全体最適を考えた採用をサポート!/
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/
保育士の採用をするなら保育のカタチがおすすめ
引用元:保育のカタチ
保育士の採用をするなら保育のカタチがおすすめです。
保育のカタチは日本で唯一、幼保業界の「人」に関する問題解決に特化した専門家集団です。採用から社員教育、それらの仕組み化まで幅広く取り組んでおり、人手不足の保育業界の中で、幼保施設にとって最善のパートナーが見つかるようなお手伝いをしています。
採用がうまくいかず悩んでいる方はぜひ一度保育のカタチにご相談ください。
| 住所 | 〒550-0004大阪府大阪市西区靱本町1-7-22 SKKビル201 |
| 許可番号 | 厚生労働大臣許可番号有料職業紹介事業:27-ユ-303764労働者派遣事業:派27-304996 |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員、パート |
| 求人施設 | 保育園、幼稚園、認定こども園、病児保育、事業内保育、学童保育、託児所など |
| 対応エリア | 全国 |
| 連絡手段 | 電話番号:06-6210-5326 |
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/
【最新版】保育士の離職率は?

保育士の離職率は医療・福祉の全体の平均より低めですが、慢性的な人材不足が続く保育業界にとって無視できない水準です。ここでは、最新データを整理して離職率について解説するので、ぜひ現場改善などの参考にしてみてください。
医療・福祉分野の離職率は14.6%
厚生労働省「令和5年雇用動向調査」によると、医療・福祉分野の離職率は14.6%(常用労働者ベース)で、全産業平均15.4%とほぼ同水準でした。また、前年度の15.3%と比べると、離職率が低下していることがわかります。
保育士の離職率が全体の離職率に比べて高いわけではありませんが、人手不足感の強まりが数字に表れています。保育士だけでなく、業界全体での離職対策が急務といえるでしょう。保育士の離職率に関しては、次に詳しく説明します。
参考:厚生労働省「令和5年雇用動向調査の概要」
保育士の離職率の推移
厚生労働省「保育士の現状と主な取組」とe-Stat「社会福祉施設等調査」に基づき、2015年以降の離職率推移を整理すると、以下のようになります。
保育士の離職率は、2015年10.3%→2017年9.3%→2019年9.2%→2022年9.3%と緩やかに低下した後、横ばい傾向です。直近数年は処遇改善加算や保育士確保策が一定の効果を示しましたが、コロナ禍での負荷増大が相まって横ばいになったと考えられます。
参照:厚生労働省「保育士等に関する関係資料」
厚生労働省「保育士の現状と主な取組」
e-Stat「社会福祉施設等調査」
運営形態別の離職率
厚生労働省によると、保育園の運営形態別離職率は公立が5.9%、私営が10.7%、幼稚園教輸10.6%の離職率です。私立より公立の方が離職率が低い背景には、公務員として勤務できることのほか、給与水準や休暇制度が整っていたり、ワークライフバランスを確保しやすかったりすることが関係していると考えられます。
一方、私立は運営資金の制約から人員配置がタイトになりがちで、残業や持ち帰り業務の負荷が大きい可能性があります。公営に比べて、待遇改善と労務管理の標準化が必要になるかもしれません。
参考:厚生労働省「保育士の現状と主な取組」
経験年数別の離職率

保育士の離職率は、経験年数を重ねるにつれて離職しやすい傾向にあります。厚生労働省の調査によると、経験年数が8年未満の保育士が全体の約半数を占めます。経験年数が2年未満の保育士は全体の15.5%で、それ以降は徐々に低下していきます。
一方、10年以上勤務している保育士はさらに少なくなり、長期間勤務する保育士は少ないです。私立での離職率は特に高いため、OJT計画やメンター制度で早期定着を支援する仕組みづくりが不可欠です。
離職率を低くする方法を知りたい方は、下記の記事もご覧ください。

保育士の離職率が高い理由

保育士の離職率は全体の離職率と比べると多くはないものの、依然として深刻な人材不足に悩まされています。なぜ、保育士は離職してしまうのでしょうか。保育士が辞める理由で多いのが、以下の8つです。
- 人間関係
- 仕事の量
- 給与の低さ
- 労働時間
- 方針との相違
- 休暇が取れない
- 残業が多い
- 結婚や出産
辞める理由について、1つずつ詳しく確認していきましょう。
人間関係
保育士を採用しても辞める背景にはさまざまな要因が隠れていますが、最大の原因は人間関係に問題があることです。職場における人間関係の問題として、上司との意見の食い違いや職場いじめ、派閥などが挙げられます。
保育士の仕事はチームで行うことが多い一方、保育観や仕事の進め方が異なることがきっかけで人間関係がギクシャクすることも少なくありません。
仕事の量
保育士は子どもたちの面倒を見るだけでなく、児童票や連絡帳の記入などの事務作業のほか、保護者との面談や相談・行事やイベントの企画や運営・片付けなど、多岐にわたる業務をこなさなければいけません。仕事の量が多いことがきっかけで、退職する保育士もいます。
通常業務以外で掃除や備品整理なども任されることがあるため、仕事の量が膨大になるケースも多いといえます。
給与の低さ

保育士の平均月給(所定内給与額)は 26.4万円で、全産業平均 31.8万円を約5.4万円 下回っています。経験年数が上がっても伸び幅は小さく、昇給や賞与が乏しい施設も少なくないため、給与面の不満が離職要因だと考えられます。
生活基盤が安定しないままでは、結婚・子育てとの両立も難しいです。自治体の処遇改善補助を確実に賃上げへ反映し、キャリアアップに応じた手当を明確に示すことが、離職率低減の鍵となるでしょう。
参考:e-Stat:「賃金構造統計調査(所定内給与)」
厚生労働省:「令和5年賃金構造基本統計調査」
労働時間
保育士は一般的に早番・中番・遅番などのシフト制で仕事をしていますが、人手不足のため早出や残業が必要になる場合も少なくありません。労働時間が長いことがきっかけで、退職する保育士もいます。
また、業務時間内に終わらなかった事務作業や制作準備を自宅に持ち帰り、勤務後に自ら残業している方もいるでしょう。残業や早出・持ち帰り仕事によって労働時間が長いと、保育士は負担の少ない保育園に転職する傾向にあります。
方針との相違
保育園には保育方針や特色がありますが、保育観が合わないことが転職のきっかけとなる人もいます。また、園長や同僚とのやり方や考え方が異なることも、退職する理由の1つにもなり得ます。
相違による退職を防ぐためには、求人を出した時点で方針を明確にしておく必要があるでしょう。
休暇が取れない
保育士が退職する理由として、休暇が取りづらいことも挙げられます。人員に余裕がある保育園でなければ、体調不良で休みを取ることが難しくなっています。
また、有休や休みの希望を提出しても人員配置の関係で許可できないケースもあり、休暇が取りにくい園では保育士が退職を検討する傾向にあります。
結婚や出産
保育士の仕事は体力を要することが多く、勤務時間も長いことから、妊娠や出産を機に退職するケースも多く見受けられます。
保育園でも産休・育休制度は利用できますが、産休明けや育休明けに「以前と同じように働くのが難しい」「復帰後の居場所がない」と感じて退職をする人もいます。
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/
保育士の離職率が高い理由には保育所以外での働き口の増加も関係している

近年は企業内保育所や児童発達支援、ベビーシッター・家事代行アプリ、学童クラブなど保育所以外で保育士資格を活かせるフィールドが急増しています。
企業主導型保育所だけでも令和3年時点で7,900施設超と平成20年比で2倍以上に拡大しており、土日休みや行事負担が少ない環境を求めて転職するケースが多いと考えられます。保育士の離職率が下がらない背景には、高い求人倍率と相まって「別の現場へ移る」という選択肢が増えているのが要因でしょう。
参照元:厚生労働省「令和3年 地域児童福祉事業等調査結果の概要」
厚生労働省「事業内保育施設の状況」
保育士が就職・転職する際にチェックしている項目

施設側の採用担当からすると、保育士が就職・転職する際に何をチェックしているのか気になる方も多いと思います。ここでは、保育士が施設選びで見ているポイントについて説明します。保育士が施設選びで重視するのは、主に以下の3つが挙げられます。
- 職場の環境
- 職員数
- 昇給や福利厚生
保育士は、具体的に何をチェックしているのか、それぞれ順に紹介します。
職場の環境
保育士は、クラス固定かフリー保育か、園庭や休憩スペースの有無、ICT導入度など「働きやすさ」を左右する制度面を重視しています。見学時に子どもと職員の表情を観察し、雰囲気や保育観が自分に合っているかを確かめる保育士が多いです。
職員数
特に転職を希望している保育師は、「児童数に対する職員の配置は適切かどうか」や「パートや派遣を含めて急な欠勤をカバーできる体制か」などの職員数もチェックしています。
職員数を確認している理由は、人員の余裕が働きやすさと強く関係するからです。「1年目に担任と行事担当を兼務させられた」など負荷のかかる業務を経験した方は、施設内における人員の状態を厳しくチェックします。
昇給や福利厚生

月給だけでなく、処遇改善手当の配分、宿舎借り上げ制度、独自休暇なども保育士はチェックしています。併せて、研修費補助などのポート制度があると評価が高いです。また、具体的にキャリアアップがイメージできる施設ほど応募数が伸びる可能があるでしょう。
離職率の低い保育園の特徴
離職率の高い保育園の最大の特徴は、保育士の人員不足や給与水準と有給取得率が低いことです。ここで紹介する離職率の高い保育園の特徴は、以下の2点です。
- 人員配置が多め
- 給与が安定している
それぞれ順に紹介します。
人員配置が多め
厚生労働省が策定している保育士の職員配置基準は最低基準ラインであり、ギリギリの人数配置は保育士の負担が大きくなります。保育士の離職理由である「仕事の量」「労働時間」「休暇が取れない」は、人員不足が関係しているといえるでしょう。
保育士は子どもたちの育成・保護に多大な労力が求められる仕事であることから、適切な給与や休暇制度の整備が重要です。しかし、運営費が限られていること、保育が集まりにくいことがきっかけで待遇を改善するのが難しい保育園が多いのが現状です。
給与が安定している
基本給に加えて、「自治体処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」や「宿舎借り上げ制度手当」などの手当てが支給され、「勤続3年ごとに1万円昇給+役職手当5千〜2万円」など、キャリアアップがイメージできる制度を公開している施設は離職率が低い傾向にあります。
さらに、賞与年3.0〜4.0カ月、家族・住宅手当、資格取得補助まで整備されていると定着率が高まるでしょう。ライフイベント期でも収入が大きく落ち込まず、職員は将来のキャリアアップをイメージしやすくなります。給与明細の内訳をわかりやすく公開することも、職員からの信頼にもつながり、離職防止に役立っています。
保育士の離職率を抑えるための離職防止策
最後に、保育士の離職率を抑えるための対策を以下の4つ紹介します。
- 働きやすい環境を作り上げる
- 独自に昇給制度を制定する
- 雇用形態を多様化する
- ICTシステムを導入する
それぞれ詳しくみていきましょう。
働きやすい環境を作り上げる
休憩専用室の整備やメンター制度など、職員が安心して勤務できる環境や制度を整えると心理的安全性が向上し、早期離職が減少するでしょう。
さらに、フレックス制や希望休優先、個人面接やストレスチェックなどの機会を充実させることで、職員が不安を溜め込まずに働き続けられる環境が整えられるように心がけてみてください。
独自に昇給制度を制定する
処遇改善Ⅰ・Ⅱを役職手当へ上乗せし、役職の段階的に応じて昇給する仕組みを整えましょう。公開評価シートや面談フィードバックで給与決定プロセスを透明化し、能力に応じたベースアップ加算や資格手当を充実させるのが重要です。
加えて、研修受講費補助も連動させると、キャリアビジョンが描きやすくなり離職抑止力が高まります。さらに、業務に連動した賞与モデルを導入すれば、動機付けが強化されるのでおすすめです。
雇用形態を多様化する
保育士の長時間労働に対して負担を軽減するために、雇用形態を多様化させて保育士を確保する方法が有効です。
パートタイムやアルバイトの保育士は、一人ひとり希望勤務時間が異なるため、さまざまな時間帯で確保できれば常勤保育士の残業時間を減らせきるでしょう。また、正社員を雇用するより人件費が低くなるという利点もあります。
雇用形態を多様化する際は、保育資格を保有していながらも保育施設で働いていない「潜在保育士」を採用するのがおすすめです。潜在保育士について知りたい方は、下記の記事もご覧ください。
ICTシステムを導入する
保育士の業務量の問題に対処する方法として、ICTシステムの使用もおすすめです。ICTを駆使することで欠席連絡管理のほか、おたよりの送信・連絡帳の記入・お便り作成などを電子機器で完結できるため、保育士の負担を大幅に軽減できます。
また、テンプレート文やデザインが用意されているサービスもあるため、文章作成やデザインに自信がない保育士でも効率的に書類を作成できるようになるでしょう。
ICTについて詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。
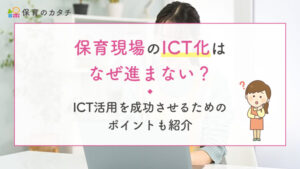
まとめ
この記事では、保育士の離職率について詳しく説明しました。保育士が辞める理由として人間関係のほか、仕事の負担・待遇面の不安など多岐に渡るため、施設側は多方面から改善を図る必要があります。労働環境を改善し、保育士の負担を軽減することが重要です。
保育士の負担を軽減する方法として、待遇面の改善とあわせて雇用形態の多様化とICT導入をするのもおすすめです。雇用形態を多様化する場合には、潜在保育士を採用すると即戦力のある人材を確保できるでしょう。
保育士の採用をするなら保育のカタチがおすすめ
引用元:保育のカタチ
保育士の採用をするなら保育のカタチがおすすめです。
保育のカタチは日本で唯一、幼保業界の「人」に関する問題解決に特化した専門家集団です。採用から社員教育、それらの仕組み化まで幅広く取り組んでおり、人手不足の保育業界の中で、幼保施設にとって最善のパートナーが見つかるようなお手伝いをしています。
採用がうまくいかず悩んでいる方はぜひ一度保育のカタチにご相談ください。
| 住所 | 〒550-0004大阪府大阪市西区靱本町1-7-22 SKKビル201 |
| 許可番号 | 厚生労働大臣許可番号有料職業紹介事業:27-ユ-303764労働者派遣事業:派27-304996 |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員、パート |
| 求人施設 | 保育園、幼稚園、認定こども園、病児保育、事業内保育、学童保育、託児所など |
| 対応エリア | 全国 |
| 連絡手段 | 電話番号:06-6210-5326 |
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/