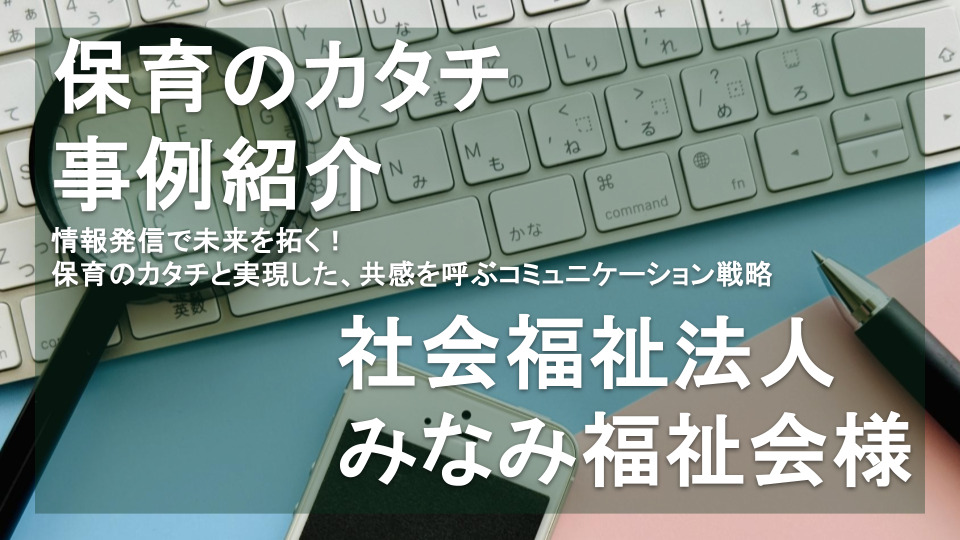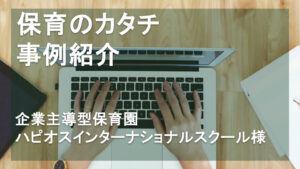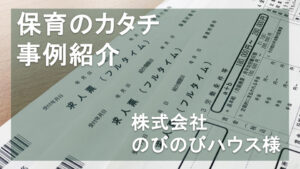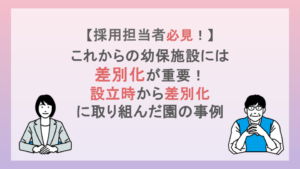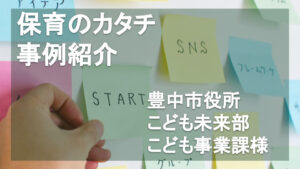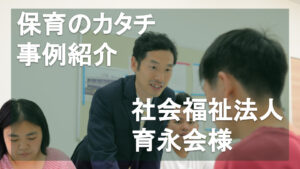幼保施設の「人」に関する問題を解決する「保育のカタチ」がお届けする本記事では、社会福祉法人みなみ福祉会の広報ご担当 宮武様、そして法人運営に深く関わる荒井様にお話を伺いました。
前回は採用の内製化についてお話を伺っております。採用の分野にご興味のある方は、以下の記事も参考にしてみてください。
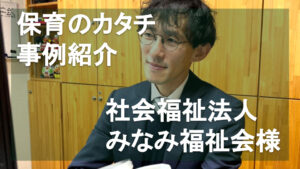
情報発信の強化と求人の内製化を目指し、「保育のカタチ」との取り組みの背景、具体的な施策、そして得られた成果とはどのようなものだったのでしょうか。本インタビューを通じて、情報発信に課題を抱える多くの保育施設の皆様にとって、新たな一歩を踏み出すためのヒントとなれば幸いです。
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/
1分で読める事例のポイント
Before
- 情報発信の具体的なノウハウが不足していた
- 定期的な情報発信が難しく、ネタ探しに苦労していた
- 採用のための情報発信が不足しているという課題感があった
- 「とりあえず何をしているか」を伝えるだけの発信が中心だった
- LINEが問い合わせ窓口としてほとんど機能していなかった
After
- 公式LINE登録者数が118名と約2倍(100名以上の登録者を持つLINE公式アカウントは全体の2.4%)に増加し、問い合わせ窓口として機能し始めた
- ホームページのアクセス数が約1.5倍に増加した
- 新卒者から「Instagramを見ていました」という声が聞かれるようになった
- 職員自身も法人全体を客観的に見直す機会となり、意識が向上した
- 現場の先生から自主的な活動報告が来るようになり、広報担当との信頼関係が構築された
導入してよかったところ
- 情報発信の方向性や記事構成についてプロの視点から具体的なアドバイスをもらえた
- 「誰に向けて情報発信するのか」という重要な視点を得られた
- 忙しい中でも法人の理念と活動を結びつけて発信することの大切さを再認識できた
- ブログ活用や保育学生の動向把握で、ネタ探しが以前より楽になった
- 外部への広報効果だけでなく、職員の意識改革や法人の強み・課題の共有に繋がった
みなみ福祉会 宮武様、荒井様に聞く


広報担当としての第一歩と、情報発信強化の切実な背景
保育のカタチ運営: 本日はお忙しい中ありがとうございます!まず、宮武様が今どのようなお仕事をされていて、みなみ福祉会様にはいつ頃からいらっしゃるのか教えていただけますか?
宮武様: みなみ福祉会で広報を担当しています、宮武です。2024年の4月に入職したので、もう1年と少し経ちましたね。入った時から広報担当として、主にホームページやInstagram、LINEなどを通じて、法人の魅力を発信するお仕事をしています。
保育のカタチ運営: 入職当初から広報をご担当されているんですね!荒井様にお伺いしたいのですが、宮武様を広報担当として採用された背景には、どのような思いがあったのでしょうか?
荒井様: はい、以前から情報発信の大切さは感じていたんです。特にSNSなどを活用した情報発信を強化したい、そして求人も自分たちでやっていきたいという思いがありました。ただ、なかなか手が回らない状況でして…。そこで専門の広報担当者が必要だと感じ、募集をかけたという経緯です。
保育のカタチ運営: なるほど、情報発信の強化と採用の内製化が背景にあったんですね。宮武様は、どのような経緯でこちらの業務を担当されるようになったのですか?また、発信する上で意識されていることはありますか?
宮武様: 実は私、元々は保育施設を利用する保護者の立場だったんです。なので、保育園の中のことは最初は全く知らなくて。まずは保育所ってどんなところなんだろう?というのを理解するところから始めました。その経験があるので、保護者の方がどんな情報があったら安心できるかなとか、どんな言葉だったら心に届くかな、という視点はいつも意識して発信しています。
保育のカタチ運営: 保護者目線、とても大切ですよね。宮武様から見て、みなみ福祉会様の「ここがいいな!」と思うところや、施設の特徴について教えていただけますか?
宮武様: はい、みなみ福祉会には4つの保育園があって、それぞれの地域性を活かした保育を行っているのが特徴です。特に、子どもたちの主体性を育む保育や、異年齢の子どもたちが関わり合う保育、そして家庭的な温かさを大切にしています。
保育のカタチ運営: 地域性を活かした保育、素敵ですね。荒井様、名古屋の保育園ならではの地域的な特性などはありますか?全国の読者の方にも伝わるような。
荒井様: 名古屋の保育園は、昔から「名保連(名古屋市民間保育園連盟)」の活動が活発で、保育園同士の横の繋がりが強いという特徴がありますね。求職者の方も地元志向の方が比較的多い印象です。ただ、私たちの法人が位置する南区は、名古屋の中心部からは少し離れているので、求人という面では少し工夫が必要なエリアでもあります。
「保育のカタチ」との出会いが生んだ、情報発信の質的転換

保育のカタチ運営: 宮武様は、法人として情報発信を強化したいという中で、当初どのような点に難しさを感じていらっしゃいましたか?
宮武様: そうですね、法人として「もっと情報を発信していきたい!」という気持ちはあったんですが、具体的に何から手をつければ良いのか分からなくて…。定期的に発信し続けるのも難しいな、と感じていました。
保育のカタチ運営: 荒井様も同じような課題感をお持ちでしたか?
荒井様: はい、宮武が言う通りです。特に採用のための情報発信が足りていないという認識はありましたね。
保育のカタチ運営: なるほど。宮武様が最初に取り組まれた情報発信は何だったんですか?
宮武様: 一番最初はInstagramの採用アカウントでした。保育士さんの普段見えない裏側を発信してみよう、と。
保育のカタチ運営: 「保育のカタチ」にご相談いただく前は、どのように情報発信に取り組まれていたのでしょうか。手探りだった部分もあったのでしょうか?
宮武様: はい、正直なところ、知識がない状態からのスタートでした。とりあえず「今こんなことしていますよ」という活動内容を伝えることが中心でしたね。以前に他の担当者がInstagramを運用していたのを見たり、前任者の方と配信ペースを相談したりはしていましたが、やっぱり内容を準備するのは大変でした。
保育のカタチ運営: ネタ探しにもご苦労されたんですね。
宮武様: そうなんです。初めは何をあげたらいいんだろう…というのは常にありました。
保育のカタチ運営: その後、「保育のカタチ」からはどのようなサポートがありましたか?また、それによってどのような変化を感じられましたか?
宮武様: 「保育のカタチ」さんには、情報発信の方向性や記事の構成など、本当にプロの視点からたくさんのアドバイスをいただきました。これがすごく心強かったです!具体的には、SNS広告やリスティング広告の運用、ブログ記事の添削、ホームページのリニューアルのサポート、それからLINE活用のサポートなど、本当に幅広くお手伝いいただいています。
保育のカタチ運営: 幅広いサポートがあったんですね!特に印象的だったアドバイスはありますか?
宮武様: やはり、「誰に向けて情報発信するのか」という視点を持つことの大切さに気づかされたことです。ホームページについても、写真の選び方や文章の書き方、例えば「結論を先に書くと伝わりやすいですよ」とか、「一番伝えたいことを最初に持ってきましょう」といった具体的な構成のアドバイスをいただいて、実践するようになりました。
保育のカタチ運営: 忙しい中でも継続的に情報発信を行うための工夫として、何かアドバイスはありましたか?
宮武様: はい、「保育のカタチ」の山下さんからは、忙しい中でも、法人の理念と活動報告を結びつけて発信することが大切だと教えていただきました。日々の業務に追われていると、つい当たり前になって忘れがちなんですけど、改めてその重要性を感じましたね。
具体的な取り組みと、見えてきた確かな成果 ~ホームページ・Instagram、そしてLINEの変化~

保育のカタチ運営: 実際にこれらの取り組みを進めてみて、どのような感想をお持ちですか?ネタ探しも以前よりスムーズになりましたか?
宮武様: はい、最初はネタ探しに本当に苦労しましたが、ブログを活用したり、保育学生さんが今どんなことに興味を持っているのかを意識したりするようになってからは、以前ほど「大変だ!」と感じずに情報発信を続けられています。スケジュール管理も、最低限の更新頻度は守ろう、ということを大切にしながら取り組んでいます。
保育のカタチ運営: 素晴らしいですね!具体的な成果として、ホームページやInstagram、そしてLINEの活用にも変化はありましたか?
宮武様: はい、ホームページのアクセス数は1年前と比較して約1.5倍に増えましたし、新卒の方から「Instagramを見ていました」という声もいただくようになりました。LINEについても、以前は登録者数が伸び悩んでいましたが、「保育のカタチ」さんにサポートしていただき、挨拶メッセージや新卒インタビューをカードタイプのメッセージで配信したり、ブログ記事を紹介したりするようになってから、登録者数が2024年4月の58人から現在は118人と約2倍に増え、問い合わせ窓口としても機能するようになってきました。
保育のカタチ運営: LINEの登録者数が倍増とはすごいですね!余談ですが、LINEで100人以上の登録者を超えるアカウントは全体の2.4%だそうです。荒井様から見て、これらの変化はいかがですか?
荒井様: そうですね、LINEは昨年ほとんど窓口として機能していませんでしたが、今年はアクティブなアカウントとして活用できています。ホームページも、以前は園を元々知っている方の問い合わせが多かったのですが、最近はインターネットで調べて初めて園を知ったと思われる方の問い合わせや入園が増えている印象です。
情報発信がもたらした、法人内外への好影響と今後の展望
保育のカタチ運営: 情報発信に取り組んでみて、一番良かったと感じることは何でしょうか?
宮武様: ブログやSNSで発信を続けることで、外部への広報効果はもちろんですが、実は職員自身も法人全体を客観的に見直す良い機会になったと感じています。法人の取り組みを言葉にして見える化することで、私たちの強みや課題がみんなで共有できて、良い方向に変わるきっかけになっているんじゃないかな、と。
保育のカタチ運営: 職員の方々にも変化があったんですね!荒井様もそのあたりは感じられますか?
荒井様: ええ、職員も発信内容を見てくれていますし、実際に反響もありますね。実は、取り組みを始めた当初は、行事の報告をお願いしてもなかなか内容が薄かったり、写真が集まらなかったりしたんです。でも、根気強くお願いして、出来上がった記事を共有していくうちに、現場の先生たちの意識が明らかに向上しました。
保育のカタチ運営: それは素晴らしい変化ですね!
荒井様: はい。こちらから依頼しなかった活動についても自主的に報告が来るようになったり、「保育の様子を伝えれば宮武さんが記事にしてくれる」という信頼関係ができてきたのかな、と感じています。
保育のカタチ運営: 現場の先生方との信頼関係、とても素敵です。今後の情報発信について、何か展望はありますか?
宮武様: これからも、見てくださる方にとって有益な情報を届けられるように、そして法人の魅力をより深く伝えられるように、色々な工夫を重ねていきたいと思っています。
同じ課題を抱える全国の保育施設の仲間たちへのエール
保育のカタチ運営: 最後に、情報発信に課題を感じている全国の保育施設の運営者や担当者の皆様へ、宮武様のご経験を踏まえたメッセージをお願いいたします。
宮武様: 日々の業務に追われて、なかなか情報発信にまで手が回らない…ということは、本当によくあることだと思います。でも、発信の仕方や手順をサポートしてくれる存在がいれば、想像以上に世界が広がるはずです。小さな発信でも、きちんと見てくれる人は必ずいますし、それがしっかり成果にも繋がっていくので、まずは専門の方に相談してみるのが一番良いのではないかな、と思います。
保育のカタチ運営: 宮武様、荒井様、本日は本当に貴重で温かいお話をありがとうございました!
まとめ
今回、社会福祉法人みなみ福祉会の宮武様、荒井様にお話を伺い、情報発信の強化がいかにして法人の内外にポジティブな変化をもたらすかを具体的に知ることができました。
「保育のカタチ」との連携を通じて、ターゲットを意識した情報発信戦略を構築し、LINE、ホームページ、Instagramといった各チャネルの特性を活かした施策を実行。その結果、問い合わせ数の増加や採用応募者からの反響といった目に見える成果だけでなく、職員の意識改革や法人全体の魅力の再発見といった、組織文化への好影響も生まれていることが明らかになりました。
特に、「誰に何を伝えるか」という原点に立ち返り、法人の理念や日々の保育実践と情報発信を結びつけることの重要性は、多くの保育施設にとって大きなヒントとなるでしょう。
本記事が、情報発信の課題を抱える皆様にとって、新たな可能性を見出す一助となれば幸いです。
「保育のカタチ」が、貴園の「人」に関する課題解決をサポートします
「保育のカタチ」は、幼保施設の「人」に関するあらゆる課題解決をサポートする専門家集団です。
採用戦略の見直し、人材育成、組織風土の改善、そして今回の事例のような情報発信戦略の立案・実行支援など、貴園の状況に合わせた最適なソリューションをご提案いたします。
「情報発信を強化したいが、何から手をつければ良いかわからない」
「SNSやホームページをうまく活用できていない」
「採用に繋がる情報発信のノウハウを知りたい」
このようにお考えの保育施設経営者様、園長先生、広報・人事ご担当者様は、ぜひお気軽に「保育のカタチ」までご相談ください。専門のコンサルタントが、貴園の課題に真摯に寄り添い、具体的な解決策を共に見つけ出してまいります。
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/