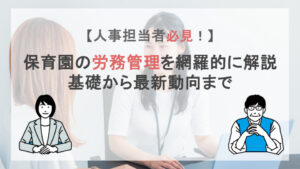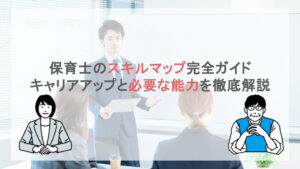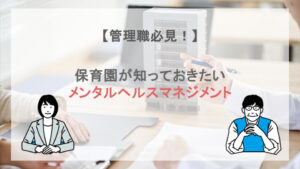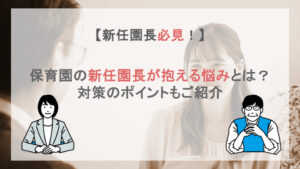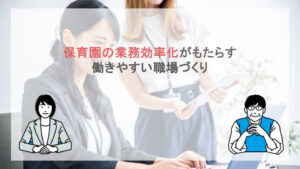近年、保育士の離職率が社会問題として注目を集めています。保育の質を高め、安心して子どもを預けられる環境を整えるためには、保育士が長く働きやすい職場づくりが欠かせません。
本記事では、保育士の離職率の現状から具体的な離職要因、そして離職率を改善するための実践的ステップをわかりやすく解説します。今後のキャリア形成や保育環境の向上に役立てていただければ幸いです。
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/
保育士の離職率の現状と業界動向

まずは、保育士の離職率がどのような状況にあるのか、公立保育園と私立保育園の比較や経験年数による違いを探ります。
厚生労働省の調査では、保育士全体の離職率は約9%台で推移しているとされています。日本全体の平均離職率が15%前後であることを考えると、数字だけ見れば低めですが、毎年5万人以上が辞めている点を考えると決して軽視できない状況です。離職が多い背景には、給与水準や職場環境など多面的な要因が複雑に絡み合っていることが大きく、園によっては短期間で人が入れ替わるケースも珍しくありません。
公立と私立で異なる離職率の比較
公立保育園は地方公務員としての安定した身分が得られることが多いため、給与や待遇面が比較的充実しており離職率も5%前後と低めです。一方、私立保育園は事業者ごとに処遇が大きく異なり、中には給料や福利厚生が十分に整っていない園もあります。その結果、離職率が公立より高くなる傾向が見られ、10%をゆうに超えるケースもしばしば報告されています。実際に園を見学する際には、給与テーブルや支援制度などの具体的な情報を確認することが重要です。
経験年数別に見る若手・ベテラン保育士の離職率
経験年数の浅い保育士が離職しやすい背景には、慣れない業務に追われるうちに支援体制が不十分であることが大きく関係しています。先輩保育士や指導担当のフォローが得られないと、仕事の進め方や子どもとの関わり方に不安を抱えやすく、そのまま退職につながることも少なくありません。一方、ベテラン保育士の場合は昇給の頭打ちやキャリアアップの道が狭いなど、将来設計に不透明感があることでモチベーションを失い、結果的に離職を選ぶケースが多いようです。
高い離職率を招く保育園・保育所の特徴
離職率の高い園には共通点があります。ここでは、具体的な特徴を洗い出し、人材流出につながる原因を掘り下げていきます。
人員配置の問題や経営方針などにより、同じ業界でも園ごとの働きやすさが大きく異なります。離職が多い園はたいてい、業務負担の偏りやコミュニケーションの不足が深刻化しており、保育士が孤立しやすい環境になっていることが多いです。こうした課題を放置すると早期退職が相次ぎ、結果として園全体の保育品質に悪影響を及ぼす可能性が高まります。
慢性的な人手不足が招く悪循環
保育士の人手不足は慢性的な課題であり、特に都市部の私立園などでは顕著に見られます。人員が足りないため一人ひとりの業務負担が増え、十分な休憩や休日を確保できず心身の負担が蓄積しがちです。その結果、さらに離職する職員が増えるという悪循環へと陥り易くなり、残った保育士への負荷がさらに肥大化するという問題を招きます。
新人や若手保育士へのサポート体制不備
新人や若手保育士にとって、初めての職場はわからないことだらけです。適切な指導担当がついて研修を行う仕組みが整備されていない園では、新人保育士が早い段階で仕事の進め方に困り果ててしまうことも少なくありません。こうしたサポート不足は職場定着を妨げる大きな要因となり、冒頭で説明した若手離職率の高さにつながっていきます。
低賃金構造と昇給の限界
保育士の給与水準は全体的に他業種と比較して低めであり、一度就職しても長く働き続けるうちに給与面での将来設計が立てにくい現実があります。年次が上がっても昇給に上限がある職場が多いと、ベテランであってもモチベーション維持が難しくなるケースは少なくありません。低賃金の構造が改善されないままでは、保育士が経済的な理由から離職を選択する状況はなかなか変わらないでしょう。
保育士が離職する主な原因とよくある退職理由

保育士が退職を決断する理由は多岐にわたります。ここでは、代表的な離職の原因を紹介します。
保育士という仕事は子どもたちの成長に寄り添うやりがいがある一方で、現場では多用な業務や人間関係の調整が求められます。賃金や待遇の問題だけでなく、精神的・肉体的な負担に耐えられず退職に至るケースも目立ちます。現場での悩みを早めに共有・解消できる環境があれば、離職を減らすことは十分可能です。
人間関係と保護者対応のプレッシャー
保育士同士の連携がスムーズでないと、仕事の割り振りや情報共有がうまくいかず、トラブルの原因になります。さらに、保護者からの要望や苦情が多い場合は、プロとして柔軟に対応する必要があるためストレスが大きくのしかかるでしょう。こうした状況が続くと、保育に対するモチベーションを維持することが難しくなり、離職を考えるきっかけになることが多いです。
長時間労働・休憩時間不足の問題
保育士の仕事は園での保育時間だけでは終わらず、行事準備や書類作成など業務外での作業が発生しがちです。子どもたちの突発的な体調不良やイベント関連の打ち合わせなどが重なると、休憩時間なく長時間労働となるケースも少なくありません。こうした負担が慢性化すれば体力的にも精神的にも厳しく、退職の大きな要因になるのは当然といえます。
事務業務や書類作成の負担
保育日誌や保護者への連絡帳など、保育に付随する書類作成業務は意外と多いものです。これらの事務業務が増えすぎると、子どもと向き合う時間が減り、本来目指すべき保育の質に影響を及ぼしかねません。業務の優先順位や効率化を検討せずに放置すると、保育士のやりがい喪失につながり、離職理由のひとつとして表面化してきます。
賃金や福利厚生への不満
給与水準が低いままでは、生活の安定を求めて他業種へ転職を考える人が増えてしまいます。特に住宅手当や家族手当などが手薄な園では、子育てや親の介護などと両立するのが難しくなることも少なくありません。十分な福利厚生がない職場で働き続けることは、将来的な不安を増幅させる要因となり、離職を決断する大きな後押しとなります。
キャリアアップや研修機会の不足
保育士としてのスキルを高めたいと思っても、園側で研修や学びの機会を提供していない場合、成長意欲を活かすことが難しくなります。役職登用に限界がある園では、ベテランになっても評価や待遇が変わらないため、長期的に働く意義を見いだせないケースも多いです。こうしたキャリア面の不満は、保育士としてのやりがいを損ない、離職につながる大きな要素といえます。
離職率が高い保育園を改善するための施策

離職率を下げるには、組織全体で取り組む具体的な方策が欠かせません。ここでは実践につながる改善案を示します。
離職を防ぐためには保育士の声を正面から受け止め、課題を一つひとつ解消していくことが重要です。シフトや給与、環境改善など、できるところから迅速に手を打つことで意欲的に働ける職場づくりを進められます。特に経営者や管理職が現場の課題を理解し、継続的にフォローアップする姿勢を示すことが欠かせません。
面談やアンケートの活用で現場の声を収集
定期的に保育士と個別面談を行い、悩みや要望を聞き取る体制を整えることは有効な施策です。匿名のアンケートを実施すれば、言いにくいことも含めて本音を把握できる可能性が高まります。こうした情報を分析し、スピーディに改善策を実行することで、保育士が安心して働ける環境づくりにつながります。
シフト管理・業務分担の見直し
保育士に過度な負担が集中しないよう、シフト編成を柔軟に考慮することがポイントです。園全体で業務を分担し、慣れない業務や負荷の高い仕事が一部の保育士に偏らないように調整することも大切でしょう。特に繁忙期や行事前などは事前に準備期間を設け、計画的に残業を減らす仕組みをモデル化しておくと効果的です。
給与・処遇改善と福利厚生の強化
安定した処遇を実現するためには、業界平均や地域水準を踏まえた給与見直しが不可欠です。加えて、住宅手当や資格手当などを充実させ、保育士が安心して長期間働ける土台を整備することも重要になります。経営的に難しい場合でも少しずつ改善を進めることで、離職率の低減につながりやすくなるでしょう。
研修や資格取得サポート体制の充実
保育士のキャリアアップを支援するために、園内研修や外部研修の積極的な導入を検討すると効果的です。特に専門分野の研修や資格取得をバックアップしてもらえる仕組みがあれば、職員のモチベーション向上にもつながります。結果的に各自の専門性が高まり、保育の質の向上と離職率の低減を同時に実現できる可能性が広がるでしょう。
ICTシステムを活用した業務効率化
書類作成や情報共有など、保育士が苦手としやすい事務作業をICTで効率化する取り組みが増えています。クラウド上で保護者との連絡を行ったり、アプリでシフト管理を自動化したりすることで、職員が保育に専念できる時間を増やすことが可能です。保育の質を保ちつつ事務作業の負担を軽減できれば、離職意向を持つ保育士を大きく減らす一助となるでしょう。
まとめ
長く働き続けられる保育の現場づくりには、働きやすい環境と適切なキャリアサポートが必要不可欠です。
保育士が安心して働けるようにするためには、給与や福利厚生といった金銭面だけでなく、サポート体制や研修制度を整えるなど、総合的な環境改善が求められます。人手不足を解消し、新人からベテランまでが活躍できるキャリアパスを提示することで、離職率を大幅に抑制することができるでしょう。子どもたちの健やかな成長を支えるためにも、保育士がやりがいを持ちながら長期的に働ける体制づくりが、今後ますます重要になります。
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/