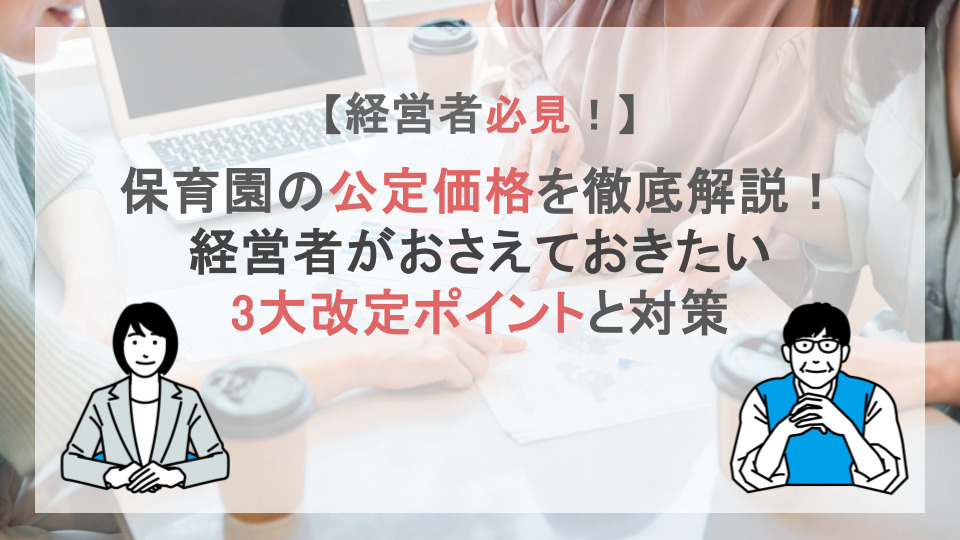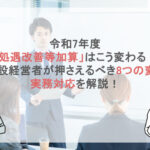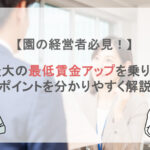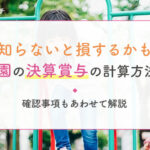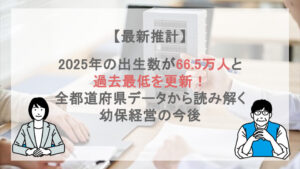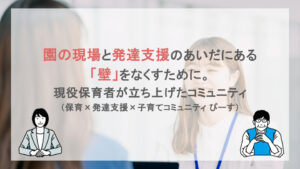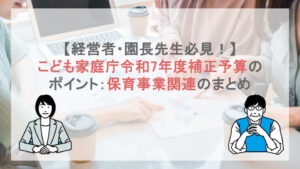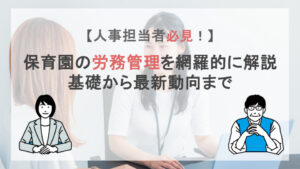保育園経営者の皆様にとって、施設の収入の根幹をなす「公定価格」。この公定価格が、令和7年度に近年まれに見る大きな改定を迎えます。職員の処遇から施設の収支構造、さらには求められる運営の質まで、その影響は多岐にわたります。
本記事では、この重要な令和7年度公定価格改定の全貌を徹底的に解説します。特に、「処遇改善等加算の一本化」「定員区分の細分化」「1歳児配置改善加算の新設」という3つの大きな変更点に焦点を当て、具体的に何がどう変わるのか、そして経営者は何をすべきなのかを、具体的なシミュレーションや対策とともに分かりやすく解説していきます。
\自園と相性のよい人材が長く働いてくれる、保育のカタチの採用支援/
3分で分かる!令和7年度 公定価格の3つの重要改定ポイント
まずは今回の改定の核心となる3つのポイントを簡潔にご紹介します。
- 処遇改善等加算の一本化:事務負担が軽減され、給与配分の柔軟性が向上
これまで複雑だった「処遇改善等加算I・II・III」の3本立ての仕組みが、令和7年度から一つの加算に統合されます。この新しい加算は、「①基礎分」「②賃金改善分」「③質の向上分」という3つの要素で構成されます。これにより、申請や報告に関する事務手続きが大幅に簡素化されるとともに、これまで厳格だった配分ルール(例:月額4万円の改善対象者を必ず1名以上設けるルール)が緩和され、各園の実情に応じた、より戦略的で柔軟な給与体系の設計が可能になります。 - 定員区分の細分化:小規模園の経営基盤が安定化
公定価格の基本単価を決定する「利用定員区分」が、特に小規模な施設にとって有利な形に変更されます。具体的には、利用定員60人以下の施設において、従来の10人刻みの区分から5人刻みの区分へと細分化されます。例えば、これまで「31人~40人」という一つの区分だったものが、「31人~35人」「36人~40人」の二つに分かれます。これにより、定員規模に応じた、より公平で実態に即した単価が適用されることになり、特に小規模園の収入安定化に繋がることが期待されます。 - 「1歳児配置改善加算」の新設:質の高い保育を行う園が報われる仕組みへ
保育の質向上を目的とした新たな加算として、「1歳児配置改善加算」が創設されます。これは、1歳児の職員配置基準を現行の「6対1」から手厚い「5対1」へと改善する施設を対象としたものです。ただし、この加算を取得するための要件は非常に厳格です。職員の平均経験年数が10年以上であることや、ICTを積極的に活用していることなど、職員の定着率や業務の効率化といった、園全体の運営レベルの高さが問われる仕組みとなっています。これは、単に人員を増やすだけでなく、総合的に質の高い運営を行っている施設を評価し、支援するという国の明確な方針の表れと言えるでしょう。
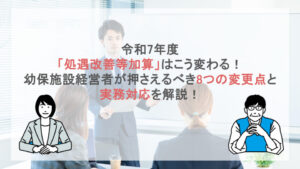
経営の根幹を理解する – そもそも「公定価格」とは?

令和7年度の改定内容を深く理解するためには、まず「公定価格」そのものの仕組みを正確に把握しておくことが不可欠です。ここでは、公定価格の基本について改めて確認します。
公定価格の定義と役割
公定価格とは、子ども・子育て支援新制度のもとで、認可保育所や認定こども園などの施設が教育・保育を提供するために必要となる費用を、国が基準を定めて算出した価格のことです。これは子ども一人当たりの単価として設定されており、施設の運営費の大部分を占める重要な財源となります。
この公定価格を基に算出された費用は、市町村から施設に対して支払われます。私立の認可保育所の場合は「委託費」として、認定こども園や施設型給付を受ける幼稚園の場合は「施設型給付費」として支給されます。重要なのは、この給付(委託費)は、施設を利用する子どもの居住地の市町村から支払われるという点です。つまり、公定価格は国が定めた基準でありながら、実際の支払いは市町村を通じて行われるという構造になっています。
公定価格の構成要素:基本分単価と加算項目
公定価格は、大きく分けて「基本分単価」と「加算項目」の二つの要素で構成されています。施設の総収入を正確に把握し、経営戦略を立てるためには、この二つの要素を正しく理解することが極めて重要です。
基本分単価
基本分単価は、その名の通り公定価格の基本となる部分であり、日常的な保育に必要な人件費や事業費、管理費などを賄うための費用です。施設の収入の大部分を占める、まさに経営の土台となる部分です。この単価は、様々な要素によって変動します。
- 地域区分: 全国の市町村が、物価や人件費水準に応じて8つの区分に分けられています。都市部などコストが高い地域ほど単価が高く設定されており、地域間の経済格差を是正する役割を担っています。
- 利用定員: 施設の利用定員の規模によって単価が異なります。一般的に、定員規模が小さいほど固定費の割合が高くなるため、一人当たりの単価は高く設定される傾向にあります。
- 子どもの年齢: 保育に必要な職員配置やケアの内容が異なるため、0歳児、1・2歳児、3歳児、4歳以上児といった年齢区分ごとに異なる単価が設定されています。
- 認定区分・保育必要量: 保護者の就労状況などにより、「1号認定(教育標準時間)」「2号認定(保育標準時間・短時間)」「3号認定(保育標準時間・短時間)」に区分され、それぞれ単価が異なります。
加算項目
加算項目は、基本分単価に上乗せされる費用であり、各施設が提供する保育の質を向上させるための特別な取り組みや、延長保育、休日保育といった特別なニーズに対応する場合などに適用されます。どのような加算を取得できるかは、施設の職員配置や専門的な取り組み、設備の状況などによって大きく異なり、経営努力が収入に直結する部分と言えます。
主な加算項目には、以下のようなものがあります。
- 処遇改善等加算
- 3歳児配置改善加算
- 主任保育士専任加算
- 賃借料加算(施設が賃貸物件の場合)
- 療育支援加算
- 休日保育加算
- 栄養管理加算
この公定価格の構造は、単なる運営費の補填制度ではありません。国が保育業界にどのような方向性を求めているかを示す、政策的なメッセージが込められています。基本分単価で安定的な基盤を保障しつつ、加算項目を通じて「職員の処遇改善」や「保育の専門性向上」といった特定の目標達成を促すインセンティブ設計になっているのです。したがって、経営者としては、基本分単価を確実に確保するだけでなく、自園の強みや目標に合わせて戦略的に加算項目を取得していくことが、持続可能な経営を実現する上で不可欠となります。
【最重要】令和7年度公定価格の3大改定ポイントを徹底解剖

ここからは、本記事の核心である令和7年度の3大改定ポイントについて、一つひとつ詳細に掘り下げていきます。それぞれの変更が、施設の運営や財務に具体的にどのような影響を与えるのかを明らかにします。
改定ポイント①:処遇改善等加算の一本化 – 事務簡素化と配分の柔軟化
今回の改定で最も影響が大きいのが、職員の給与に直結する「処遇改善等加算」の抜本的な見直しです。
Before (令和6年度まで):複雑だった3つの加算制度
これまで、保育士等の処遇改善を目的とした加算は、「処遇改善等加算I」「処遇改善等加算II」「処遇改善等加算III」の3種類が存在していました。
- 加算Iは、職員の平均経験年数に応じた昇給(基礎分)と、キャリアパス要件を満たした上での賃金改善(賃金改善要件分)を支援するものでした。
- 加算IIは、副主任保育士や職務分野別リーダーといった中核的な役割を担う職員に対し、月額4万円または5千円の役職手当を支給するためのものでした。
- 加算IIIは、近年の賃上げ促進を目的として、月額9,000円程度のベースアップを支援するものでした。
これらの加算は、それぞれ目的や計算方法、申請・報告様式が異なり、制度の複雑さが経営者や事務担当者の大きな負担となっていました。
After (令和7年度から):目的別の3要素で構成される新制度へ
令和7年度からは、これら3つの加算が一つに「処遇改善等加算」として一本化されます。ただし、単に統合されるだけではなく、旧制度の目的を引き継ぐ形で、以下の3つの区分に再編されます。
- ①基礎分: 旧加算Iの基礎分に相当し、職員の平均経験年数の上昇に応じた昇給等に充てられます。
- ②賃金改善分: 旧加算Iの賃金改善要件分と旧加算IIIを統合したもので、職員の継続的な賃金引き上げ(ベースアップ)を目的とします。
- ③質の向上分: 旧加算IIに相当し、副主任保育士などのリーダー層の処遇改善を通じて、保育の質の向上を図ることを目的とします。
経営者が注目すべきルールの変更点
この一本化に伴い、運営上のルールも大きく変わります。
- 事務手続きの簡素化: これまで加算ごとに必要だった計画書や実績報告書が一本化されます。さらに、賃金改善計画書の提出は原則として廃止され、代わりに賃金改善を行う旨の「誓約書」を提出する方式となり、事務負担が大幅に軽減されます。
- 配分ルールの柔軟化: 最も大きな変更点の一つが、配分ルールの緩和です。特に旧加算IIで課されていた「月額4万円の改善を行う者を必ず1人以上確保する」という厳格な要件が撤廃されます。新制度では、「質の向上分」の配分において、施設の判断でより柔軟な配分が可能になります(ただし、一人当たりの改善額が4万円を超えることはできません)。
- ベースアップ要件の新設: 新たなルールとして、「賃金改善分」と「質の向上分」の合計額の2分の1以上を、基本給または毎月決まって支払われる手当の引き上げに充てることが義務付けられます。これは、賞与などの一時金だけでなく、月々の安定した収入増に繋げることを国が重視している表れです。
この一連の変更は、単なる事務作業の軽減を意味するものではありません。国がこれまで詳細なルールで縛ってきた給与配分の権限を、より多く現場の経営者に委ねるという、大きな方針転換を示唆しています。
これまでの「ルールに従って配分する」というコンプライアンス重視の姿勢から、「自園の理念や人材戦略に基づいて最適な給与体系を設計する」という、より高度な経営判断が求められるようになります。この柔軟性を活かせるかどうかで、職員の満足度や定着率、ひいては園の競争力に大きな差が生まれることになるでしょう。
表1:処遇改善等加算の新旧比較
| 項目 | ~令和6年度(旧制度) | 令和7年度~(新制度) |
| 構成 | 処遇改善等加算I、II、IIIの3つの独立した加算 | 「処遇改善等加算」に一本化。 内部で「①基礎分」「②賃金改善分」「③質の向上分」の3区分に整理。 |
| 申請・報告手続き | 各加算で個別の計画書・実績報告書が必要で、手続きが煩雑。 | 申請・報告様式が一本化される。 計画書は原則「誓約書」の提出に代替され、事務負担が大幅に軽減。 |
| 主な配分ルール | 加算II: 月額4万円の改善対象者を最低1名確保する必要があるなど、 rigidなルールが存在。 | 質の向上分: 4万円の最低確保要件が撤廃され、施設の実情に応じた柔軟な配分が可能に(上限4万円/人)。 |
| 賃金改善方法 | 各加算で改善方法の要件が異なる。 | 賃金改善分+質の向上分: 合計額の1/2以上を基本給または毎月決まって支払われる手当の改善に充てる必要あり。 |
| 主な目的 | 経験年数、リーダー育成、ベースアップなど、個別の目的に応じた加算が並立。 | 職員のキャリアパス全体を支える総合的な処遇改善を目指す。 |
改定ポイント②:定員区分の細分化 – 小規模園に追い風
次に、施設の基本収入に直接影響する定員区分の変更です。これは特に定員60人以下の施設にとって重要な改定となります。
Before (令和6年度まで):広い定員区分による不利益
従来の公定価格では、基本分単価を算定する際の定員区分は、比較的広い幅で設定されていました。例えば、「31人~40人」「41人~50人」といった10人刻みの区分が一般的でした。
この制度では、例えば定員35人の園と定員40人の園が、同じ「31人~40人」の区分に属するため、子ども一人当たりの基本分単価が全く同じでした。しかし、実際には定員が少ない方が一人当たりの固定費負担は重くなるため、定員区分の上限に近い園に比べて、下限に近い園は実質的に不利な状況に置かれていました。
After (令和7年度から):5人刻みへの細分化による適正化
令和7年度からは、利用定員が60人以下の施設を対象に、この定員区分が5人刻みに細分化されます。
例えば、従来の「31人~40人」区分は、「31人~35人」と「36人~40人」の2つの区分に分割されます。
これにより、定員35人の園は、より単価の高い「31人~35人」の区分に属することになり、これまでよりも実態に即した、より手厚い単価が適用されることになります。
この変更の背景には、少子化が進む中で、地域に根差した小規模保育施設の重要性が増しているという社会的な現実があります。従来の制度は、結果的にこうした小規模施設の経営を圧迫しかねない構造を持っていました。
今回の細分化は、その構造的な不利益を是正し、小規模施設の経営基盤を安定させることを目的とした、国の明確な政策的判断です。これは単なる単価表の修正ではなく、多様な保育ニーズに応える小規模施設の持続可能性を支えるための重要な一歩と言えるでしょう。
表2:定員区分変更による基本分単価への影響(シミュレーション)
※その他地域、保育標準時間認定の場合。令和6年度単価は実際の公表値 19、令和7年度単価は改定の趣旨を反映した想定値です。
| 利用定員区分 | 令和6年度 単価(3歳児) | 令和7年度 単価(3歳児) | 収入への影響(定員35人の園の場合) |
| 31~40人 | 63,410円 | – | 令和6年度はこの単価が適用 |
| 31~35人 | – | 68,250円(想定) | 令和7年度から、より高い単価が適用され、増収となる。 |
| 36~40人 | – | 63,410円(想定) | – |
改定ポイント③:新設「1歳児配置改善加算」- 質の高い園が報われる仕組み
令和7年度改定の目玉の一つが、保育の質向上に直接的に繋がる「1歳児配置改善加算」の新設です。
新設加算の概要と目的
この加算は、心身の発達が著しく、特に手厚い関わりが求められる1歳児クラスの職員配置を、現行の基準である「子ども6人に対して職員1人(6:1)」から、「子ども5人に対して職員1人(5:1)」以上に手厚くした場合に支給されるものです。保育士不足が叫ばれる中、基準を上回る手厚い配置を実現している施設を経済的に支援し、保育の質向上を全国的に推進することが大きな目的です。
取得の鍵となる厳格な4つの要件
注目すべきは、この加算の取得要件が極めて厳しい点です。単に1歳児の職員を一人増やせばよいという単純な話ではありません。以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
- 職員配置の実践: 実際に1歳児の職員配置を「5対1」以上に改善していること。
- 既存の処遇改善の完全実施: 令和6年度までの「処遇改善等加算I・II・III」のすべてを取得していること。
- 職員の高い定着率: 施設に勤務する常勤職員の平均経験年数が10年以上であること。
- ICTの積極的な活用: 業務の効率化のためにICTシステムを導入し、活用していること。具体的には、「登降園管理」機能に加えて、「保護者連絡」「計画・記録」「キャッシュレス決済」などのうち、もう1つ以上の機能を活用している必要があります。
これらの要件は、一見すると非常にハードルが高いと感じられるかもしれません。しかし、国は、この魅力的な大型加算をインセンティブとして、保育施設に総合的な経営改善を促しているのです。
要件を一つずつ見ていくと、それが分かります。「既存の処遇改善の完全実施」は職員の給与水準への配慮を、「平均経験年数10年以上」は働きやすい職場環境と職員の高い定着率を、「ICTの活用」は業務効率化と現代的な運営体制を、それぞれ示しています。
つまり、この加算は「1歳児の配置を手厚くした園」に与えられるのではなく、「職員を大切にし、長く働き続けてもらえる環境を整え、テクノロジーを活用して効率的な運営を実現している、総合力の高い優良な園」が、さらなる質の向上(1歳児配置改善)に取り組むことを支援するための制度なのです。これは、今後の公定価格が、施設の総合的な運営品質を評価する方向へシフトしていくことを示す、重要な試金石と言えるでしょう。
経営への影響は?シミュレーションで見る収入の変化
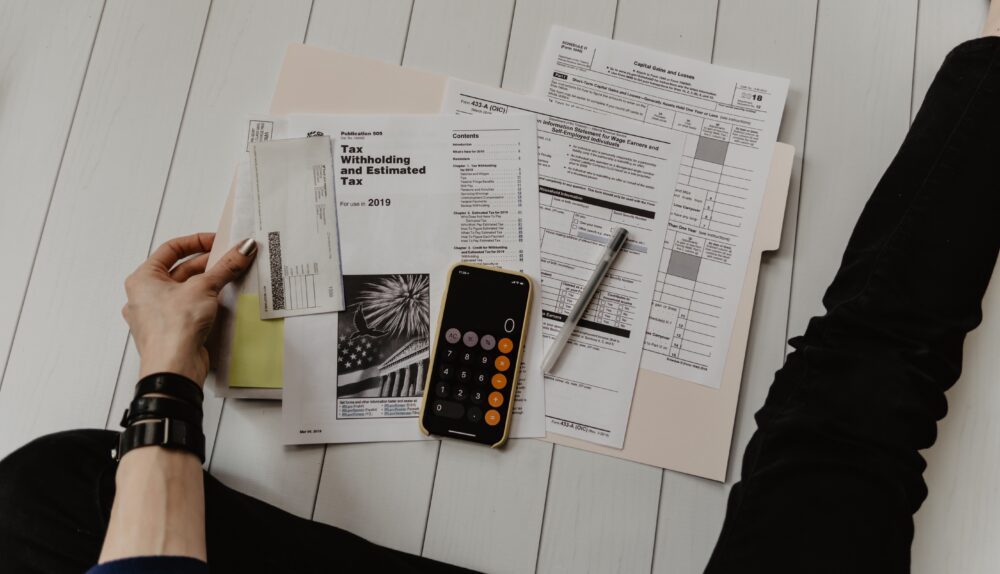
では、これらの改定は実際の園の収入にどれほどのインパクトを与えるのでしょうか。具体的なモデルケースを用いて、その影響をシミュレーションしてみましょう。
【モデルケース】
- 施設概要: 私立認可保育所
- 利用定員: 45人
- 所在地: 16/100地域
- 在籍園児(標準時間): 1歳児 8名、3歳児 15名、4歳以上児 22名
- 運営状況: 職員の平均経験年数11年、処遇改善等加算I,II,IIIを全て取得済み、ICTも活用しており、「1歳児配置改善加算」の要件を満たすものとする。
Step 1: 基本分単価の変動による影響
まず、定員区分の細分化が基本収入に与える影響を見てみます。
- 令和6年度の計算
定員45人のため、「41人~50人」の区分が適用されます。
令和6年度の単価表(16/100地域)に基づくと
- 1・2歳児単価: 139,490円
- 3歳児単価: 66,220円
- 4歳以上児単価: 56,120円
- 月額基本収入: (139,490円 × 8人) + (66,220円 × 15人) + (56,120円 × 22人) = 3,342,860円
- 令和7年度の計算
定員45人のため、新設された「41人~45人」の区分が適用されます。この区分の単価は、従来の「41人~50人」区分より高くなると想定されます(ここでは仮に3%増と仮定)。
- 1・2歳児単価: 139,490円 × 1.03 ≒ 143,670円
- 3歳児単価: 66,220円 × 1.03 ≒ 68,210円
- 4歳以上児単価: 56,120円 × 1.03 ≒ 57,800円
- 月額基本収入: (143,670円 × 8人) + (68,210円 × 15人) + (57,800円 × 22人) = 3,442,710円
- 影響: このケースでは、定員区分の細分化だけで 月額約99,850円の増収 が見込めます。
Step 2: 「1歳児配置改善加算」の取得による影響
次に、このモデル園が新たに「1歳児配置改善加算」を取得した場合の増収額を計算します。加算額の算定は複雑ですが、公表資料の計算例を参考にすると、1歳児一人当たり月額2万円程度の加算が見込まれる場合があります。
- 加算額: 20,000円/人 × 8人 = 160,000円/月
まとめ:収入変化の全体像
| 項目 | 令和6年度 月額収入 | 令和7年度 月額収入 | 増減額 |
| 基本分単価 | 3,342,860円 | 3,442,710円 | +99,850円 |
| 1歳児配置改善加算 | 0円 | 160,000円 | +160,000円 |
| 合計 | 3,342,860円 | 3,602,710円 | +259,850円 |
このシミュレーションから分かるように、今回の改定は、要件を満たす施設にとって大幅な増収に繋がるポテンシャルを秘めています。特に、これまで運営努力を重ねてきた質の高い施設ほど、その恩恵を大きく受けられる構造となっています。
経営者が今すぐ取り組むべき3つのアクションプラン

今回の大きな変化を前に、経営者はただ待つのではなく、積極的に行動を起こす必要があります。以下に、今すぐ着手すべき3つのアクションプランを提案します。
Action 1: 収支計画の再策定と資金使途の検討
最も緊急性が高いのは、財務計画の見直しです。
まずは、自園が令和7年度からどの「定員区分」に該当するのかを正確に確認し、新しい基本分単価に基づいた年間の収入予測を再計算してください。シミュレーションで示した通り、定員区分の変更だけでも収支に大きな影響を与える可能性があります。
その上で、「1歳児配置改善加算」やその他の加算項目について、自園が取得可能かどうかを精査し、増収見込み額を算出します。増収が見込める場合は、その資金をどのように活用するか(例:さらなる職員の処遇改善、保育環境の整備、ICTへの追加投資など)、具体的な使途計画を早期に策定することが重要です。
Action 2: 給与体系の見直しと職員への丁寧な説明
処遇改善等加算の一本化と配分ルールの柔軟化は、各園の給与体系を見直す絶好の機会です。
これまでの画一的な配分から脱却し、自園の人材育成方針や理念に基づいた、メリハリのある給与体系を再設計しましょう。例えば、勤続年数、役職、専門性、貢献度などをどのように評価し、給与に反映させるか。リーダー層にどの程度手厚く配分するのか。複数のシミュレーションを行い、最も効果的な配分方法を検討してください。
そして何よりも重要なのが、職員への丁寧な説明です。なぜ給与体系を変更するのか、新しい制度が職員一人ひとりにとってどのようなメリットがあるのかを、全職員が納得できるよう透明性をもって説明する場を設けることが、組織の信頼関係を維持し、職員のモチベーションを高める上で不可欠です。
Action 3: 「1歳児配置改善加算」の取得に向けた戦略的ロードマップの策定
「1歳児配置改善加算」は、単なる追加収入源ではなく、自園の運営品質を客観的に測る指標となります。まずは、取得要件である4つの項目(①5:1配置、②旧処遇改善全取得、③平均経験年数10年以上、④ICT活用)について、自園の現状を冷静に自己評価してください。
もし未達の項目があれば、それをクリアするための具体的な中期計画(ロードマップ)を策定しましょう。例えば、平均経験年数が足りないなら、職員の離職率を低下させるための職場環境改善に本格的に取り組む必要があります。ICTの活用が不十分なら、どの業務にどのシステムを導入すれば効果的か、情報収集とベンダー選定を開始すべきです。この加算取得に向けたプロセスそのものが、自園の経営体質を強化し、将来の持続可能性を高めることに繋がります。
公定価格に関するよくある質問(FAQ)
最後に、経営者の皆様から寄せられることの多い公定価格に関する疑問にお答えします。
Q1: 自分の園の地域区分はどこで確認できますか?
A1: 地域区分は、施設が所在する市町村ごとに定められています。基本的には国家公務員の地域手当の支給区分に準拠しており、各自治体の子育て支援担当部署から公表される資料や、こども家庭庁のウェブサイトで確認することができます。ご自身の市町村がどの区分に該当するか、最新の情報を必ずご確認ください。
Q2: 年度途中で園児の人数が変動した場合、公定価格はどうなりますか?
A2: 公定価格に基づく委託費(給付費)は、原則として毎月1日時点の在籍園児数に基づいて算定されます。そのため、年度の途中で園児の入退所があった場合、その翌月から委託費(給付費)の額も変動します。月ごとの園児数を正確に把握し、収入予測を立てることが重要です。
Q3: 処遇改善等加算で得たお金は、全額職員の給与に充てなければいけませんか?
A3: はい、その通りです。処遇改善等加算は、その全額を職員の賃金改善(基本給、手当、賞与など)に充てることが義務付けられています。法定福利費の事業主負担分の増加分に充当することは可能ですが、それ以外の目的(例えば施設の設備投資など)に使用することはできません。年度末には、実際に支払った賃金改善額が加算額を上回っていることを証明する実績報告書の提出が求められます。
Q4: 「1歳児配置改善加算」の要件にある「ICTの活用」とは、具体的に何を指しますか?
A4: 具体的な要件が定められています。まず、保育業務支援システムの「登降園管理」機能の活用が必須です。それに加えて、「保護者連絡」「計画・記録」「利用料等のキャッシュレス決済」といった機能の中から、少なくとももう1つ以上の機能を導入し、実際に業務で活用している必要があります。単にシステムを導入しているだけでなく、それによって業務が効率化されている実態が求められます。
Q5: 公定価格(委託費)の使い道に制限はありますか?
A5: はい、厳格な使途制限があります。委託費は、保育所の運営に直接必要な経費(人件費、事業費、管理費など)に充てるためのものであり、それ以外の目的(例えば、関連法人への過度な貸付や、運営とは無関係な投資など)に使用することは認められていません。自治体による監査の対象となり、不適切な支出が認められた場合は、費用の返還を求められることもあります。
まとめ:変化をチャンスに変えるために
令和7年度の公定価格改定は、単なる単価の変更にとどまらず、保育施設の経営そのもののあり方を問い直す、大きな転換点です。
処遇改善等加算の一本化は、経営者に「戦略的な人事・給与制度を設計する自由と責任」を与えました。定員区分の細分化は、特に小規模園に「安定した経営基盤」を提供します。そして、新設された1歳児配置改善加算は、総合的に質の高い運営を行う施設が正当に評価され、報われる「新たな品質基準」を提示しました。
これらの変化は、一見すると複雑で対応が大変に思えるかもしれません。しかし、その本質を理解すれば、自園の保育の質と経営の安定性を同時に高めるための、またとないチャンスであることが分かります。
変化の波にただ流されるのではなく、その波を乗りこなし、自園の発展の追い風とすること。この記事が、そのための羅針盤として、保育の未来を担うすべての経営者の皆様の一助となれば幸いです。
\自園と相性のよい人材が長く働いてくれる、保育のカタチの採用支援/