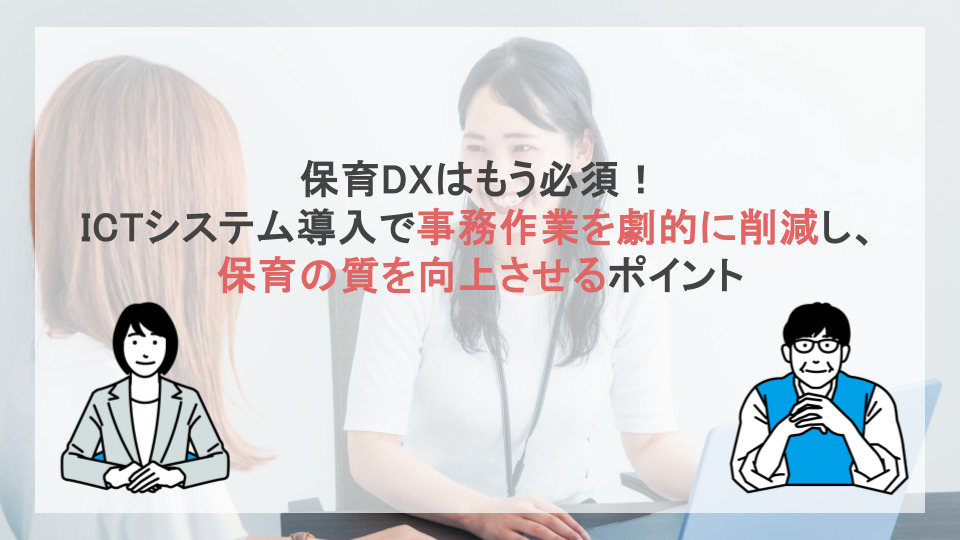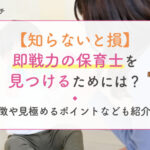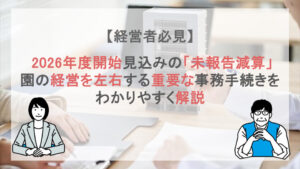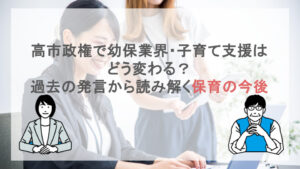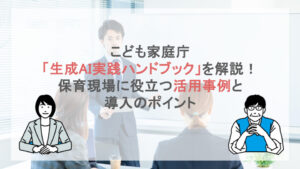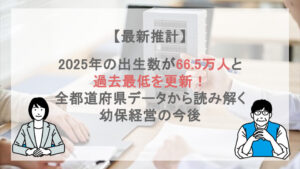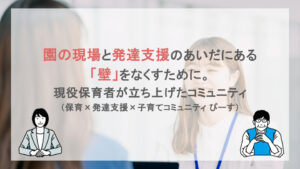保育業界では、少子化対策や働き方改革に伴う保育現場の負担軽減が急務となっています。そんな中、業務の効率化や子どもの安全を確保するためにデジタル技術を活用する“保育DX”が注目を集めています。保育士の事務作業を削減することで、本来の保育に割ける時間を増やし、子ども一人ひとりと向き合う環境づくりが期待されています。
本記事では、保育DXの背景や目的、実際に得られるメリットと導入上の課題を整理し、保育施設のDX化を成功に導くためのポイントを解説します。保育に関わる方々だけでなく、子育てを支える社会全体にとって有益な内容となっていますので、ぜひご覧ください。保育ICTサービス導入の成功事例も紹介しているので、ぜひ最後までご参考ください。
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/
保育業界でDXが注目される背景

保育の現場では慢性的な人材不足や長時間労働が課題となっており、これを解決するための方策としてDXが取り上げられています。
保育業界では、一人の保育士が担う作業範囲が非常に広く、子どものお世話や安全管理に加え、細かな書類作成や事務作業なども日常的に行わなければなりません。このような負担の大きさから保育士の離職率が高まり、人員不足が深刻化しています。そこで注目されているのが、デジタル技術を使った業務の効率化、いわゆる保育DXです。
保育DXを導入することで、書類業務やコミュニケーションが効率化され、職員の働きやすさや保護者との連携強化が期待できます。また、データを活用することで園の運営を最適化し、子どもの発達状況や安全管理にもつながります。社会全体の少子化対策の観点からも、保育環境の質を高めるためにDXが大きなカギとなっています。
「IT化」「ICT化」「DX」の違いと保育現場への応用
IT化するだけでなく、職員間や保護者との情報共有を進め、業務全体をデジタルで再設計するDXが求められています。
まずIT化とは、アナログ業務を単純にデジタル機器へ置き換えることを指します。これに対しICT化は、情報技術を使ってコミュニケーションを円滑化し、情報伝達や管理方法を高度化する狙いがあります。しかし保育DXでは、そこからさらに踏み込み、経済産業省の定義に沿った形で組織のビジネスモデルや業務プロセスそのものを革新することが重視されます。
保育現場においては、単に帳票をデジタル化するだけでなく、保護者との連絡帳をオンラインで行ったり、人事や研修管理をクラウド上で一元化したりと、作業プロセス全体を見直すことが求められます。これにより保育園や幼稚園内での情報共有がスムーズになり、施設間連携や職員同士の負担軽減につながる可能性が広がります。
保育DXの目的と本質:子ども・保護者・保育士の負担軽減とは
単なる業務効率化だけでなく、子どもの成長を手厚くサポートするための時間や人的リソースを生み出すことが保育DXの真価です。
従来の保育現場では、園児の様子を丁寧に記録する作業や、保護者への連絡帳記入など、多岐にわたる業務が山積みになりがちでした。保育DXの導入によって、こうした事務作業を大幅に減らし、保育士が子どもの成長や学びにしっかり向き合う時間を確保できるようになります。
保護者にとっても、オンラインで日々の様子を確認できたり、保育計画や連絡事項が迅速に共有されたりするメリットがあります。つまり、保育施設側の効率化だけでなく、子どもと保護者の満足度向上にもつながり、結果的により充実した子育て支援環境が構築されるのです。
保育DXのメリット①:保育施設の業務効率化
デジタルツールの導入により、書類整理や連絡業務といった煩雑な作業を削減し、本来の保育に注力できる環境を作ることが可能です。
保育現場では子どもの情報共有や出席管理、各種申請書類など、多数の事務作業が発生します。これらを紙ベースで行う場合、更新や共有に時間がかかり、ミスが生じるリスクも否定できません。デジタルツールやクラウドサービスを用いることで、作業時間を削減し、業務プロセスの透明性と正確性を高めることができます。
特にICTシステムを活用した一元管理が普及しつつあり、情報検索の手間を省き、フォーマットの統一によるミスの減少など、多方面にメリットをもたらしています。これらの仕組みを取り入れることで、保護者との連絡対応に追われる時間を減らし、子どものサポートに重点を置けるようになるのが大きな利点です。
記録業務の削減で残業を減らす仕組みづくり
これまで紙に手書きして保管していた保育日誌や子ども一人ひとりの観察記録をシステム上で管理することで、保育士の作業時間を大幅に削減できます。適切なシステムを選ぶと、スマートフォンやタブレット端末を使って瞬時にデータ入力が可能になり、更新や共有の手間が減少します。結果として、残業や休日出勤を抑え、保育士が心身ともに余裕を持って保育に取り組める環境づくりが期待されます。
デジタル連絡帳で保護者とのコミュニケーションをスムーズに
連絡帳アプリやチャットツールを導入することで、保護者が子どもの様子をリアルタイムで知ることができ、気になる点をすぐに相談できます。紙の連絡帳では起こりがちな記入ミスや伝達漏れも減少し、保育士の記入作業に伴う時間削減も実現します。結果として、双方の安心感が高まり、保護者満足度の向上にも直結します。
オンラインシステム導入による職員間の情報共有の最適化
クラウドを活用し、園児ごとの情報や業務マニュアルなどをデータベース化すると、複数の保育士が同時に情報を確認・更新できる環境が整います。これにより引き継ぎミスや二重入力のリスクを下げ、全体の業務効率を飛躍的に向上させることが可能です。職員同士のコミュニケーションロスも減り、迅速かつ柔軟な連携を実現します。
保育DXのメリット②:保育の質向上と働きやすい環境づくり
デジタル化の恩恵は業務効率化だけでなく、子どもの成長を把握し支援する質の高い保育と、スタッフの負担軽減にもつながります。
書類作成や記録業務が減ると、保育士は子ども一人ひとりに目を配る時間を確保しやすくなります。例えば、タブレット端末で日々の活動内容を記録すれば、効率よくその日の振り返りができ、次のアクティビティに活かすことも可能です。これによって、より個々の成長に合った保育プランを提案しやすくなります。
一方、働きやすい職場環境の整備が進むことで、保育士のモチベーションも向上しやすいという利点があります。デジタルツールが煩雑な作業を引き受けてくれることで、専門家としてのスキルアップや研修への時間を捻出する余地も生まれ、結果的に保育の質を一層高めることができます。
子どもの発達記録や健康管理のデータ活用
子どもの身体計測や健康状態、アレルギー情報などをデータ管理し、定期的に更新していくことで、保育士がより的確に保育計画を立てられるようになります。実際にデータを分析すれば、保育の方向性や個別ニーズを把握しやすくなり、早期に必要なフォローを行うことが可能です。
スタッフの離職率低減につながるサポート体制
保育士が長時間労働や膨大な事務負担に追われると、離職率が高まる傾向があります。DXシステムの導入によって、これらの負担を軽減し、ワークライフバランスを維持することで、離職率の低下や保育士の定着率向上を期待できます。結果として、子どもたちが慣れ親しんだ保育士と継続的に過ごせるメリットも生まれます。
保育DX化が進む上での課題とデメリット
メリットの多いDX導入でも、初期投資やセキュリティなど乗り越えなければならない課題やリスクが存在します。
保育DXの本格導入には、システムや機器の購入費用、現場スタッフへの教育コストなど、多くの投資が必要となります。特に予算に限りのある保育施設では、綿密な計画と導入後の運用を考慮することが不可欠です。
また、デジタル化による利便性と引き換えに、システムトラブルやデータ漏えいのリスクも増加します。安全性と効果のバランスを保ちつつ、確実に現場で活用できる仕組みを作るには、専門知識が必要です。
初期導入コストとITインフラ整備の必要性
DX化を進めるには、タブレットやパソコン、サーバーなどのハードウェア投資だけでなく、ソフトウェア利用料やネットワーク環境の整備も考慮する必要があります。公的補助金や助成制度を活用しても、ある程度の自己負担は避けられず、設備投資計画を立てることが重要です。
セキュリティやプライバシーのリスク管理
保育施設が扱う情報には、子どもの健康状態や家族構成など、極めてプライバシー性の高いデータが含まれます。導入時にはセキュリティ対策が万全なシステムを選定し、定期的に運用チェックを行うことで情報漏えいリスクを最低限に抑えることが求められます。
DXツール導入時のスタッフ教育・ITリテラシーの問題
新しいシステムや機器を導入しても、使いこなせるスタッフがいなければその効果は最大限発揮されません。導入前後の研修や日常的なサポート体制を整え、ITが苦手な職員でも円滑に利用できるようにすることで、保育DXのメリットを十分に享受できます。
保育DXの具体的な導入事例

すでに多くの園や保育施設がDXに取り組んでおり、さまざまな成功事例が生まれています。
実際に導入事例を調べると、登降園管理システムやクラウド型の保育記録システムなど、さまざまなツールが現場で活用されています。これにより、業務の効率化だけでなく、事故リスクの低減や緊急時の対応迅速化など、子どもたちの安全性向上にも寄与しているケースが多く見受けられます。
また、記録業務のデジタル化が進むことで、保育計画の作成や振り返りもスマートフォンやパソコンで手早く行えるようになりました。職員同士の連携が強化され、子どもの発育状況に応じたきめ細かいプログラムを組むことも容易となっています。
登降園管理システム導入による保護者との情報共有強化
タッチパネルやQRコードを使ったシステムでは、保護者が園に来たタイミングで端末にアクセスし、登園・降園時刻を記録します。これにより職員側の入力ミスを減らし、保護者への通知を自動化することで、子どもの安全確認とコミュニケーションを同時に効率化できる事例が増えています。
午睡センサー導入で子どもの安全を守りつつ保育士の心理的負担を軽減
午睡センサーは、子どもの呼吸や体動を検知して異常があればアラートを発する仕組みです。職員がひとりひとりを頻繁に巡回しなくても安全管理ができ、ヒヤリハットを減らす効果が期待できます。保育士の安心感が高まることで、より落ち着いて子どもたちと向き合えるという利点も得られます。
クラウド活用で保育計画・教材データを一元管理
クラウド上で保育計画や教材データを一元管理すると、年度ごとの更新作業がスムーズになり、過去の資料を簡単に参照できるようになります。チーム内で瞬時に情報を共有できるため、職員の急な欠勤やシフト変更にも柔軟に対応しやすく、保育の質を保つうえでも有効です。
保育DX推進に役立つ補助金と自治体支援制度
公共機関や自治体の支援制度を活用することで、保育施設のDX導入コストを大きく削減できます。
国や自治体では、保育ICT化に向けた補助金や助成金プログラムを用意しています。これらを活用すると、システム導入費用やデバイス購入費用の一部を補填できるため、予算が限られる保育園や幼稚園にもDX導入のハードルが下がります。
ただし、各制度の適用条件や応募手続きは自治体ごとに異なることが多いため、最新の情報を調査し、要件を満たすよう計画立案をすることが重要です。こうした支援を上手に活用すれば、コスト面でのリスクを抑えながらDXの効果を早期に実感できます。
保育DXを成功に導くポイント
DX化を確実に進めるためには、明確な計画やスタッフ教育など、段階ごとの取り組みが重要です。
保育DXを計画的に進めるためには、どの業務を優先的にデジタル化するかを見極めることが肝心です。短期的に成果を出しやすい領域から実施し、徐々に範囲を拡大することで、スタッフ同士の理解や協力を得やすくなります。
また、導入後も継続的な改善を図る姿勢が欠かせません。保育士やスタッフの声をこまめに拾い上げ、運用上の問題点や追加機能のニーズを洗い出すことで、現場に合った最適なDXを実現できます。
段階的な導入計画と試験運用の重要性
いきなり全工程をデジタル化すると、スタッフに大きな負荷がかかり、システムトラブルのリスクも増大します。まずは一部分から試験運用を行い、問題点や改善策を見出したうえで段階的に拡大していく方法が安心です。
保育士・スタッフへの研修とサポート体制づくり
システム導入後は、操作に慣れるまでにそれなりの時間を要します。研修会やマニュアルの整備、ヘルプデスクの設置など、アフターフォローを手厚く行うことで、定着を促し、スタッフ同士がサポートし合える環境を作り上げることが大切です。
ITベンダーや専門家との連携によるリスク回避
DX化をスムーズに進めるためには、信頼できるITベンダーや専門家との連携が欠かせません。システム開発や導入の計画段階で適切なアドバイスを得ることで、セキュリティ面や予算面のリスクを最小限に抑え、より最適な形で保育施設への導入を実現できるでしょう。
まとめ・総括:保育DXが切り拓く次世代の子育て環境
保育DXは、子ども・保護者・保育士すべてに恩恵を与え、今後の保育環境を大きく変える可能性を秘めています。
保育DXの導入には一定のコストやスタッフのITリテラシー向上などの課題があるものの、それを上回るメリットが存在します。業務効率化によって保育士が子どもと向き合う時間が増え、保護者との連携が強化され、結果的に保育の質が向上する効果は大きいといえます。
今後ますます深刻化する保育ニーズに対応するためにも、ICTシステムやクラウド活用による革新的な取り組みが欠かせません。これまでの慣習にとらわれず、デジタル技術を上手に取り入れて、子どもたちにとってより良い保育環境を目指していくことが重要です。
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/