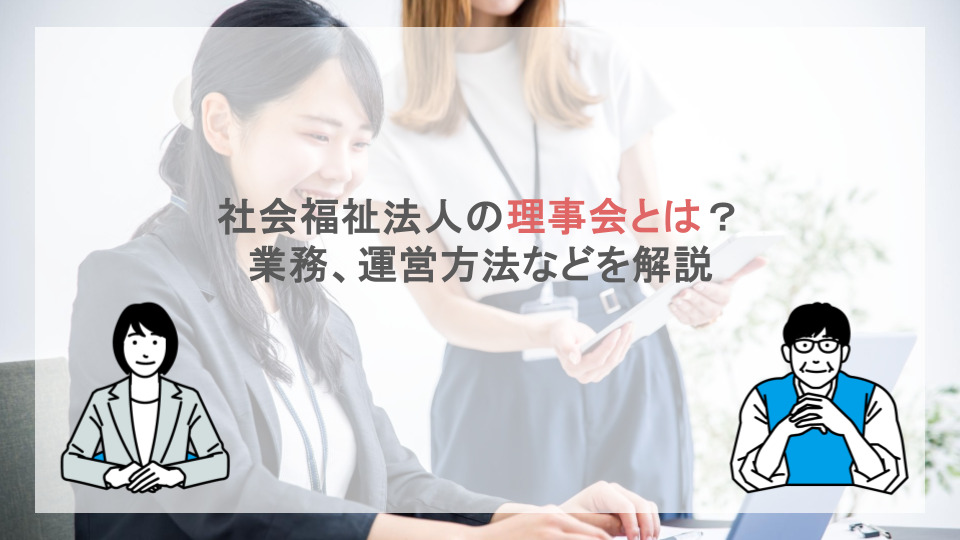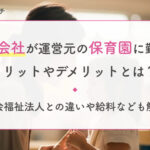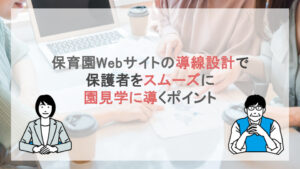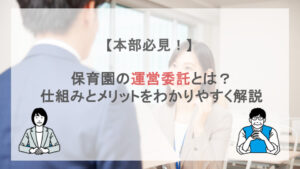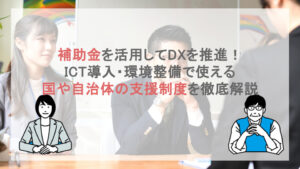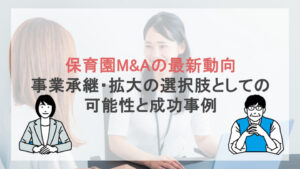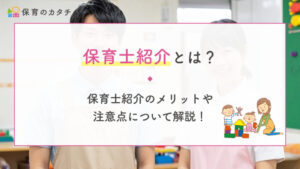社会福祉法人においては、理事会が内部統制や方針決定の要を担っており、法人の適正な運営に欠かせない存在です。多くのステークホルダーが関わる中で、公的資金を有効かつ公平に活用するためにも、理事会の果たす役割はますます重要視されています。
しかし、理事会の責任範囲や理事同士の連携方法、評議員会や監事などの他機関との関係を十分に把握しないまま運営を進めると、ガバナンス上のリスクや不正を見過ごす可能性があります。正しい知識と実務的な手順を理解して、透明性を高めることが法人の信頼を築く近道です。
本記事では、社会福祉法人 理事会の位置づけや設置要件、運営ルールなどを分かりやすく解説するとともに、実務上の注意点やガバナンス強化のポイントもあわせて紹介します。理事会を活性化させたいと考えている方や、これから理事に就任する方はぜひ参考にしてください。
\支援実績1000社以上!園の全体最適を考えた採用をサポート!/
\自園と相性のよい人材が長く働いてくれる、保育のカタチの採用支援/
社会福祉法人における理事会の位置づけ

ここでは、理事会が社会福祉法人全体の運営においてどのような位置づけを持ち、何が求められているのかを確認します。
社会福祉法人は、公的資金をもとに社会福祉事業を行う性質上、高い透明性と説明責任が求められます。理事会はその中核として法人が向かう方向性を示し、事業計画や運営方針を決定する重大な責任を負います。適切なガバナンス体制を構築するためにも、理事会のあり方を正しく理解し、法人内部で共有しておくことが重要です。
理事会は単に方針を決定するだけでなく、実際の業務執行を監督し、必要に応じた見直しや改善を図る役割も担います。理事同士の緊密なコミュニケーションや、他の機関との協力体制が整っていなければ、施策の実現やリスク管理が疎かになる可能性があります。こうした観点から、理事会の運営は法人全体の信頼に直結する要素といえます。
理事会の適切な位置づけを定義するためには、定款や法令によって定められた要件を正しく理解することが第一歩です。その上で、実際の運営における手続きや意思決定フローを整備し、定期的に点検を行うことが望まれます。これらの取り組みにより、理事会の機能を十分に発揮し、公正性や信頼性を高めることができるでしょう。
社会福祉法人が求められるガバナンスの確保
社会福祉法人は、国や自治体からの補助金をはじめとする公的資金を活用して事業を行います。そのため、経営の透明性や意思決定の公平性が特に重視され、公的な観点からの監査や監督も強化されています。こうした背景のもとでは理事会が主導して公正な内部統制を整え、法人運営における不正やリスクを未然に防止するガバナンス体制を確立することが求められます。
具体的には、理事会が定期的に開催され、事業施策や財務状況に関する情報を正確に共有することが必要です。また、監査体制の充実や評議員会からの意見の取り込みなど、多角的なチェック機能を活かすことで、より監督力を高めることが可能です。これらの取り組みによって、社会的信用の獲得や利用者保護の実現へとつなげることができます。
理事会が担う基本責任と重要性
理事会は、法人全体の方針決定とともに、理事の職務執行状況を確認し、必要な修正や注意喚起を行う監督機能を兼ね備えています。理事会で決定された施策や予算方針が適正かつ効率的に運用されるかどうかは、法人活動の成果だけでなく、社会的信用にも直結します。そのため、理事会の一人ひとりは重い責任感を持ち、慎重な審議と情報共有を行うことが必要です。
理事会が有効に機能するためには、リーダーシップを担う理事長や他の理事間の協力体制が不可欠です。議決においては多数決の原則が採用されるものの、ただ数字だけで結論を出すのではなく、社会福祉法人の公益目的を踏まえた議論が重要となります。こうしたプロセスの中で、理事会の存在意義が発揮され、法人の方向性をより明確に示すことができるでしょう。
社会福祉法人の機関設計と理事会

次に、社会福祉法人の全体機構の中で、理事会と他の機関がどのように連携しているのかを整理します。
社会福祉法人は、理事会以外にも評議員会や監事など、多くの機関によって支えられています。評議員会は法人の基本方針を審議し、理事や監事の選任・解任を決定する役割を担い、理事会との連携を通じて全体の統括を行います。監事は財政状況や理事の職務執行を監査する独立した立場であり、内部から適正性を確保する仕組みとして機能します。
これらの各機関が相互に独立しながらも協力し合うことで、法人のガバナンスが高まり、リスク回避や適切な資金運用が期待されます。理事会は業務執行に対する最高意思決定機関である一方、評議員会や監事からのチェックを受けることで透明性の確保を図ります。複数の視点から検証を重ねることができる体制が、信頼性の高い社会福祉事業を支える基盤となります。
規模の大きい社会福祉法人では、加えて会計監査人の導入が法令などで義務づけられる場合があります。専門的な立場から財務諸表や会計処理に問題がないかを監査し、法人運営の一層の透明性を高めます。これらの仕組みが総合的に機能することで、利用者や地域社会からの信頼を長期的に維持することが可能となるでしょう。
評議員・評議員会との関係
評議員会は社会福祉法人における重要な機関であり、主に理事や監事の選任・解任、定款変更の審議、法人運営の基本方針の承認などを行います。理事会が策定した事業計画や予算案について、評議員が意見を出し合うことで、法人運営の健全性を高める役割を担います。
理事会としては、評議員会への情報提供を適時かつ正確に行うことがガバナンスを機能させる上で不可欠です。特に、年に複数回行われる評議員会の開催時には、十分な資料と説明が用意されているかを確認し、双方でコンセンサスを形成できるよう取り組むことが大切です。
理事・監事・会計監査人との関係
理事は法人の業務執行を担い、理事会にはその主任務を全うするための意思決定領域が広く与えられています。一方、監事は理事に対して監督機能を果たし、業務や会計処理の適正を確保する役割を担います。また、法人の規模によっては会計監査人が選任され、財務諸表や会計処理の透明性をさらに高める仕組みが導入されます。
これらの機関はそれぞれ独立した権限のもとに活動しますが、理事会の決定事項を補完し、適正なガバナンス体制を築くために連携が欠かせません。情報や意見交換の場を増やし、必要に応じて意見を反映させることで、内部統制の質をより高めることが期待されます。
役員等の兼務について(特殊関係含む)
社会福祉法人では利益相反や不正を防止する観点から、役員同士の兼務や親族関係にある者同士の同時就任などに一定の制限があります。例えば、理事と監事を同一人物が兼任することは、監査機能の独立性を損なうため禁じられています。また、特殊関係者が集中して役職を占めることも避けるべきとされています。
こうした制限を守らずに運営を続けると、法人内部のチェック体制そのものが形骸化し、公的資金の不正利用や利益相反の温床となるリスクがあります。役員の人選にあたっては定款や関連法令をしっかりと確認し、疑義がある場合は専門家の意見を求めることが望ましいでしょう。
理事会の設置要件と構成
ここでは、理事会の設置要件や具体的な構成要素について解説します。
社会福祉法人には、少なくとも一定数の理事を置くことが義務付けられており、これによって理事会という意思決定機関が形成されます。法人の規模や事業内容に応じた人員構成を整え、業務の専門性を幅広くカバーすることが理事会の円滑な運営には欠かせません。また、定款には理事の数や理事長の選任方法などが定められているため、事前にこれらをチェックしておくことが必要です。
社会福祉法人の理事は、法人に対して忠実義務と善管注意義務を負うと同時に、理事会の合議による方針を支持する役割があります。理事が複数名就任することで専門分野からの意見を集約し、より客観性の高い意思決定を行うことができるようになります。理事長は全体を代表して法人を牽引する立場にあり、内部外部の利害をバランスよく調整する力量が求められます。
このように、理事会は法人の方針決定と業務執行の監督を担う中心的存在であるため、構成メンバーの選定は慎重に行う必要があります。評議員会の承認や定款の規定などを踏まえつつ、的確な人材をバランスよく配置することが、適正かつ効率的なガバナンスを築くうえで重要となるでしょう。
理事・理事長の選任・解任
社会福祉法人の理事や理事長は、評議員会の決議などを経て選任あるいは解任されます。選任にあたっては、候補者の社会福祉事業に対する理解やコンプライアンス意識、経営上の知見などが総合的に検討されます。理事を増やす場合や変更する場合は、定款の規定だけでなく、法人の現状や将来像にも目を向けることが大切です。
また、解任についてはやむを得ない事情や不正防止の観点から行われる場合があります。いずれの場合も、評議員会での議決や監事の意見聴取など透明性のある手続きを経ることで、後々のトラブルを防ぐことに繋がります。
理事会から理事に委任できない事項
社会福祉法人の中核を担う理事会では多くの業務執行を決定しますが、その中には理事会のみが決裁可能な重要事項も含まれます。定款変更のように法人の基本構造に関わる事項や、大規模な財産処分・借財など、意思決定において慎重な審議が必要な項目は理事会の専決事項とされています。
理事に一定の業務を委任することで運営はスムーズになりますが、委任できない事項まで個々の理事に任せてしまうと、法人としての統制が取れなくなる恐れがあります。重要な事項は必ず理事会で議論し、必要に応じて評議員会や監事との連携を図りながら、責任ある意思決定を行うことが求められます。
理事会の職務・権限の具体例
社会福祉法人の理事会は、業務執行の決定や財産の処分・譲受け、重要な職員の選任・解任など、多岐にわたる事項を審議・決定する権限を有しています。これらの事項は法人活動の根幹を成すため、理事会での議論を充実させ、合議を重ねることが不可欠です。
また、理事長や業務執行理事からの事業報告を受けることも理事会の重要な職務のひとつです。こうした情報共有によって理事会のメンバーが法人の現状と課題を正しく把握し、より良い運営体制づくりに活かすことができます。
理事会の開催と運営ルール
理事会を円滑に運営するために、開催までの手続きや決議方法、議事録作成などのルールを確認します。
理事会は法人の運営方針や監督に関わる意思決定を行う場であるため、定期的かつ計画的に開催されることが重要です。通常は理事長が招集を行いますが、理事の一定数から請求があった場合は理事長が速やかに理事会を招集しなければなりません。事前に開催日程や議題を適切に告知し、全員が十分に準備できる環境を整えることが円滑な議事進行につながります。
決議においては、定足数(出席理事の過半数など)や議決要件を事前に確認する必要があります。特に特別利害関係がある理事は、議決に参加できない場合があるため、一人ひとりの利害状況を把握しておくことが大切です。こうしたルールを踏まえて審議を進めることで、決議の正当性と透明性を確保し、後日のトラブルを回避できます。
さらに、理事会の開催後には必ず議事録を作成し、適切に保管することが法律上の義務となっています。議事録には会議の日時、場所、出席理事の氏名、審議事項の概要、決議内容などを明確に記載しなければなりません。評議員など利害関係者からの閲覧請求があった場合に備えて、正確で網羅的な記録を残しておくことが大切です。
招集手続きとスケジュール管理
理事会の招集手続きとしては、まず理事長が開催日時や場所、議題などを事前に通知する方法が一般的です。招集通知の期限は定款や内規によって定められている場合があり、余裕を持ったスケジュールを組むことが望まれます。理事全員が充分な準備を行い、重要事項について意見交換や情報収集ができるよう配慮することで、実りある審議が可能となります。
また、緊急の問題が発生した場合にも柔軟に対応できる体制を整えておくことが大切です。オンライン会議の導入や、緊急時の簡易決議の手続きなどを検討しておくと、スピード感ある意思決定が行いやすくなります。それでも、法人の基盤に関わる重大事項については、必ず全員で十分に協議をしたうえで決議を行うことが理想です。
決議方法と議事録作成の要点
理事会の決議方法は、出席理事の過半数の同意による通常決議と、より厳格な要件を課す特別決議に大きく分かれます。具体的な要件は定款や法令によって異なるため、事前に確認しておく必要があります。特に重要な事項は理事全員の意思統一を図りながら、必要に応じて監事や専門家の意見を取り入れるなどして、より慎重に議決を行います。
議事録は理事会の手続きを公的に証明する重要な書類であり、後々の監査や評議員からの請求に応じる際にも役立ちます。作成の際には、会議の目的や議事内容、出席者名簿、決議の結論とその理由などを正確にまとめることが欠かせません。これにより、理事会の開催が適正に行われたかを客観的に示すことができます。
ガバナンス強化に向けた理事会の取り組み

理事会が中心となって進めるガバナンス強化の一端を紹介し、リスク管理やコンプライアンスの重要性に注目します。
社会福祉法人におけるガバナンス強化の取り組みは、日々の業務執行におけるリスクを見直し、早期発見と適切な対処を行う仕組みを整備することから始まります。理事会はこうしたリスク管理の方針を策定し、具体的なマニュアルや研修制度の導入を進めるなどの実務的アプローチが重要です。関連法令や社会情勢の変化を意識しながら継続的に見直しを行うことで、実効性を高めることができます。
また、コンプライアンスに関しては、職員や関係者全体への周知と徹底が欠かせません。理事会が率先して法令順守や倫理意識の向上を呼びかけ、疑義があった場合には早期に相談・報告ができる環境を整えることが効果的です。これらの取り組みによって、社会福祉法人の体制全体が強化され、公共性の高い福祉サービスの提供が安心して続けられるようになります。
リスク管理やコンプライアンス上の留意点
理事会としては、法人活動に関するリスクを全方位で把握し、法令違反や財務上の不透明さを防ぐための仕組みを整備することが大切です。例えば、内部通報制度を設けて不正を早期に発見する仕組みを作る、外部の専門家からチェックを受けるなどのアプローチが有効です。こうした対策によって、社会福祉法人としての信用を維持し、社会的責任を果たすことができます。
加えて、理事をはじめとする役職者には、コンプライアンス違反が見逃されないよう社内外の情報に常にアンテナを張ることが求められます。そのうえで、法人全体における法令順守の意識を高めるために、研修やマニュアルの整備など継続的な教育努力を行うことが望まれます。
理事会の運営に関するQ&A
理事会を運営していく上で生じる疑問点やトラブルシューティングについて、よくある質問を取り上げます。
Q: 理事会の開催はどのくらいの頻度で行えばよいのでしょうか? A: 法令上の定めはありませんが、定期的に開催することで情報共有と意思決定の迅速化を図ることが推奨されています。少なくとも決算期や大きな方針転換時などに合わせて開催するとよいでしょう。
Q: 議事録に記載すべき内容はどこまで詳細にする必要がありますか? A: 会議の概要だけでなく、決議事項とその理由、出席者、利害関係の有無なども明示し、監査や評議員会からの請求に耐えられる内容にすることが重要です。
Q: 理事や理事長が急遽退任する場合、どのような手続きが必要でしょうか? A: 退任理由にもよりますが、評議員会の承認を得た上で新理事を選任するなど、定款や法令に沿った手続きを踏む必要があります。この際は法人の運営体制が滞らないよう留意しましょう。
まとめ・総括
最後に、本記事で解説してきた要点を振り返り、理事会運営を活性化させるためのポイントを総括します。
社会福祉法人の理事会は、意思決定機関としての役割だけでなく、業務執行の監督やガバナンス体制の強化においても中核を担う重要な存在です。理事会が有効に機能すれば、公的資金を有効活用し、利用者や地域にとって高品質な福祉サービスを安定的に提供することが可能となります。
そのためには、評議員会や監事など他の機関との連携を欠かさず、リスク管理やコンプライアンスに関する取り組みを継続的に行うことが大切です。また、理事の選任・解任や理事会の運営ルールなどを正しく理解し、定期的に見直しを行うことで、法人運営の透明性と信頼性を一層高めることができます。
\支援実績1000社以上!園の全体最適を考えた採用をサポート!/
\自園と相性のよい人材が長く働いてくれる、保育のカタチの採用支援/