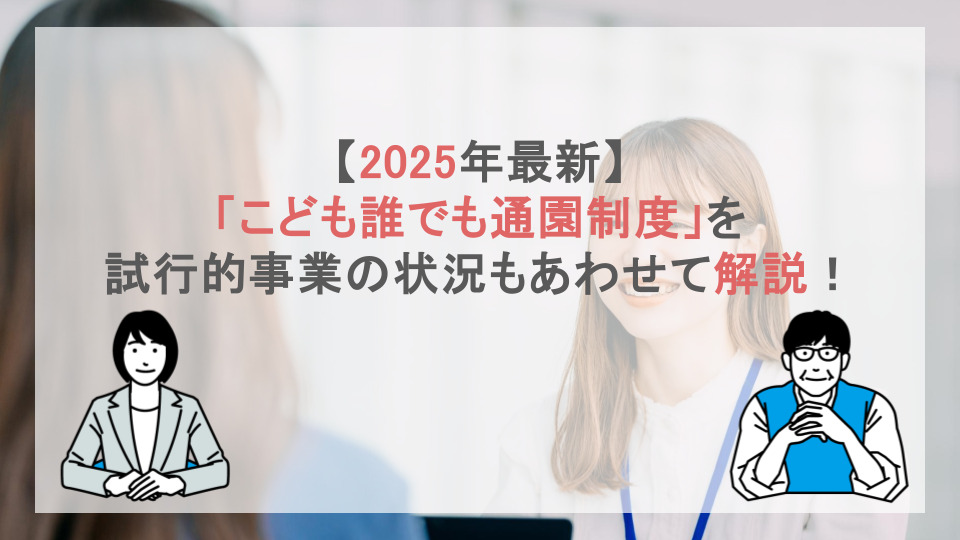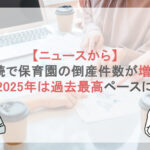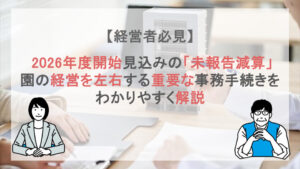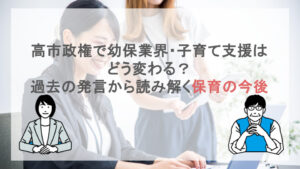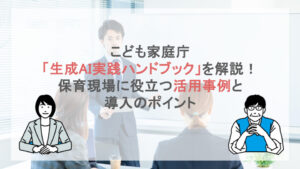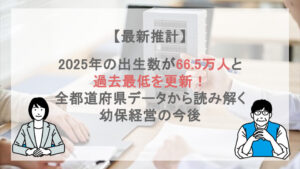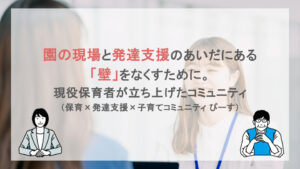「定員の空きが埋まらず、施設の将来に漠然とした不安がある…」
「地域の子育て家庭ともっと深く関わり、施設の価値を高めたい…」
2025年度から本格的に制度化される「こども誰でも通園制度」は、こうした課題を解決し、貴園の新たな可能性を拓く大きなチャンスかもしれません。もちろん、現場環境の充実は必要です。例えばSNS上では、保育現場の声として、「人員が増えないのに忙しくなる」「何かあった時にどうするのか」など、新制度に対しての不満の声もあがっています。
本記事では、国の資料を基に、この新制度を経営者・運営者の皆様の視点から分かりやすく解説します。制度の概要から、事業を始める具体的なステップ、運営上の留意点までわかりやすくご紹介します。
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/
3分でわかる「こども誰でも通園制度」のポイント
「こども誰でも通園制度」とは、保護者の就労要件にかかわらず、保育所などに通っていない0歳6ヶ月から満3歳未満のお子様が、月10時間を上限に、時間単位で柔軟に施設を利用できる新しい通園制度です。
- 目的は「こどもまんなか」:この制度は、保護者のリフレッシュなどを目的とした一時預かりとは異なり、すべてのこどもの健やかな成長を応援し、質の高い成育環境を整えることを主な目的としています。
- 多様な利用を想定:在宅で子育てをしているお子様が、家庭だけでは得られない多様な経験や他の子どもたちと関わる機会を提供します。 同時に、保護者の孤立感の解消や育児負担の軽減にも繋がることも期待されています。
- 特別な配慮が必要な子も:支援障害のあるお子様、医療的ケア児、その他支援が必要なご家庭のお子様も対象となり、受け入れる施設には特別な加算が適用される仕組みがあります。
- 多様な施設が実施可能:保育所、認定こども園、幼稚園はもちろん、地域子育て支援拠点など、市町村の認可を受ければ多様な施設が事業を実施できます。
- 2025年度からシステム運用開始:利用者の予約から施設の請求業務までを一元管理できる「こども誰でも通園制度総合支援システム」が導入され、運営の効率化が図られます。
こども誰でも通園制度に取り組むメリット

この制度は、単なる社会貢献活動ではありません。施設の経営基盤を強化し、持続的な発展に繋がる4つの大きなメリットがあります。
1. 施設の空き定員が「新たな収益源」に
利用児童の減少により、定員の充足が課題となっている施設にとって、この制度は大きなチャンスです。 既存の保育室や保育士などの資源(リソース)を有効活用し、新たな収益の柱を育てることができます。
2. 地域での「信頼とブランド価値」が向上
これまで接点のなかった地域の子育て家庭に広く門戸を開くことで、「地域に開かれた施設」としての認知度が高まります。 専門性を活かして地域の子育てを支えることで、社会的な評価と信頼を獲得し、施設のブランドイメージ向上に直結します。
3. 「未来の入園希望者」との出会いの場に
この制度の利用が、いわば施設の「お試し体験」となり、将来的な正規入園に繋がる可能性があります。保護者や子どもに施設の魅力や保育の質を直接体験してもらう絶好の機会です。
4. 保育者の「専門性発揮と離職防止」に貢献
多様な背景を持つ子どもや家庭と関わることは、保育者の専門性をより広い形で発揮する機会となります。 在宅で子育てをする保護者への支援などを通じて、保育者自身のスキルアップと仕事へのやりがいを高め、キャリアを積んだ人材の定着にも繋がります。
事業開始までの具体的な流れと実施形態
では、実際に事業を始めるにはどうすればよいのでしょうか。大まかな流れと、施設の状況に合わせて選べる実施形態を解説します。
事業開始までのフロー
事業を行うには、まず事業所の所在地がある市町村の認可を受ける必要があります。 手続きは市町村が行い、児童福祉審議会などへの意見聴取を経て、認可、開所に至ります。
児童福祉審議会等への意見聴取
※認可手続きの詳細は、事業所の所在地となる市町村へお問い合わせください。
施設の状況で選べる「2つの実施方法」
事業の実施方法は、大きく「余裕活用型」と「一般型」の2つに分けられます。
| 実施方法 | 概要 | こんな施設におすすめ |
| 余裕活用型 | 保育所等の既存の空き定員を活用して受け入れる方法。 利用する子どもは、主に同年齢の在園児と同じクラスで過ごします。 | ・まずはスモールスタートで始めたい ・初期投資を抑えたい |
| 一般型 | 制度のための定員を別途設けて受け入れる方法。 「在園児合同」「専用室独立」「独立施設」の3つの形態があります。 | ・安定的に事業を運営したい ・制度を本格的な事業の柱にしたい ・施設の特色や専門性を打ち出したい |
2024年11月末時点の試行的事業では、余裕活用型が43%と最も多く、次いで一般型(在園児合同)が31%、一般型(専用室独立)が26%となっています。 まずは既存の資源で始められる「余裕活用型」から検討する施設が多いようです。
先行事例に学ぶ!試行的事業の状況
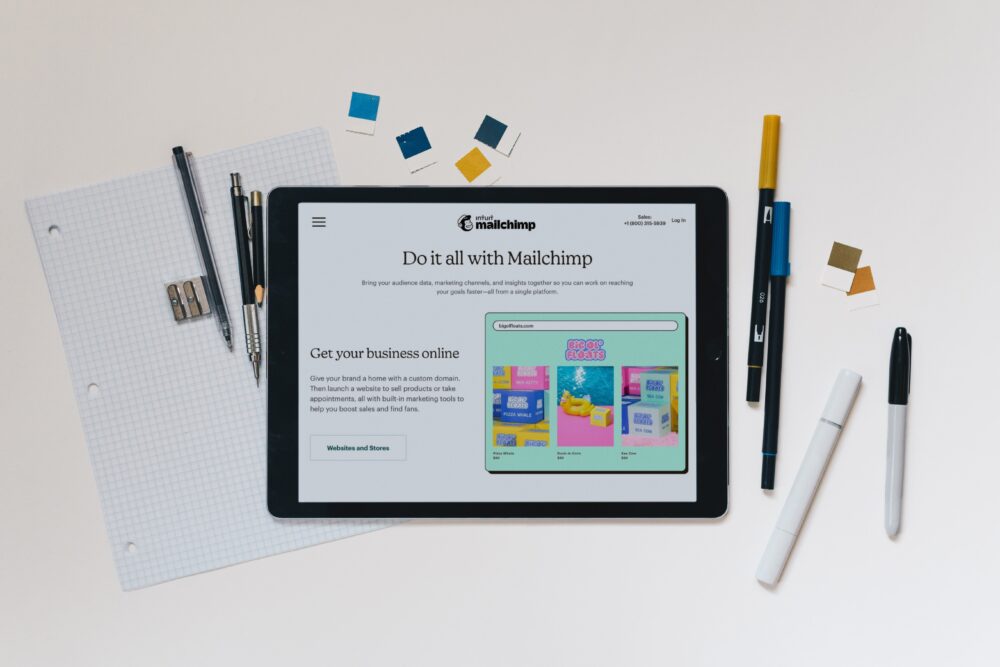
本格実施に先立ち、2024年度から全国で試行的事業が開始されています。 2024年11月30日時点のデータから、どのような施設が参入しているのか見てみましょう。
【データで見る】試行的事業の実施状況 (2024/11/30現在)
- 実施自治体数: 118自治体
- 開始事業所数: 801か所
▼ 事業所の類型
- 認可保育所・認定こども園(幼保連携型): 53.2%
- 小規模保育事業所(A型): 10.4%
- 認定こども園(幼稚園型): 6.4%
- 認定こども園(保育所型): 6.2%
- 幼稚園(施設型給付): 4.5%
- その他: 19.3%
▼ 運営主体
- 社会福祉法人: 43.1%
- 学校法人: 22.9%
- 公立: 17.9%
- 株式会社: 10.6%
- その他: 5.5%
認可保育所や認定こども園、運営主体としては社会福祉法人や学校法人が中心ですが、株式会社やNPO法人なども参入しており、多様なプレイヤーがこの新制度に注目していることがわかります。
【運営者向け】制度実施における8つの注意点

円滑な制度運営のためには、事前の準備と理解が不可欠です。現場の責任者として押さえておくべきポイントを8つにまとめました。
1. 安全確保は何よりも最優先
子どもの安全確保は、この制度の大前提です。 特に、重大事故が起こりやすい睡眠中・食事中・水遊び中は細心の注意が必要です。
- 情報共有: アレルギーの有無や緊急連絡先など、安全確保に必要な情報は利用前に必ず把握し、全職員で共有します。
- 安全計画: 事故防止マニュアルの策定や定期的な安全点検、災害時の避難計画などを定めた安全計画の策定が義務付けられています。
- SIDS対策: 窒息事故防止のため、医学的な理由がなければ仰向けに寝かせ、睡眠中の呼吸確認を徹底します。
2. 丁寧な「通園初期」の対応
初めての環境に不安を感じる子どもや保護者は少なくありません。安心して利用を開始できるよう、丁寧な初期対応が求められます。
- 事前面談: 初回利用の前に必ず保護者・子ども同席の面談を行い、施設のルールを説明し、子どもの特性や家庭での様子を把握します。 87%の事業所が初回の面談を実施しています。
- 親子通園: 環境に慣れるまでの対応として「親子通園」を取り入れることも有効です。 ただし、親子通園を利用の条件とすることは不適切とされています。
3. 「個別計画」と「記録」の重要性
利用頻度や成育歴が多様なため、一人ひとりの実態に応じた計画と記録が重要です。
- 計画作成: 長期的な視点に立った「全体的な計画」と、個々の状況に応じた「個別計画」を作成します。
- 記録の活用: 日々の様子を記録し職員間で共有することで、次回の利用時に一貫性のある適切な支援が可能になります。
4. 信頼関係を築く「保護者対応」
この制度は、保護者にとって身近な子育て相談の場としての役割も期待されています。
- 傾聴と受容: 保護者の気持ちを受け止め、信頼関係を築くことを基本とします。
- 自己決定の尊重: 保護者自身が考え、決定していくことを尊重する姿勢が大切です。
- 要支援家庭への気づき: 虐待の未然防止や早期発見の観点から、気になる様子が見られた場合は、速やかに市町村と連携することが求められます。
5. 特別な配慮が必要な子どもへの対応
障害の有無にかかわらず、すべての子どもが利用できるよう体制を整える必要があります。
- 事前の体制整備: 受け入れ方針を定め、専門人材の確保や関係機関との連携体制を構築します。
- 居宅訪問: 通園が難しい子ども(医療的ケア児など)に対しては、保育者を居宅へ派遣する形も運用上可能とされています。 ただし、安全確保のための体制整備が前提です。
6. 「総合支援システム」の活用
2025年度から、国が整備する「こども誰でも通園制度総合支援システム」が稼働します。
- 機能: 利用者の予約管理、事業者間の情報共有、自治体への費用請求などを一元的に行えます。
- 代理予約: 保護者がシステム操作に困難を抱える場合、施設側で代理予約を行うことも可能です。
7. 既存制度との違いを明確に
この制度は、他の制度とは目的や位置づけが異なります。特に「一時預かり事業」との違いを正しく理解しておくことが重要です。
| 項目 | こども誰でも通園制度 | 一時預かり事業 |
| 目的 | こどもの育ちの応援 | 保護者の必要性への対応(就労、リフレッシュ等) |
| 根拠 | 給付制度(令和8年度~) | 事業(補助事業) |
また、この制度はリトミックや英語教室のような「習い事」として提供することは不適切とされています。 あくまで子どもの主体性を尊重した関わりが求められます。
8. 人材確保と職員のメンタルヘルス
新たな事業の開始には、人材の確保が不可欠です。 また、多様な子どもや家庭と短時間で関わることは、保育者に通常保育とは異なる負担がかかる可能性があります。 定期的な面談を行うなど、職員のメンタルヘルスへの配慮も運営者の重要な責務です。
まとめ:変化をチャンスに、施設の未来を創造しよう
「こども誰でも通園制度」は、単に保育の受け皿を増やすだけの制度ではありません。地域の子育て支援の拠点として施設の価値を高め、経営の安定化を図り、保育者の専門性をさらに輝かせる可能性を秘めた制度です。もちろん、新しい制度を導入するにあたり、現場の先生たちに対しての丁寧な説明や、環境の整備は必要です。
ただ、今後の少子化が想定されている中で、保育園が定員割れで閉所に追い込まれている現状を考えると、変化の波を的確に捉え、貴園ならではの強みを活かすことで、この挑戦を大きなチャンスに変えることができるかもしれません。
まずは、所在地の自治体の担当窓口に相談し、地域の実情やニーズについて情報収集を始めることからスタートしてみてはいかがでしょうか。
保育のカタチでは引き続き、こども誰でも通園制度についての情報を提供していきます。
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/