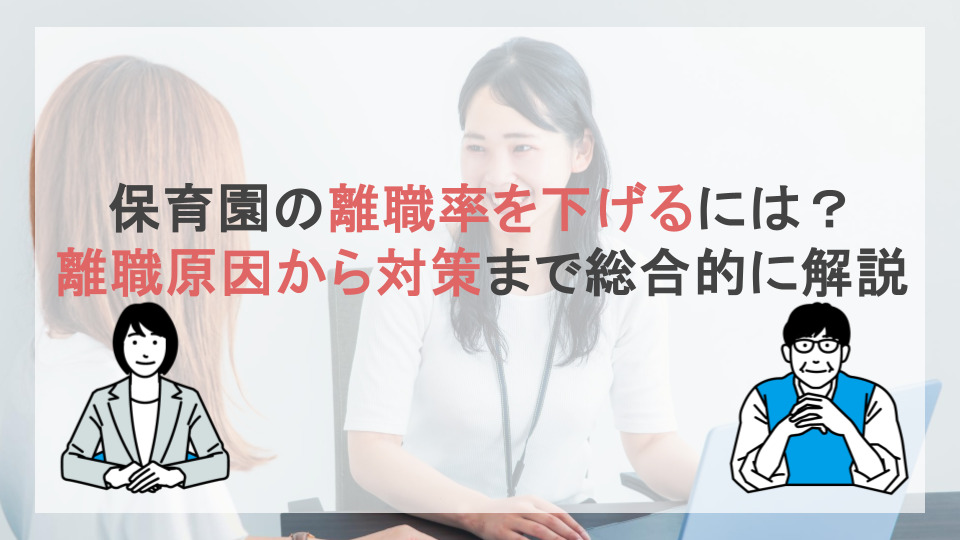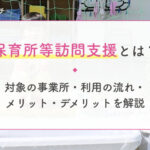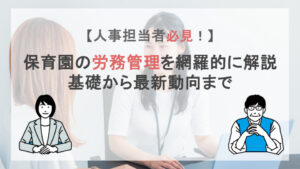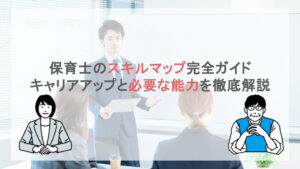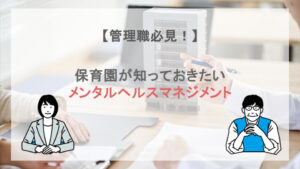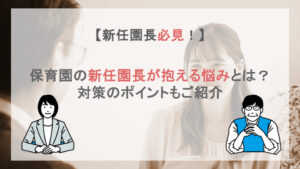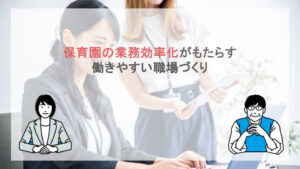保育士の離職率は他業種に比べて高い傾向があり、特に若手保育士の定着率が課題となっています。本記事では、保育業界を取り巻く離職率の現状や原因を整理し、離職率が高い保育園と低い保育園の特徴を比較しながら、離職率を下げるための具体策を総合的に解説していきます。保育士が安心して働ける環境づくりにお役立てください。
\支援実績1000社以上!園の全体最適を考えた採用をサポート!/
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/
保育士の離職率の現状を知ろう

まずは保育士の離職率がどのような状況にあるのか、他の常用労働者との比較や公立・私立の違い、そして若手保育士に焦点を当てて把握しましょう。
近年の統計によると、保育士の離職率は約10%前後とされており、一般常用労働者の平均離職率と比べてもやや高い水準が続いています。特に私立保育園では10%を超える傾向が強く、公立保育園とは待遇や雇用条件の差がみられることが背景にあります。
離職率は単に数字だけを見るのではなく、その裏にある現場の状況や人的資源の不足具合を把握することが重要です。保育士の離職が続けば、現場は人手不足から業務負担が増し、ますます離職に拍車がかかるという悪循環に陥りやすくなります。
こうした実情の把握は、保育園の運営者や管理者だけでなく、保育士自身にも必要です。離職率の把握を通して自園・自分が置かれている環境を正しく認識することで、具体的な対策を検討するきっかけになります。
保育業界全体の離職率と常用労働者との比較
保育士の離職率は、他の常用労働者が概ね1桁台後半で推移しているのに対し、10%前後とやや高い傾向が指摘されています。業務そのものの責任や心身の負担が大きいこと、残業や持ち帰り作業が発生しやすい現場構造などが要因に挙げられます。
こうした数値を踏まえると、「保育の現場で働くのは大変」というイメージが定着しやすく、採用面でも苦戦する保育園が少なくありません。人手確保が難しいほど、既存のスタッフへの負担がさらに重くなる点も大きな問題です。
公立・私立保育園での離職率の差
公立保育園の場合、地方自治体の運営や給与体系が安定しているケースが多く、福利厚生面でも優遇されることから離職率が比較的低いとされています。一方、私立保育園は公立に比べて給与や昇給制度にばらつきがあり、働く保育士も転職を考えやすくなる傾向があります。
短いスパンで保育士が入れ替わる職場では、子どもの発達を一貫して見守る体制が難しくなるだけでなく、保護者の信頼低下にもつながる恐れがあります。そこで私立保育園では、積極的に処遇改善や支援制度を整えるなどの労務管理が求められています。
若手保育士の離職率が高い背景
保育園全体の離職率の中でも、特に1〜3年目の若手保育士が早期に職場を離れる割合が高いと言われています。初めて現場に出る際の不安や、十分なフォロー体制が整わないまま大きな責任を負わされるなど、心理的ストレスが大きな離職要因です。
また、未経験や経験の浅い保育士ほど、洗練された業務手順や対人スキルを身に付ける時間が必要ですが、現場に余裕がないと十分なOJTも受けにくくなります。こうした状況を放置してしまうと若手のモチベーション低下を招き、離職率をさらに押し上げてしまいます。
保育士が離職を考える主な原因
保育士が離職を検討するに至る理由は多岐にわたります。代表的な原因を押さえて、対策のヒントを探ります。
離職を考える理由は一つではなく、給与や働き方のみならず人間関係や福利厚生など複合的な要因が絡み合っているケースが多いです。職場環境をしっかり整備していないと、保育士の疲労が蓄積しやすくなり、気がついたときには退職を選択してしまうという流れに陥りがちです。
特に保育業界では、保育の質と直結する業務内容の重さに比して報酬や処遇が必ずしも良好とは限りません。現場で何が起こっているのかを正しく理解し、それぞれの原因に対して具体的な改善策を検討することが重要です。
さらに、環境改善に注力しても保育士一人ひとりが置かれている事情は異なるため、制度導入だけでなく、個別のフォロー体制も必要となります。こうした複眼的なアプローチこそが離職率の低減に大きく寄与すると考えられます。
人間関係・職場環境の問題
保育士同士の連携不足や職場内のコミュニケーションが円滑でない場合、業務の引き継ぎミスやストレスが増大しやすくなります。さらに、保護者とのコミュニケーションでもトラブルが頻発すると、精神的な負担は大きくなるでしょう。
保育士はチームワークが重要な仕事ですが、意見を言いづらい風土や、先輩・後輩間の上下関係が厳しい職場環境が続けば、意欲ある保育士ほど退職を決断しやすくなります。
給与の低さや昇給制度への不満
保育士の給与水準は、責任の重さや子どもの命を預かるプレッシャーに比べて低めと感じる人が多いと言われています。加えて、昇給制度の基準が不明瞭だったり、経験を積んでも待遇があまり変わらなかったりすると、将来に希望が持ちづらくなるでしょう。
実際に、公立保育園と私立保育園の給与格差が離職原因として挙げられるケースも少なくありません。条件面の改善が遅れると、魅力的な職場への転職を考える保育士が増加するリスクがあります。
残業や持ち帰り仕事が増える長時間労働
保育の業務時間は子どもたちがいる日中が中心ですが、そのほかにも事務作業や制作物の準備、行事の計画など、意外と多岐にわたります。人手不足が続くと、一人あたりの負担も増加し、残業や持ち帰り仕事が常態化しがちです。
このような長時間労働が慢性化してしまうと、保育士の健康リスクだけでなく、保育の質を低下させる恐れがあるため、早期対策が不可欠です。
妊娠・出産に伴う退職の決断
産休・育休制度が整っていない、あるいは復職時にサポートを受けられないと感じる保育士は、妊娠や出産を機に退職を選択する傾向が強まります。現場が「妊娠=退職」という空気になってしまうと、制度の利用自体が難しくなり、キャリアを断念するケースも出てきます。
結果として、優秀な人材が家庭の事情で離職してしまい、保育園の人材不足に拍車がかかるという課題を引き起こすことがあります。制度面の充実と復帰後のフォローが、離職率抑制には欠かせません。
離職率が高い保育園の特徴とは
離職率が高まる要因を内包している保育園には、どのような共通点があるのでしょうか。具体的な特徴を押さえて改善に活かします。
離職率が高い保育園では、労働環境が整わないまま人材不足や業務過多の状態に陥っているケースが多く見られます。こうした環境では、スタッフが一時的に抜けるとすぐに大きな負担増につながり、さらに離職に拍車をかける悪循環が生まれます。
また、キャリアやスキルアップの道筋を示す制度や、スタッフ同士が話し合う機会がほとんどないと、現場の問題が放置されがちになります。限られたメンバーで回している職場ほど、内部コミュニケーションの質が離職率に大きく影響するのです。
このような状態が常態化すると、保育士一人ひとりのモチベーションが下がり、自ら働き方を見直して退職を検討し始めます。経営者やリーダー層が現状を放置していると、人材流出は止められません。
慢性的な保育士不足で業務負担が過重
離職率の高さと保育士不足は密接に関係します。人手が十分でないと、現場の保育士は一人あたりの作業量が増し、疲弊していきます。その結果、体力的にも精神的にも厳しくなり、転職を考える人が増えていくのです。
特に私立保育園は公立に比べて給与水準が低い場合も多く、人手不足を解消するための積極的な施策を打ち出せないケースが目立ちます。
キャリア支援や研修制度が不十分
保育士にとって、長期的なキャリアビジョンを描けるかどうかは大きなモチベーション要素です。しかし、一部の保育園では研修制度が整備されておらず、スキルアップの機会に恵まれないまま現場業務をこなすしかありません。
意欲があっても、どんな資格や研修を受けられるのか分からない職場では、将来を見通しづらくなり、人材の流出を招きやすいといえます。
コミュニケーションや情報共有の仕組みがない
保護者対応や子どもの生活習慣などには、スタッフ間での細やかな情報共有が欠かせません。しかし、仕組みがなく個人の善意や努力に頼るだけだと、ミスやトラブルが起きやすくなります。
コミュニケーション不足によって小さなストレスが積み重なると、現場に負の空気が蔓延し、離職への要因が増えるため、早めの対策が必要です。
\支援実績1000社以上!園の全体最適を考えた採用をサポート!/
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/
離職率が低い保育園の取り組み事例

離職率が低く、保育士が働きやすいと感じる保育園ではどのような取り組みが行われているのかを紹介します。
離職率が低い保育園は、給与体系やキャリア形成のみならず、日々の保育士同士のサポート体制が整っています。新人保育士だけでなく、子育て中の保育士も働き続けやすいように配慮したシフトや福利厚生が特徴的です。
また、職員の声を定期的に拾い上げ、改善につなげる姿勢が定着していることも重要なポイントといえます。上層部が現場の意見を真摯に受け止める文化であれば、保育士は自分の意見を遠慮なく発信しやすくなります。
こうした環境を継続的に維持するためには、管理職や園長のリーダーシップが欠かせません。組織全体で保育士をサポートする仕組みづくりが、安定的な人材確保にも直結していきます。
保育士の人数配置が手厚く、残業を抑制
適切な人数配置を確保することで、保育士一人あたりの業務負担を軽減します。残業が減り、持ち帰り仕事が少なくなることでプライベートの充実を図りやすくなり、労働環境が向上する好循環が生まれます。
子ども一人ひとりと向き合う時間も増やしやすいため、やりがいを感じやすくなり、長期的に働きたいという意欲に結びつくことが多いです。
福利厚生・職員同士のサポート体制
育児休暇や時短勤務などを充実させることで、出産や子育てと仕事を両立しやすくなります。また、仲間同士が自然に助け合う culturales があると、押し付け合いではなく協働で業務を進める雰囲気が保たれます。
こうした仕組みを整えることは企業努力も必要ですが、いずれは保育園の評判を高め、採用にもプラス効果をもたらします。
定期的なアンケートや面談で不満をすくい上げる
毎月や四半期ごとにアンケートを実施し、保育士の生の声を集める取り組みを行う保育園もあります。上司に直接言いづらいことも匿名なら伝えやすく、早めに不満を顕在化できるメリットがあります。
不満や課題が把握できれば、経営層やリーダーは具体的な改善策を打ち出しやすくなります。その結果、現場の信頼度も高まり、離職率の低減につながります。
保育士の離職率を下げるための具体的対策
現場で取り入れやすい具体例を中心に、保育士のモチベーション維持と職場定着を図るための対策を解説します。
保育士の離職率を下げるためには、給与や福利厚生だけに目を向けるのではなく、職場における働きやすさ全般を見直す必要があります。適切なマネジメント体制を構築し、保育士一人ひとりの負担を軽減する施策が欠かせません。
同時に、保育士自身がスキルアップしながら成長を感じ取れる仕組みも大切です。どんなに給与が良くても、自分の仕事にやりがいを感じられなければ長続きしません。組織としても、育成と支援を積極的に行う必要があります。
また、保育業界特有の課題として、女性が多い職場ならではのライフイベント(結婚・出産など)に伴う離職リスクがあります。これらを見据えて、制度面・環境面で柔軟に対応できる姿勢を整えることがポイントです。
給与・処遇の改善と制度の導入
給与アップや賞与の拡充はモチベーション維持に直結する重要な要素です。勤務年数や能力に応じて、どのように昇給していくのかを明確にし、保育士が将来像を描きやすい制度にすることで離職を防ぎやすくなります。
また、住宅手当や各種手当の充実など、経済的負担を軽減する取り組みを検討すれば、保育士の定着率向上にもつながります。
人間関係を円滑にするコミュニケーションづくり
保育の現場はチームプレイが大切ですが、意見交換の場や定期的なミーティングがないと、人間関係がぎこちなくなりやすいです。小さな行き違いが大きな軋轢に発展する前に、話し合いで解決できる土壌を整えましょう。
職場全体で研修を受けるなど、チームビルディングの取り組みを制度化すれば、保育士同士が協力しやすい特徴ある職場として魅力が高まります。
シフト管理や業務分担の見直しで負担を軽減
シフト調整にITツールを導入するなど、業務管理の仕組みを改善していくと、保育士の休日や休憩時間を十分に確保しやすくなります。持ち帰り仕事を減らす取り組みも欠かせません。
業務プロセスを明確化し、個々の保育士に割り当てる作業を可視化することで、人的リソースの偏りを抑えられます。これによりストレスを最小限にし、離職の大きな原因である長時間労働を改善できます。
産休・育休制度の充実と復職支援
結婚・出産などのライフイベントを経ても安心して働き続けられるよう、産休・育休制度の整備は非常に重要です。園全体でフォロー体制を構築し、妊娠中の負担軽減や復帰後の支援を行うことで、保育士が長くキャリアを続けやすくなります。
このような取り組みを積極的にアピールすることは、採用活動でも大きな強みになります。わかりやすく示すことで、まだ見ぬ優秀な人材も安心して応募しやすくなるでしょう。
研修やスキルアップ環境の整備
保育士が長く働くうえで、専門性を高める機会を提供することは欠かせません。内部研修や外部研修への参加を奨励し、資格取得を支援する制度を設けると、保育士のやりがいが向上し離職が減ることが期待できます。
キャリアパスを明確に示すことは、若手保育士の早期離職対策にも効果的です。達成目標があるとモチベーションが維持しやすく、経験を重ねるほどに充実感が得られます。
ICTシステム活用による離職防止策
保育業務の効率化や情報共有の改善に効果的なICTシステムの導入事例と、そのメリットを紹介します。
ICT活用により事務作業の効率化が図れれば、保育士は子どものケアにより多くの時間とエネルギーを注げるようになります。結果的に余裕をもって保育に臨めるため、業務負担の軽減やストレスの減少につながるのです。
また、システム導入は初期コストがかかる場合もありますが、中長期的には紙の保管や手作業によるミスを減らす効果が高いため、職場全体の生産性を底上げする選択肢となってきています。
保育士同士や保護者とのやりとりに関するコミュニケーション改革が進むと、離職の原因である人間関係の不満や業務過多が大きく緩和される点も見逃せません。
電子化による保育記録の効率化とミス軽減
ICT導入の代表例として、保育記録の電子化が挙げられます。アプリやクラウドソフトを用いることで、必要な情報をいつでもすぐに共有でき、手書きや複数転記のミスを削減できます。
特に行事やイベントが多い時期は、業務量が一時的に集中しがちです。電子化による効率化はそうしたピーク時の負担を和らげ、保育士が本来の業務に集中できる時間を保障します。
保護者との連携がスムーズになる情報共有ツール
連絡帳アプリやオンラインの掲示板などを活用すると、子どもの日々の様子や連絡事項を保護者へ迅速に伝えられます。保護者からの問い合わせにもスムーズに対応できるため、誤解やトラブルの防止に効果的です。
こうしたツールは、保育士の負担を減らすだけでなく、保護者も時間帯を問わず情報を受け取れる利便性があり、双方のコミュニケーションが良好になりやすいメリットがあります。
ICT導入で実現する職員同士の意識改革
ICTの活用には研修や習熟期間が必要ですが、導入をきっかけにチーム全体の働き方を見直す機会となります。情報共有の精度が高まれば、これまで属人的だった業務が組織的に進められるようになります。
ITに苦手意識を持つ保育士もいるため、導入初期は丁寧なサポートが欠かせません。しかし、慣れてしまえば使い勝手の良さを実感し、日々の業務効率を大幅に高める手段として定着しやすくなります。
保育士が安心して働ける職場づくりのポイント
保育士が長く安心して働き続けるためには、職場全体でどのような心がけが必要かポイントを整理します。
第一に、保育士が忙しさに追われて声を上げられない状態を作らないようにすることが大切です。アンケートや面談などを通じて定期的に本音を聞く機会を設け、改善に結びつけていきましょう。
また、役割分担やシフトなどで現場をコントロールしやすい仕組みを確立しておくのもポイントです。負担が集中しがちな業務を洗い出し、皆で協力し合うという意識を共有できれば、離職を生まない風通しの良い環境が育まれます。
さらに、育成やスキルアップ、ライフイベントとの両立支援に力を入れれば、保育士がキャリアを継続しやすくなります。職員全員が安心できる職場を目指すことが、離職率を下げる最も効果的な方法の一つといえるでしょう。
まとめ|離職率を下げるには職場環境の改善が鍵

最後に、離職率を下げるために最も重要な職場環境の改善施策について総括します。
保育士の離職率を下げるには、給与や福利厚生といった基本的な条件の整備はもちろん、人間関係などソフト面のケアも必要です。ICTシステムによる効率化や情報共有の円滑化も、現場の負担を減らし、離職率低減に貢献します。
また、妊娠・出産といったライフイベントへのサポートや研修制度の充実など、多様な働き方を継続できる柔軟性が欠かせません。これらの取り組みによって作られる「保育士が安心して働ける職場」が、結果的に高い保育の質につながります。
経営者や園長など指導的立場にある人は、現場の声をしっかり拾い上げ、改善策を着実に実行していくリーダーシップが求められます。保育士が長く働き続けられる環境づくりを意識し続けることが、離職率低下の最大のカギといえるでしょう。
\支援実績1000社以上!園の全体最適を考えた採用をサポート!/
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/