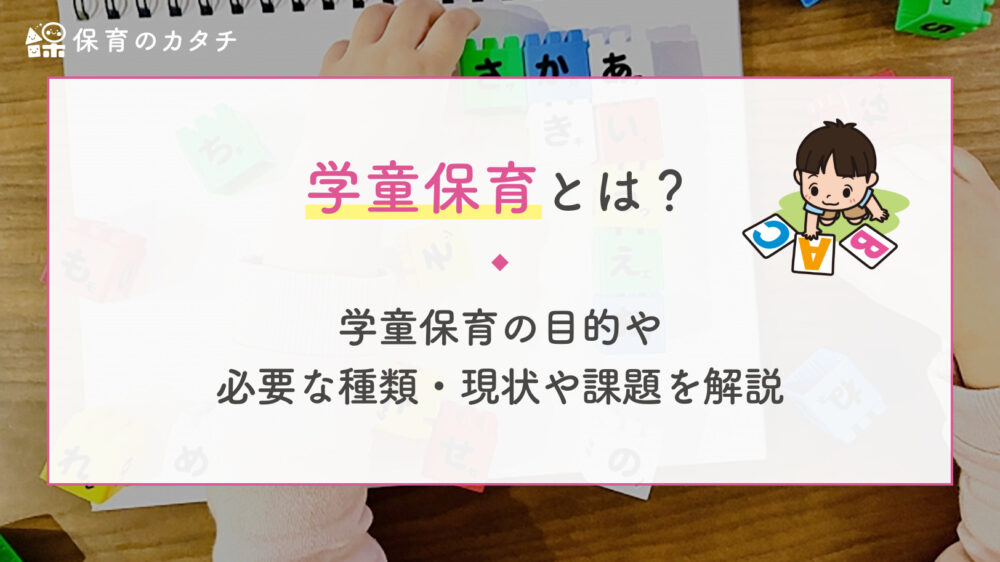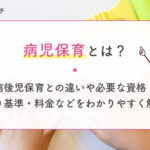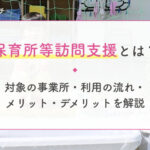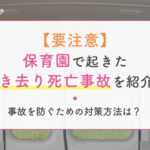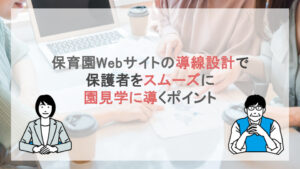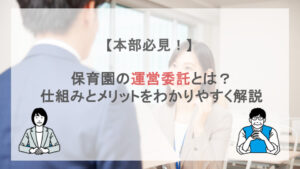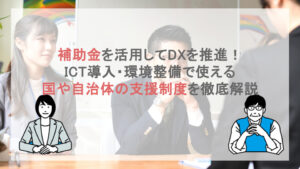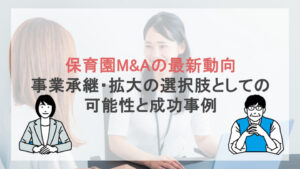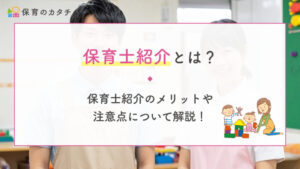学童保育は、放課後など「児童が1人にならないため」の子育て支援の一環です。市町村で実施されているイメージが強い学童保育ですが、一般企業なども運営に進出しています。
この記事では、学童保育の種類や特徴・学童サービスの運営元・今後の課題などについて詳しく解説します。
\支援実績1000社以上!園の全体最適を考えた採用をサポート!/
保育士の採用をするなら保育のカタチがおすすめ
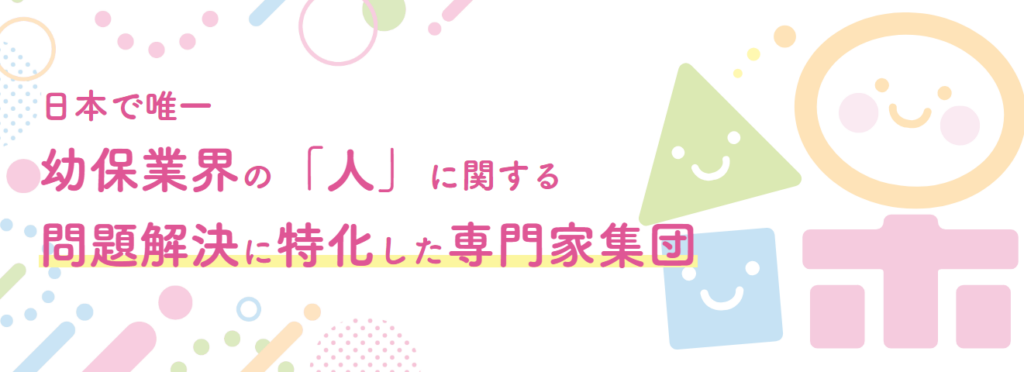
引用元:保育のカタチ
保育士の採用をするなら保育のカタチがおすすめです。
保育のカタチは日本で唯一、幼保業界の「人」に関する問題解決に特化した専門家集団です。採用から社員教育、それらの仕組み化まで幅広く取り組んでおり、人手不足の保育業界の中で、幼保施設にとって最善のパートナーが見つかるようなお手伝いをしています。
採用がうまくいかず悩んでいる方はぜひ一度保育のカタチにご相談ください。
| 住所 | 〒550-0004大阪府大阪市西区靱本町1-7-22 SKKビル201 |
| 許可番号 | 厚生労働大臣許可番号有料職業紹介事業:27-ユ-303764 労働者派遣事業:派27-304996 |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員、パート |
| 求人施設 | 保育園、幼稚園、認定こども園、病児保育、事業内保育、学童保育、託児所など |
| 対応エリア | 全国 |
| 連絡手段 | 電話番号:06-6210-5326 LINE |
\支援実績1000社以上!園の全体最適を考えた採用をサポート!/
学童保育とは?

子育てにおける国の事業である学童保育は、市町村が主体となり学童保育事業として運営しています。正式には「放課後児童健全育成事業」と呼ばれ、厚生労働省の管轄のもと、児童の健全な育成を図るために実施している事業です。
1940年代後半、民間保育園から始まったといわれる学童保育は、世の中におけるニーズの高まりにより1997年に法制化されました。
学童保育の目的
学童保育の目的は、保護者が働いている児童を対象に、適切な遊び場や生活の場を提供することです。
学童保育の要件は、以下の3つです。
- 生活の場として存在
- 安心して過ごせる専用施設
- 保護者の代わりとなる指導員の配置
学童保育は、自宅に次ぐ子どもの居場所を提供するだけでなく、指導員が「保護者の代わりに安心して頼れる身近な大人」であることも求められています。
学童保育の活動内容
学童保育では、子どもが自宅で過ごすときと同じように、メリハリのある生活を提供します。
一般的な学童保育の活動内容には、以下のような取り組みが行われています。
- 自主学習や宿題時間の提供
- おやつの提供
- 集団や個別の遊び場の提供
近年、保護者のニーズにより民間の学童保育では、夕食を提供したり習い事を取り入れたりするケースもみられるようになりました。
学童保育が広まった背景

「留守家庭児童」や「放課後児童クラブ」と呼ばれることもある学童保育は、2000年代に国が「仕事と子育ての両立」を掲げたことで急激に増加しました。
自治体の運営による学童保育は増えました。ただ、共働き世帯の増加とともに学童待機児童は増え、近年では民間企業が学童保育事業に進出し、より学童保育の拡大が注目されるようになりました。
また、核家族化や近所づきあいの少なさや、近くにいる大人が子どもを見守る風習が薄れていったことも、学童保育が広まった要因だと考えられます。
学童保育の種類

学童保育は大きく分けると、放課後児童クラブ・民間学童保育・放課後こども教室の3つの種類に分類されます。
ここからは、学童保育の種類を詳しく解説します。
放課後児童クラブ
放課後児童クラブは、厚生労働省の管轄下にある一般的な学童保育で、自治体が運営しています。保護者の就労が利用条件となっており、原則小学校3年生までの児童が対象です。
| 放課後児童クラブの特徴 | 概要 |
|---|---|
| 親の就労状況 | 自治体ごとに就労時間などの要件あり (介護や疾病の場合も利用可能) |
| 運営時間 | 平日:下校から18時頃まで 土曜日:9時~17時頃まで |
| 学童の特色 | ・自由時間を多く設けている ・学校や児童館の体育館を利用できる場合がある ・おやつを提供 ・自治体の審査により利用可否が決まる ・延長保育はないケースが多い |
| 申込受付方法 | 自治体の窓口 |
自治体が直接運営する場合は「公立公営」、民間に委託して運営する場合は「公立民営」と呼ばれ、施設の老朽化などにより公立民営の学童は増加傾向にあります。
民間学童保育
民間学童保育は、厚生労働省管轄外の学童保育で、一般の企業や学校法人が運営しています。保護者に就業などの条件はなく、子どもの年齢も問わないケースが多い傾向にあります。
| 民間学童保育の特徴 | 概要 |
|---|---|
| 親の就労状況 | 要件なし |
| 運営時間 | 平日:下校から20時頃まで 土曜日:9時~20時頃まで |
| 学童の特色 | ・子どもが好きなプログラムがある ・学習時間を設けている ・夕食を提供 ・24時間利用できる場合もある |
| 申込受付方法 | 民間企業や学校法人など運営窓口 |
プログラムには、スポーツや塾、ダンスやプログラミングなど、子どもが興味を持ちそうな習い事がある場合が多く、ニーズに合わせて施設独自のプログラムを実施しています。
なお、一般的な学童とは異なり、民間学童保育の運営には自治体からの助成金がありません。
放課後こども教室
放課後こども教室は、文部科学省の管轄で、小学校や児童館などの教室を使って自治体が運営している学童保育です。
自治体ごとに運営されており、公立小学校に通う全児童が無料で利用できます。
| 放課後こども教室の特徴 | 概要 |
|---|---|
| 親の就労状況 | 要件なし |
| 運営時間 | 平日:16~17時頃まで |
| 学童の特色 | ・自由時間が多い ・イベントなどを実施 ・平日のみ運営 ・外部講師を呼び学習支援 ・自治体ごとに名称が異なる |
| 申込受付方法 | 自治体の窓口 |
自治体が運営することが多い放課後こども教室ですが、NPO法人や一般企業に委託し、独自の運営をおこなうケースも増えてきています。
\支援実績1000社以上!園の全体最適を考えた採用をサポート!/
学童保育にかかる料金

学童保育の種類によって、月々の料金設定が異なります。
- 放課後児童クラブ(学童保育):4,000円~10,000円
- 民間学童保育:20,000円~100,000円
- 放課後子ども教室:無料
自治体が運営する学童保育では、子育て支援が目的のため、保護者の所得を考慮するなど低額に設定されています。一方、民間学童保育では、保護者や子どものニーズを満たすための事業として運営されているため、月々の利用回数や習い事の別途費用によって異なり、高額になりがちです。なお、入学金が必要となるケースもあります。
放課後子ども教室は無料で運営されていますが、イベント開催における工作費用を別途徴収しているケースもあります。
学童保育に必要な資格

学童保育の運営では「放課後児童支援員」の資格保有者を2名以上在籍させる必要があります。学童保育と保育における資格の違いには、以下のようなものがあります。
| 資格の違い | 放課後児童支援員 | 保育士 |
|---|---|---|
| 資格 | 認定資格 | 国家資格 |
| 対象とする児童年齢 | 小学生 | 0歳~就学前 |
| 必要な資格 | 不要 | 保育士資格 |
学童保育の運営において、独自のプログラムを実施するときには、それぞれに適した資格保持者がいると、施設としての信頼も高くなることでしょう。
保育士配置基準は2024年に見直されました。改訂内容について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
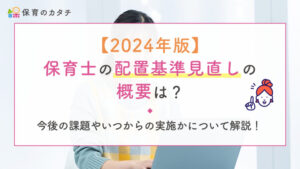
学童保育の現状

学童保育の施設は増加傾向ではあるものの、需要と供給が間に合わず、学童待機児童は確実に増えているのです。また、自治体が運営する児童保育では、保護者のニーズに合致しないという不満の声も高まっています。
働き方が多様化した現代では「学童保育があるから良い」ではなく、「なぜ学童保育が必要なのか」という原点に立ち戻った考え方で運営することが求められています。
学童保育の課題

学童保育において、解決を急ぐ課題は「学童待機児童を減らすこと」です。定員オーバーや待機児童の問題により、子どもの安全面が損なわれてしまう可能性があります。
身近な大人と接しながら、第二の家庭として過ごす学童保育は、利用できない児童が増えるばかりか、利用目的に合致していないケースも多々あります。こども家庭庁によると、令和5年5月1日時点において、放課後児童クラブを利用できなかった児童数は1万6,276人とのことでした。
前年に比べ1,096人も増加しており、少子化を防ぐ意味でも、この数を氷山の一角と捉え、待機児童における課題解決が急がれています。
参考:こども家庭庁「令和5年 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況」
まとめ

学童保育は、仕事と子育ての両立支援として生まれ、現在に至りますが、待機児童は年々数を増しています。自治体による学童保育は増えているものの、子育てのニーズを満たしきれていない現状も浮き彫りになりつつあるのです。
学童保育の運営には、民間企業などの進出も多くなっています。一方、民間の学童保育には、自治体では実現できない「ニーズを捉えた独自プログラム」が欠かせないと考えられるでしょう。
\支援実績1000社以上!園の全体最適を考えた採用をサポート!/
保育士の採用をするなら保育のカタチがおすすめ
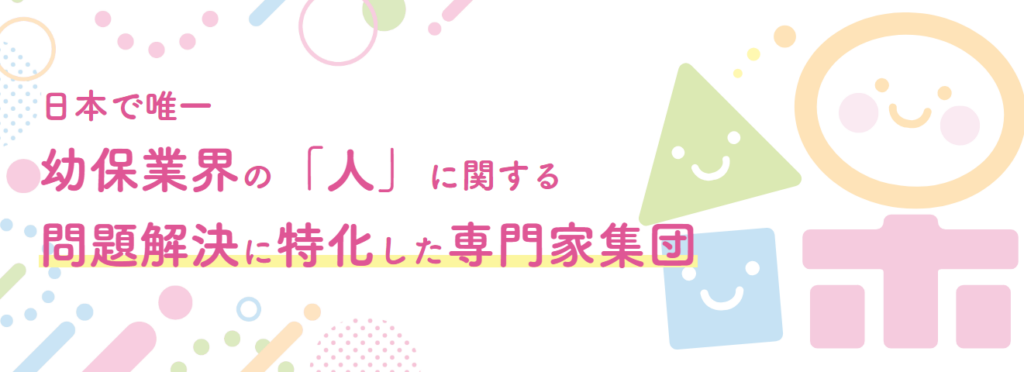
引用元:保育のカタチ
保育士の採用をするなら保育のカタチがおすすめです。
保育のカタチは日本で唯一、幼保業界の「人」に関する問題解決に特化した専門家集団です。採用から社員教育、それらの仕組み化まで幅広く取り組んでおり、人手不足の保育業界の中で、幼保施設にとって最善のパートナーが見つかるようなお手伝いをしています。
採用がうまくいかず悩んでいる方はぜひ一度保育のカタチにご相談ください。
| 住所 | 〒550-0004大阪府大阪市西区靱本町1-7-22 SKKビル201 |
| 許可番号 | 厚生労働大臣許可番号有料職業紹介事業:27-ユ-303764 労働者派遣事業:派27-304996 |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員、パート |
| 求人施設 | 保育園、幼稚園、認定こども園、病児保育、事業内保育、学童保育、託児所など |
| 対応エリア | 全国 |
| 連絡手段 | 電話番号:06-6210-5326 LINE |
\支援実績1000社以上!園の全体最適を考えた採用をサポート!/