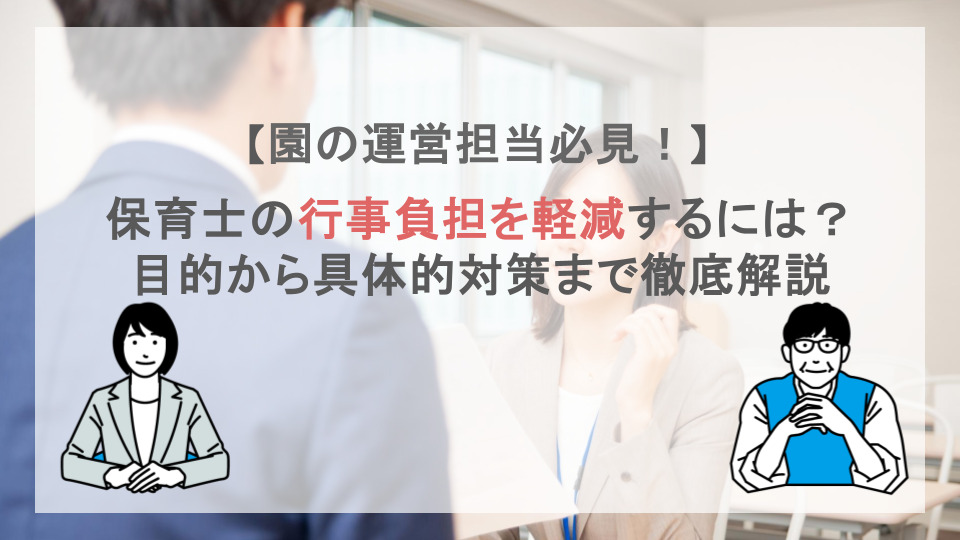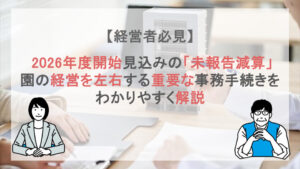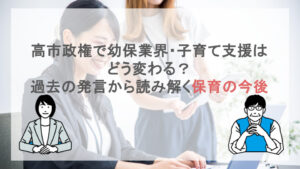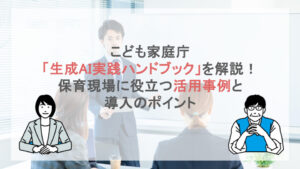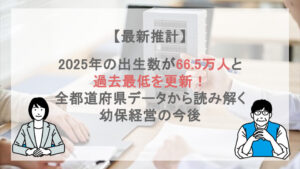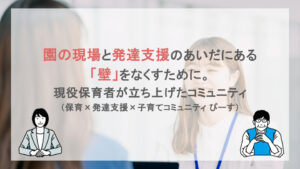保育園で行われる行事は、子どもたちにとって貴重な学びや成長の機会ですが、その準備や運営を担う保育士にとっては大きな負担となる場合があります。イベントの回数が増えるほど、残業や休日出勤に追われることも少なくありません。
それでも行事が果たす役割は重要であり、まったく削減してしまうのでは子どもたちの成長に影響が出る可能性があります。そこで、本来の目的を見直しながら、保育士の業務を効率化する方法を検討することが大切です。
本記事では行事負担が増える背景から、具体的な効率化のポイント、そして保育士の働き方の見直しや転職の視点までを詳しく解説します。行事に追われず、より良い保育が実現できる方法を一緒に考えていきましょう。
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/
行事負担が増える背景と主な要因

保育園の行事が増えることには、子どもや保護者の期待に応えるだけでなく、文化的な行事を多く取り入れたいという思いなど、さまざまな理由があります。そうした背景を理解することで、負担を軽減する糸口が見えてきます。
最近の保育園では年間を通して20回以上の行事を実施する園もあり、その準備や運営のために保育士が長時間労働を強いられることがあります。行事を充実させたいという思いが強いほど、企画や準備が増えがちです。
一方で、現場の保育士は慢性的な人手不足に加え、当日のアクシデント対応などで負担が大きくなりがちです。こうした状況を放置してしまうと、保育士の心身への負担が増え、結果的に質の高い保育が損なわれる恐れもあります。
まずはなぜこれほど多くの行事を行い、それがどのように保育士の負担へと繋がっているのかを把握し、対策を講じることが重要です。
保育園行事が多岐にわたる理由
日本の伝統文化を大切にしようとすれば、節分やひなまつり、七夕などの行事を取り入れたくなります。さらに運動会や発表会、遠足などを合わせると、年間の行事回数は自然と増加します。
特に季節行事や地域独自の行事が多い園では、同じ時期に複数のイベントが集中することがあります。そうした場合、準備期間や片付けのタイミングが重なり、保育士が十分に休息を取ることが難しくなるのです。
行事が多くなる背景には、保護者や地域からの期待も含まれています。伝統を伝えるためにも大切なイベントですが、過度に増やすことで保育士だけが大きな負担を抱えているという状況も見受けられます。
慢性的な保育士不足による負担増
全国的な保育士不足の影響で、行事の準備や運営を分担できるスタッフが限られている園は少なくありません。そのため、一部の保育士のみに負荷が集中しやすい現状があります。
保育士同士が協力したくても、日々の保育業務だけで手いっぱいというケースもあり、行事準備に割く時間を捻出するのが難しいという声もよく聞かれます。
結果として残業や休日の作業が増えるため、体力的にも精神的にも疲れがたまりやすくなります。この悪循環が進行すると離職率が上がり、さらなる人員不足を招いてしまう恐れがあります。
保育園行事の目的と本来のねらい
行事は保育現場にとって欠かせない行事が多いのも事実です。本来の目的をしっかり理解し、意味のあるイベントとして活用することが大切になります。
保育園の行事は、子どもたちに多彩な体験を提供する大切な機会です。同時に、保護者と直接交流する場としても機能しており、信頼関係の形成にもつながります。
では、そんな行事にはどのようなねらいがあるのでしょうか。ここでは、主に子どもや保護者への役割といった視点から掘り下げてみます。
本来のねらいを見失わないようにすることが、行事の規模や回数を適切に見直すきっかけにもなるはずです。
子どもにとっての意義
運動会や夏祭り、発表会などの行事は、子どもにとって新しい挑戦の場です。友だちと協力して何かを成し遂げる過程で社会性や協調性を育むことができます。
行事の準備や練習を通じて、“やればできる”という自己肯定感を育むきっかけにもなります。また、日本の文化や季節感を肌で感じる機会としても有意義です。
行事は子どもの成長をサポートする大切な場でもあるため、保育士としては十分に活かしたい反面、過度な準備や長時間の練習が大きな負担になる可能性もあるでしょう。
保護者とのコミュニケーションを深める
行事は保護者と一緒に子どもの成長を感じられる貴重な場です。運動会や参観日などを通じて、普段は見られない子どもの姿を知ることができます。
また、保育士と保護者が直接対話できる機会が増えるため、子育てに関する悩みを相談しやすくなり、信頼関係の構築にもつながります。
一方で、行事が多くなりすぎると保護者自身も参加の負担が増える恐れがあります。双方のメリットをしっかりと考え、適切な頻度や内容を検討すると良いでしょう。
行事見直しが負担軽減の第一歩

負担を大きくしないためには、行事を例年通りにすべて実施するのではなく、内容や目的を再確認して必要不可欠なイベントを明確にすることが大切です。
行事を減らすことへの抵抗感はあるかもしれません。しかし、すべての行事を同じように力を入れて準備するのは、保育士に大きな負担を強いる結果になります。
まずは行事ごとに目的を整理し、それが子どもたちの成長や保護者との信頼関係にどの程度寄与しているかを考えてみましょう。
優先度の低い行事を削減しても、必要な行事に集中して質を高めることで、より満足度の高いイベント運営ができる場合もあります。
必要不可欠な行事の優先度を決める
すべての行事が重要に見えるかもしれませんが、それぞれの行事が持つ目的を整理して“必須”か“あれば良い”かを分けることが大切です。
たとえば、子どもの発表の場として欠かせない行事に優先的に時間と労力をかけ、伝統行事は簡易的な形でも意義を伝えられれば十分というケースもあります。
こうした優先度付けを職員間で共有しておくと、新しく着任した保育士やサポートに入るアルバイトなどにもわかりやすく、準備のスムーズ化につながります。
行事スケジュールを逆算して立案する
年間の行事計画を早めに立てることで、準備期間をどの程度確保すべきかが明確になり、工程に余裕を持てるようになります。
特に複数の行事が近接して行われる場合、どのタイミングで準備を進めるかを逆算し、タスクを分散しておくことが肝心です。
はじめから“いつまでに何を終えるか”を明確にしておくと、個々の保育士が動きやすくなるだけでなく、全体のスケジュール管理も容易になるでしょう。
保育士の行事準備を効率化するポイント
行事を削減するだけでなく、準備自体を効率化する工夫も大切です。ここでは、作り物の進め方やスタッフ同士の連携などの具体的な方法を見ていきましょう。
保育士の行事負担を軽減するためには、既存のやり方を見直して無理のない範囲で準備を進められる仕組みづくりが求められます。
実際に行事ごとの担当を明確にし、小さなタスクに分解して進めることで、互いにフォローし合える体制を整えやすくなります。
また、子どもが参加できる作業は積極的に取り入れることで、子どもが行事への意欲を持つと同時に、保育士の負担を軽くする効果も期待できます。
作り物は子どもと一緒に行い協力体制を築く
行事の飾り付けや小道具づくりなど、手作りが必要な場面では子どもと一緒に制作したほうが保育の時間としても有意義です。
子どもにとっても楽しみながら作業することで創造性が育まれますし、保育士だけで一から作るよりも時間と労力を節約できます。
子どもの作品を行事に取り入れると、達成感を得て行事に積極的に参加してくれるようになるという効果も望めます。
職員間の情報共有と役割分担
行事の運営をスムーズにするには、定期的なミーティングを設けてタスクの進捗を確認し合うことが重要です。オンラインツールを活用することで、離れた場所からも情報共有が可能になります。
一人に作業が偏らないよう、担当を細かく分けておくと互いにサポートしやすくなります。定期的なやりとりの場を設定しておくと、問題点の早期発見や調整が行いやすいでしょう。
保育士全員が同じゴールを共有できるよう、事前に行事の目的やおおまかな流れを共有しておくことも効率化に欠かせないポイントです。
ICTシステムや既製品を活用する
シフト管理や予定表はアナログで行う園もまだ多いですが、可能であればICT化してスケジュールを簡単に共有できるようにすると便利です。
衣装や飾り付けには既製品をうまく活用することもおすすめです。手作りにこだわりすぎず、大切な部分だけ手作りにするなどのバランスを考えましょう。
時間と労力を節約できる部分はなるべく省力化し、そのぶん子どもたちの指導やコミュニケーションに注力できる環境を作ることが大切です。
まとめ
行事は子どもたちの成長や保護者との信頼関係づくりに重要ですが、その負担が大きすぎると保育士の離職や保育環境の悪化を招く可能性があります。適切な見直しと効率化を行うことで、双方にとってより良い行事運営を目指しましょう。
まずは行事が多くなる背景を理解し、本当に必要な行事を精査することから始めると良いでしょう。子どもにとっての意味や保護者との関係構築に役立つ行事を模索し、必要以上に準備に時間がかかるものは簡略化を検討するのがポイントです。
また、仕事の効率化を図ることで、保育士の業務負担を減らすことができます。具体的には、ICT化や服装・飾りの既製品活用、そして職員同士の情報共有や役割分担などが挙げられるでしょう。
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/