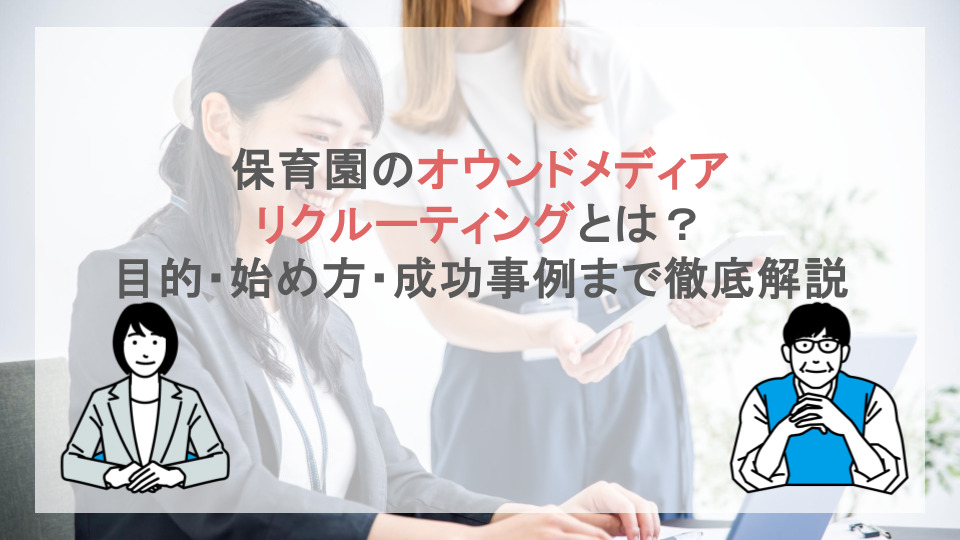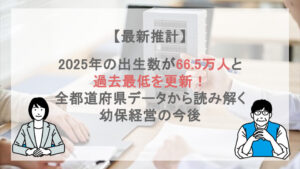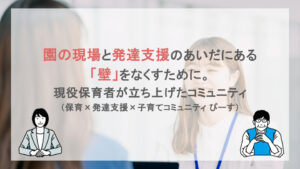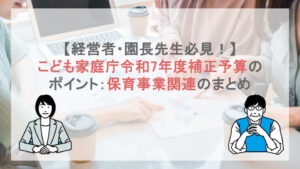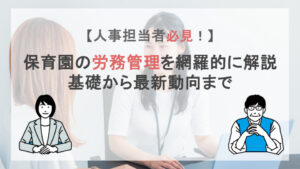近年、保育園の採用活動では優秀な人材の確保がますます難しくなってきています。従来の求人サイトや人材紹介だけでは魅力を十分に伝えきれないことも多く、新たな手法が求められています。
そこで注目されているのが、自社が運営するメディアを活かして採用活動を行うオウンドメディアリクルーティングです。本記事では、保育園の採用にも活用しやすいオウンドメディアリクルーティングの概要や始め方、実際の成功事例までを詳しく解説します。
\自園と相性のよい人材が長く働いてくれる、保育のカタチの採用支援/
オウンドメディアリクルーティングの基本概要

まずは、オウンドメディアリクルーティングがどのような手法であるか、その定義や特徴を押さえておきましょう。
オウンドメディアリクルーティングとは、自社が所有するサイトやブログ、SNSといったメディアを拠点に情報発信を行い、求職者を惹きつける採用手法です。求人サイトなどの外部プラットフォームに依存しにくいぶん、園の理念や環境をしっかりアピールできる点が特徴的です。特に保育園の場合、教育方針や子どもの笑顔に繋がる日常のストーリーを発信することで、求職者の関心をより深く引き寄せる効果が期待できます。
保育園にとっては、長期的に安定して優秀な人材を確保することが非常に重要です。オウンドメディアを通じて園の魅力や理念を伝えておくことで、候補者に対して継続的に情報発信ができ、採用のための“資産”を育てることができます。いざ採用が必要になったときに、一気にメディアを活用・拡散しやすいのも利点です。
また、保育業界は職場の雰囲気やチームワークが非常に大切な要素です。自社運営のメディアであれば、職員同士の協力や園内イベントの様子などをリアルかつ自由に表現できるため、求人サイトや人材紹介にはない強いアピール材料となります。求める人材像に合った人材の応募を増やすためにも、まずはオウンドメディアの全体像を理解して運用を始めましょう。
オウンドメディアリクルーティングの定義と特徴
オウンドメディアリクルーティングは、企業や保育園が自ら運営するブログやSNS、ウェブサイト上で採用情報や職場の魅力を発信する取り組みを指します。一般的な求人サイトよりも掲載内容に制限が少なく、園の文化や雰囲気を多角的にアピールできる自由度の高さが大きな特徴です。継続的にコンテンツを蓄積することでブランディング効果が高まり、長期的に採用活動の資産となる点でも注目を集めています。
求人サイト・人材紹介との使い分け
求人サイトや人材紹介サービスは短期的に募集したいときや、多くの候補者へ効率的にリーチしたいときに役立ちます。一方で、保育園が大切にしている教育方針や職員同士のコミュニケーションなどは、外部プラットフォームだけでは十分に伝わりきりません。オウンドメディアを使うことで、園の理念や日々の保育現場の様子を詳しく紹介し、長期的な採用プールを形成することが可能になります。
ダイレクトリクルーティング・リファラル採用との違い
ダイレクトリクルーティングは人材データベースから求職者へ直接アプローチする方法で、すぐに成果を求める場面で効果を発揮します。リファラル採用は、既存スタッフの紹介により信頼度の高い候補者を集めることができます。ただし、オウンドメディアリクルーティングは潜在層を含めた広範な求職者に向け、園の魅力を受動的に届けられる手法です。これにより、まだ転職意欲がはっきりしていない層にも興味を持ってもらえるメリットがあります。
オウンドメディアが担う採用ブランディングの役割
採用ブランディングの要は、保育園の理念や方針、働く人々の想いを求職者にしっかり伝えることです。オウンドメディアでは、園での日常風景や職員の声などを積極的に発信することで、保育園の世界観を深く体感してもらえます。結果的に、入職後のミスマッチが減少し、長く勤めてくれる人材を集めやすくなるという効果が得られるのです。
オウンドメディアリクルーティングが注目される理由
なぜいま、保育園の採用手法としてオウンドメディアリクルーティングに関心が寄せられているのか、その背景を整理してみましょう。
少子高齢化や労働人口の減少に伴い、保育士を含めた優秀な人材の採用は年々難しさを増しています。これまで利用されてきた求人サイトや人材紹介だけでは、全ての保育園が求める条件に合った人材を集めきれないケースも多くなっているのです。こうした採用市場の厳しさが、新しい手法への需要を高める大きな要因となっています。
さらに、求職者が仕事を探す際の情報収集方法が多様化し、インターネット上で園の評判や職場環境を深く調べる人が増えてきました。SNSや各種口コミサイトをチェックすることで、園の内部情報を得ようとする求職者も多く、情報発信の方法を工夫することが欠かせません。オウンドメディアは、こうした情報ニーズに応えられる強みがあるのです。
また、人々の価値観が変わり、仕事を選ぶときに給与や通勤時間だけでなく、やりがいや社会貢献の度合い、職場の人間関係など多面的に判断する人が増えています。保育園の温かい雰囲気や社会的意義を訴求することができれば、他業種で保育に興味を持つ潜在層にもアプローチできるでしょう。
多様化する働き方と採用の難易度上昇
保育士には女性だけでなく、男性保育士の需要も高まるなど働き方の選択肢が拡大しています。同時に、求人倍率の高さや他園との競合などの影響で、欲しい人材を短期間で確保することが難しくなっています。オウンドメディアを利用した継続的な情報発信が、長期的な採用戦略を支える重要な手段として位置づけられています。
デジタル化による情報収集の容易性
スマートフォンやSNSの普及によって、求職者は勤め先候補の雰囲気や実態を簡単に確認できるようになりました。企業や園側もこれを活かさない手はなく、オウンドメディアで写真や動画、テキストを使って多面的に情報を提供することが必要です。前もって生きた情報を確認できることで、応募者側の不安や疑問を軽減する効果が期待できます。
求職者の企業選びにおける価値観の変化
近年、仕事の目的や職場環境を重視する人が増え、保育という社会的意義の高い職場に魅力を感じる人が多くなりました。しかし、その良さを伝える場が有限だと十分に理解してもらうのは難しいでしょう。オウンドメディアを通じて、教育理念やチームワーク、子どもたちの成長をサポートするやりがいなどを具体的に発信することで、共感を生むことができます。
オウンドメディアリクルーティングのメリット・デメリット

どのような採用手法にもメリットとデメリットが存在します。相反する面を理解してこそ、効果的な活用が可能になります。
オウンドメディアリクルーティングにより得られる恩恵は、単に応募数の増加だけではありません。園の魅力をじっくりと発信できることで、入職後のミスマッチを減らし、結果的に定着率を高められる可能性が高まります。さらに、自作のメディアを継続して運営することで、宣伝費用を抑えながらも認知度向上を図れるのも魅力です。
一方で、オウンドメディアを立ち上げるための準備や、継続的な更新に手間やコストがかかるのは避けられません。また成果がすぐに出るものではないため、短期的な採用に期待しすぎると効果を感じづらいでしょう。ただ、保育園の温かみや特色を長期的に発信していく姿勢があるならば、投資に見合うリターンを得られる可能性は十分にあります。
デメリットの解消には社内(園内)での明確な役割分担と、コンテンツマーケティングの基本的な知識が求められます。運営を円滑にするためにも、事前に運用体制を整え、各スタッフが自主的に情報を集めやすいフローを作っておくことがポイントです。
メリット1:企業理解促進による採用ミスマッチの減少
オウンドメディアでは募集要項だけでなく、園の価値観や職員の声など深い情報を伝えられるため、求職者は入職後の具体的なイメージが描きやすくなります。これにより、実際に勤務を始めたときの「思っていた職場と違う」というギャップが減ります。結果的に、保育園と求職者の両者にとって納得感のある採用が可能になります。
メリット2:認知度向上とブランド構築
オウンドメディアを通じて保育園の理念や活動内容を継続的に発信することで、検索エンジンでの露出も増え、園名の認知が高まります。長期にわたってコンテンツを積み上げれば、職員や保護者、地域社会からの信頼を得やすくなり、ブランディングを強化できます。地道に情報発信を続けることが、最終的には大きな差異化要素につながるのです。
メリット3:長期的に見た採用コストの削減効果
最初はサイト構築などへの投資やスタッフの工数がかかりますが、一度しっかりとしたメディア基盤ができれば、求人広告を出し続けるよりも結果的に費用を抑えられます。蓄積されたコンテンツが資産化し、継続的に求職者を呼び込み続けるため、長期的には高い費用対効果を期待できるのがメリットです。
デメリット1:成果が出るまでに時間的コストがかかる
オウンドメディアは記事やSNSなどでの露出を積み重ねることで徐々に成果を積み上げていく手法です。短期間ですぐに採用につながるわけではなく、コンテンツのクオリティや更新頻度、SEO対策の度合いによって効果は変動します。即効性よりも将来の安定的な採用力強化を重視する場合に向いていると言えます。
デメリット2:専門知識と社内連携が求められる
メディアを運営するには、制作スキルやデジタルマーケティングの基礎知識が必要です。スタッフや外部専門家を巻き込みながら進行するため、スケジュール調整や権限管理も欠かせません。保育園では、現場業務との両立もしなければならないため、効率よく作業を進めるしくみ作りが大切です。
デメリット3:コンテンツ更新の手間と運用費用
オウンドメディアで情報を鮮度高く保つためには、写真や動画、記事などを定期的に更新する必要があります。特に保育園の場合、行事の様子やスタッフのインタビューなど長期的に発信できるネタは多い反面、その撮影や編集に手間がかかるのは事実です。こうしたコストを見越して、無理のない運用計画を立てることが大切になります。
オウンドメディアリクルーティングの始め方と運用プロセス

実際にメディアを立ち上げ、ともに採用活動を進める手順を整理しておきましょう。
オウンドメディアリクルーティングを成功させるには、準備段階で採用ターゲットを明確にし、どのような人にどんな情報を届けたいかを定義することが欠かせません。具体的にペルソナを設計し、記事や動画の内容を決めていくプロセスが基本になります。保育園ならではの視点として、保育理念や子どもとの関わり方など、業界特有の価値をしっかりと盛り込むと良いでしょう。
また、メディア構築やデザインはブログやSNSから始める場合もあれば、本格的なCMSを導入する場合もあります。小さくスタートしてからノウハウを得て拡大する戦略でも十分に効果を発揮しますので、これらの方法は保育園の規模やリソースに合わせて選択しましょう。運用開始後は社内体制や更新フローの確立が重要となり、日々の保育活動の一環として情報を収集・発信していくスキームが求められます。
さらに、オウンドメディアの運用ではアクセス解析や応募数などのデータを活用し、改善を繰り返すことが大切です。定期的に振り返りを行い、反応が良いテーマやコンテンツ形式を把握することで、より効果的に求職者を惹きつけられるようになります。
ステップ1:採用ターゲットの設定とペルソナ設計
まずは、園が求める人材像を明確にすることが重要です。保育業界の経験やスキルレベルに加え、理念への共感や子どもとのかかわり方などもポイントになります。ペルソナを詳細に描くことで、発信すべき情報や使う言葉遣いなど、コンテンツ制作の方向性がはっきりするでしょう。
ステップ2:コンテンツ計画とKPI設定
どのようなテーマで記事を作るのか、更新頻度はどれくらいか、といったコンテンツ計画を立てます。同時に、PV数や応募数、問い合わせ件数などのKPIを設定し、目標数値の達成度合いを定期的にモニタリングします。数字を意識することで、単発の効果測定ではなく継続的な改善につなげやすくなります。
ステップ3:オウンドメディアの構築・デザイン
保育園の温かみや雰囲気が伝わるデザインを心がけましょう。簡易なブログサービスやSNSを使ったスタートから、専門家に依頼した本格サイトの立ち上げまで方法はさまざまです。重要なのは、保護者や求職者にとって見やすく、園の魅力を直感的に理解してもらえるレイアウトや色使いです。
ステップ4:運用体制の確立と定期的な更新
メディア運営においては、誰が取材し、誰が執筆し、誰が写真を撮るのかといった役割分担が必要です。スムーズなフローを作り、無理なく記事や写真をアップできる環境を整えましょう。保育現場での忙しさを考慮して、スタッフ全員で協力し合う運用体制を確立することがカギとなります。
ステップ5:分析・改善サイクルを回す
アクセス解析や応募数の推移、記事ごとの反響などを定期的に確認し、運営方針を微調整していくことが欠かせません。たとえば、職員インタビュー記事の応募率が高いとわかれば、その形式のコンテンツを増やすといった改善が可能です。こうしたサイクルを続けることで、オウンドメディアがより効果的に採用を支援する仕組みに進化します。
オウンドメディアで発信すべきコンテンツ事例
保育園には独自のイベントや職員のキャラクターなど、数多くの発信材料があります。具体的にはどんな情報を掲載すべきでしょうか。
大切なのは、求職者が「この園で働いてみたい」と感じられる具体的なイメージを与えることです。たとえば、保育理念や教育方針を丁寧に解説することで、自身の考えと合うかどうかを判断しやすくなります。スタッフのインタビューや座談会、園内行事の様子がわかる写真・動画も効果的に活用しましょう。
また、今後のキャリアパスや職場のサポート体制を示すことも重要です。園長やリーダー職に興味がある人や、出産後や育児中でも働ける環境を探している人に対しては、具体的な制度や事例を提示することで安心感を与えられます。
さらに、保育だけでなく地域との連携や新しい教育プログラムなど、園が特に力を入れている取り組みを積極的に発信すると、求職者の興味・関心を引きつけやすくなります。それが園の強みとして認知されれば、採用はもちろん、保護者や地域住民からの信頼形成にもつながるでしょう。
企業理念・ミッション・バリューの紹介
保育園が大切にしている理念や使命をわかりやすい言葉で伝えることは、求職者が共感を得やすくする第一歩です。具体的なエピソードやエピソードを交えると、文字情報だけでは伝わりづらい想いが伝わりやすくなります。理念やバリューを共有できる人にとって、入職後の満足度は格段に高まるでしょう。
従業員インタビュー・座談会
現役保育士の生の声や、職場でどんな楽しさや課題があるのかを知ることは、求職者にとって魅力的な情報源です。保育士の一日の流れややりがい、チームワークの様子などをリアルに伝えることで、実際の働き方をイメージしてもらいやすくなります。信頼度が高いコンテンツとして、応募促進につながるケースも多いです。
社内イベントやワークスタイルのレポート
運動会や季節の行事、研修会などの写真やエピソードを紹介するのも有効です。保育園でのイベントは子どもたちが主役ですが、職員同士がどのように連携し、工夫を凝らしているかが見えると、職場の雰囲気は一層伝わりやすくなります。こうしたレポートは親近感や温かみを表現する絶好の機会です。
自社サービス・新規事業の現場声
保育の現場では、新しい教育プログラムや地域との交流イベント、子どもたちの成長を促す独自の仕組みなどが多数存在します。これらを具体的に紹介することで、園がどのような姿勢で進化や改善に取り組んでいるのかを伝えられます。専門性が求められる内容こそ、オウンドメディアの良さが活きるでしょう。
具体的なポジション・キャリアパスの紹介
園長やリーダー職へのステップ、専門分野へのチャレンジなど、保育士としてのキャリアパスを分かりやすく開示しておくことも重要です。キャリアアップの仕組みが見えることで、長期的に働きたいと考えている人材を惹きつけることができます。自分らしく成長できる職場環境があるとわかると、応募の意欲も高まります。
運用コストと期間の目安

オウンドメディアリクルーティングを始めるにあたって気になるのは費用と効果が出始めるまでの期間です。
実際のコストはメディアの規模や更新頻度、外部の専門家への依頼状況によって大きく異なります。初期投資としてサイト構築やデザインへの予算は必要になりますが、小規模でSNSを活用しながら無料や低コストのツールで運用を始めることも可能です。運用しながら徐々に規模を拡大していく園も増えています。
効果が現れるタイミングとしては、早い場合で3~6ヶ月ほど、一般的には半年から1年ほどかけて成果が見え始めることが多いです。これは、コンテンツの質や量が蓄積され、検索エンジンで上位表示されるようになるまでに一定の時間が必要なためです。短期決戦というよりは、中長期的な視点でじっくり取り組む姿勢が求められます。
また、運用段階では記事執筆やデザイン変更、SNS対応などの実働コストが継続的に発生します。内部リソースだけでは負荷が大きい場合、社外のライターやコンサルタントを適宜活用するといった工夫も検討すると良いでしょう。
小規模でのスタートと想定予算
初期費用を抑えるためには、無料ブログサービスやSNSなど既存のプラットフォームをうまく活用する方法があります。写真やテキスト中心であれば大きなコストをかけずに済みますし、少人数でも運用をスタートしやすいです。まずは運営に慣れ、コンテンツ制作の流れを習得してから徐々にリニューアルや拡張を検討する段階的なアプローチがおすすめです。
本格的な施策導入とROI
デザインやシステム構築に専門家を入れ、本格的なメディア運営を始めると初期投資は大きくなります。しかし、採用コストが高い外部サービスに長期的に依存するよりも、自前のメディアを育てていくほうが結果的に費用を圧縮できる可能性が高いです。狙い通りに運用できれば、保育園全体の認知度向上やブランド力アップにも寄与し、ROIとして十分な成果を生むでしょう。
オウンドメディアリクルーティングにおけるKGI/KPIの考え方
採用活動を成功させるには、どのような指標を追いかけて運用を最適化していくかが重要になります。
オウンドメディアリクルーティングでは、最終的に何名の人材を採用できるかが大きなゴール(KGI)となりますが、すぐに結果が出るわけではありません。そのため、途中経過を測定するうえで中間指標(KPI)を設定し、定期的な検証を行うことが鍵になります。例えば、PV数やエントリー数に加え、問い合わせや資料請求などのアクションをKPIと設定することで、効果を確認しながら運用方針を調整できます。
さらに、SNSからの流入や、他サイトからのリンク状況、記事ごとの直帰率なども分析することで、どのコンテンツが有効かを把握できます。保育士を志望する人が興味を持ちやすいテーマを深掘りすることで、応募意欲の高い層にリーチしやすくなるのです。
複数のKPIがある場合は、優先順位を定めることが大切です。新規の認知度向上を狙うフェーズなのか、具体的な応募増加を目指すフェーズなのかに応じて、指標を見直しましょう。長期的には、入社後の定着率のような指標も合わせて評価することで、より質の高い採用が実現できているかを測ることができます。
定量指標:エントリー数・内定数など
エントリー数や内定率は、採用の進捗をダイレクトに示す重要な数値です。定期的にチェックすることで、応募の増減にあわせたコンテンツの改善やプロモーションの調整が行えます。意図した目標を達成できているかを判断するもっともわかりやすい指標でもあります。
定性指標:企業イメージ向上やエンゲージメント
一方で、数値化しづらいブランド認知や企業イメージの向上もオウンドメディアの重要な成果となります。SNSでのコメントの質や、保育園に対する問い合わせ内容が変化したかなど、エンゲージメントの傾向を捉えることで、情報発信がどの程度求職者に伝わっているかを測ることができます。
オウンドメディアリクルーティングを成功させるポイント
オウンドメディアを活用して成果を出している園には、いくつかの共通点があります。ポイントを押さえて、自園でも活かしてみましょう。
オウンドメディアをしっかりと機能させるには、園全体でコンテンツ作りに協力する体制を整える必要があります。経営者層や現場スタッフを巻き込み、日々の保育活動を取材・撮影できるようにすると、鮮度の高い情報が自然と蓄積していきます。メディア担当者だけに負荷をかけず、全員参加のスタイルが理想的です。
また、検索エンジンやSNSからの流入を意識することで、より多くの潜在的候補者に園の存在を知ってもらうことができます。SEO対策やハッシュタグ活用、写真の見せ方など、細かな工夫が結果的に大きな差を生むポイントです。
さらに、発信する情報は常に保育園の理念やスタッフの想いと一致させることが大切です。方向性がブレると応募者の混乱を招き、園の魅力が正しく伝わりにくくなります。採用後の新人保育士へのフォローアップ体制を強化することで、せっかく入ってきた人材が長く活躍できる土壌を育むことも忘れてはいけません。
社内巻き込みとコンテンツ制作の推進体制
保育士や事務スタッフなど、さまざまな職員が日頃からコンテンツ制作や撮影に協力すると、更新の負担が分散されます。特定の担当者だけが頑張るのではなく、園全体で“メディアを育てていく”意識を共有することで、オウンドメディアがより活気あるものとなるでしょう。
SNS連携やSEOによる認知度拡大
オウンドメディアの内容をSNSでシェアしたり、キーワードを適切に設定して検索結果で上位表示されるようにしたりと、外部との連携を強化することで多くの求職者にリーチできます。特に保育園の場合、地域の保護者からのシェアや口コミの波及効果も期待できるため、多方面を意識した発信が効果的です。
ブランディング方針の継続的な検証と改良
どんな情報をどう伝えれば、保育園の理念や現場の魅力を正しく理解してもらえるのか、常に改善サイクルを回すことが大切です。数値分析とあわせて、保育園をよく知らない友人や知人の意見を取り入れたり、既存の職員からフィードバックを得たりすることで、ブラッシュアップの糸口が見つかります。
採用後のオンボーディング強化で定着率向上
オウンドメディアによる採用が成功した後も、新しいスタッフが園に溶け込みやすい仕組みを用意しておくことが重要です。具体的には、研修マニュアルの整備や、定期的な業務レビュー、メンター制度などが考えられます。採用時に得た好印象を崩さず、長期的な活躍につなげるための施策といえます。
成功事例から学ぶオウンドメディアリクルーティングの活用法
実際にオウンドメディアを活用して採用活動を成功させている事例から、自園に取り入れられるヒントを見つけましょう。
他園の成功事例を参考にすることで、オウンドメディアリクルーティングの具体的な取り組みイメージをつかみやすくなります。SNSやブログで写真や動画を日常的に発信し、園の雰囲気をありのままに見せることで共感を得ている例や、職員インタビューを記事化して保育への想いを伝えている事例など、さまざまな形が考えられます。
ポイントは、自園らしさをどのようにコンテンツに落とし込むかということです。どの成功事例にも共通するのは、ありのままの園の姿をリアルタイムで発信する一方で、しっかりとブランディングやメッセージ性を持たせている点です。もちろん、全面的に真似するのではなく、自園の強みや方針に合わせてカスタマイズしましょう。
成功事例を研究しつつ、自園で試してみたい企画やコンテンツをピックアップし、まずは小さく試すのも有効です。効果のある取り組みは継続・拡大しながら、定期的にPDCAを回して改善することで、オウンドメディアリクルーティングの成果を最大化できます。
事例1:SNS活用で企業文化をアピール
Instagramなどのビジュアル中心のSNSを活用し、日常の保育活動風景や子どもたちの笑顔を発信する事例があります。視覚的な要素が強いため、見ただけで園の雰囲気が伝わりやすく、保護者や地域住民のシェアによってより広く周知される可能性があります。結果的に、園の注目度を高め、採用にもプラスの影響を与えたケースです。
事例2:従業員インタビューでミスマッチを解消
現場で働く保育士の本音ややりがい、キャリア形成について、インタビュー形式で記事化している園があります。応募前の求職者にとっては、勤務後のイメージがつかみやすくなるため、結果としてミスマッチの解消につながります。園をより深く理解して入職を希望してくれる人が増え、定着率が高まった成功事例です。
事例3:社内リソースを活かしたコンテンツ内製化
職員の中に写真撮影やデザインが得意な人を見つけて、コンテンツ制作を内製化している保育園もあります。外注費を削減できるだけでなく、園の空気感をよく知るスタッフが発信するので、よりリアルで質の高い情報を届けることができます。運営コストを抑えながら継続的な更新ができるため、長期的にメディアを育てるうえで大きなメリットを享受しています。
まとめ:自社の魅力発信を軸に長期的な採用力を高めよう
オウンドメディアリクルーティングは、保育園だからこそ発信できる多彩なコンテンツを活用し、長期的に理想の人材を確保するための有力な手段です。
保育園という現場には、子どもの笑顔をはじめ、スタッフのチームワークや教育方針など、魅力を感じてもらえる要素が数多く存在します。オウンドメディアはこれらの強みを直接求職者に届けられる点で、他の手法にはない大きな可能性を秘めています。
ただ、成功に向けては初期投資や継続的な運用体制づくりなど、時間と手間を惜しまない姿勢が欠かせません。短期的な効果のみを求めるのではなく、長い目でメディアを育てることで、安定的な採用力とブランド力を手にすることができるでしょう。
今後も保育園の採用環境はますます変化していくことが予想されます。オウンドメディアを軸に情報発信を強化し、未来のスタッフが安心して働きやすい環境づくりに取り組んでいくことが、理想のチームづくりへと繋がるはずです。
\自園と相性のよい人材が長く働いてくれる、保育のカタチの採用支援/