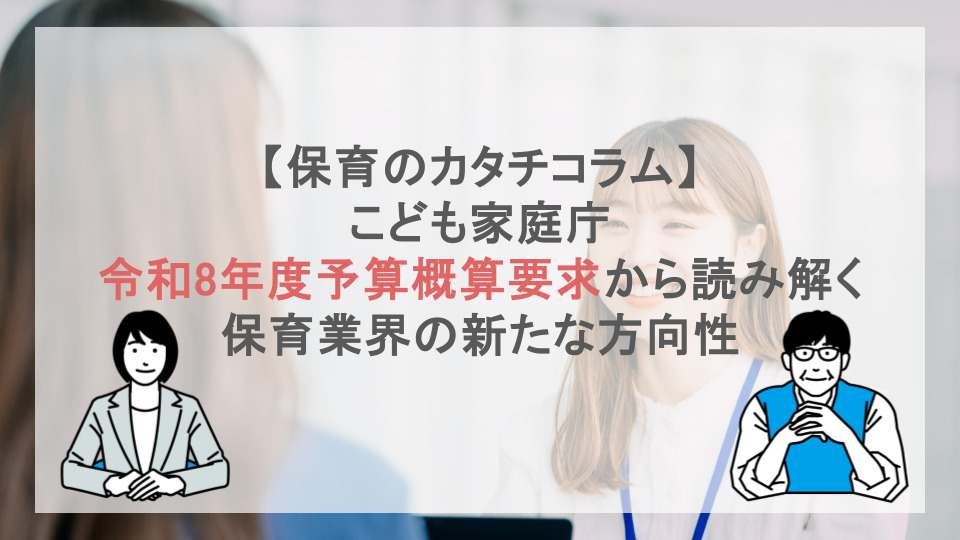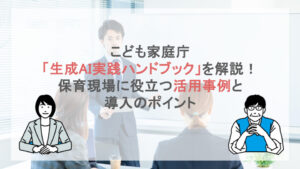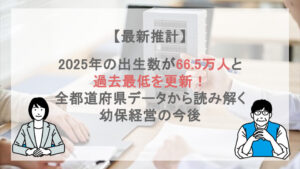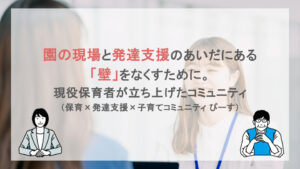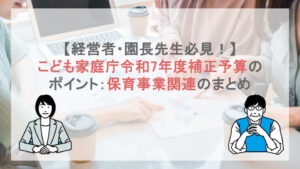3分でわかる令和8年度予算のポイント
こども家庭庁が公表した令和8年度の保育関係予算概算要求は、総額2兆5,074億円(前年度比562億円増)にのぼります。この予算案は、今後の保育政策が大きく変わることを示しており、その方向性は主に4つのキーワードで説明できます。
- 保育の対象拡大(普遍的利用): これまで保育施設は主に共働き家庭の子どもが利用する場所でしたが、「こども誰でも通園制度」が本格的に始まることで、親の就労状況にかかわらず、すべての子どもが利用できる地域の施設へと役割が変わります。
- 人材確保の方針転換: これまでの待機児童対策を中心とした保育士の「数」の確保から、保育士の専門性を高め、キャリアアップを支援する「質」の向上へと政策の重点が移ります。
- 国主導のデジタル化(保育DX): 各施設が個別にICT化を進める段階から、国が統一したデジタルシステムを構築する段階へと移行します。これにより、業界全体の事務負担軽減と業務効率化を目指します。
- 多様なニーズへの対応: 少子化や人口減少、児童虐待問題の深刻化といった社会の変化に対応するため、過疎地域の保育機能の維持や、病児保育、医療的ケア児支援など、多様な家庭環境に合わせたきめ細やかな支援が強化されます。
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/
これらの変化は、保育施設の運営者や現場の保育士にとって、新たな対応が求められることを意味します。以下の表は、今回の予算案の主要なポイントをまとめたものです。
| 重点分野 | 主要事業名 | 概要 | 施設運営上のポイント |
| 新たな保育の形 | こども誰でも通園制度の本格実施 | 在園していない子どもも時間単位で利用できる制度を全国で開始。 | 新たな収益機会となる一方、不特定多数の子どもへの対応力や安全管理体制の構築が必要。 |
| 人材確保・質向上 | ミドルリーダー育成事業【新規】 | 園内で研修などを企画できる中核人材を育成し、保育の質向上を目指す。 | 職員の新たなキャリアパスとなり、定着率向上が期待できる。育成した人材の活用方法が重要になる。 |
| 人材確保・質向上 | 保育士・保育所支援センターの機能強化 | 就職実績などの目標(KPI)を設定し、成果に応じて支援を強化。人材確保の実効性を高める。 | 地域の支援センターとの連携を強めることで、人材採用が有利になる可能性がある。 |
| 保育DX | 保育業務施設管理プラットフォーム構築 | 給付申請や監査対応などをオンラインで完結させる国の新システム。 | 国のシステムへの対応が必須となる。事務負担の大幅な軽減が期待されるが、初期の操作習熟が必要。 |
| 保育DX | 保活情報連携基盤の構築 | 保護者の施設探しから申請までをオンラインで完結させるサービス基盤。 | 保護者からの問い合わせや申し込みがデジタル化。施設の情報をオンラインで効果的に発信する必要性が高まる。 |
| 地域・安全対策 | 人口減少地域の保育機能確保モデル事業【新規】 | 人口減少地域の保育所が、地域の子育て拠点として多機能化するためのモデル事業。 | 学童保育や高齢者交流など、地域のニーズに応える新たな役割を担うことで、地域での存在価値を高める機会となる。 |
| 地域・安全対策 | 保育所等における虐待防止対策支援【新規】 | 改正児童福祉法に基づく通報義務化に対応するため、自治体の体制強化や研修を支援。 | 虐待防止に関する園内体制の見直しと全職員への研修が必須に。行政との連携がより重要になる。 |
こども家庭庁が目指す保育業界の姿とは?

今回の予算概算要求から、こども家庭庁が保育業界にどのような変化を期待しているのか、その意図を読み解いていきます。
意図1:保育施設を「すべての子育て家庭を支える地域の拠点」へ

今回の予算案で最も象徴的なのが「こども誰でも通園制度」の本格実施です。これは、保育施設の役割を根本的に変えようとする国の意図の表れです。
こども家庭庁の狙い: これまで保育施設は、主に「親の就労支援」という目的で利用されてきました。しかし、この新制度によって、親が働いているかどうかにかかわらず、生後6か月から3歳未満の子どもが時間単位で施設を利用できるようになります。
これにより、こども家庭庁は保育施設を、すべての子育て家庭が気軽に利用できる「社会的なインフラ」へと転換させたいと考えています。
施設への影響: 施設にとっては、定員割れしている場合の空き定員や空きスペースを活用して新たな収益源を確保できるというメリットがあります。国も施設改修費の補助率を引き上げるなど、制度導入を後押ししています。
一方で、課題もあります。毎日違う子どもを短時間預かることは、在園児中心の従来の保育とは異なり、アレルギーや発達特性の把握、安全確保など、より高度な対応力が求められます。
現場の保育士の負担が増えることへの懸念も指摘されています。 この変化に対応するためには、例えば「誰でも通園」専門の職員を配置したり、専用のスペースを設けたりするなど、従来の運営方法を見直す必要が出てくるでしょう。
意図2:保育士を「量から質へ」、キャリアアップできる専門職へ

待機児童問題が全国的に解消に向かう中、こども家庭庁は保育士政策の重点を「数の確保」から「質の向上」へと大きくシフトさせています。
こども家庭庁の狙い: 保育士が専門職として長く働き続けられるよう、キャリアアップの道筋を明確にし、その専門性に見合った評価と処遇を実現できる業界にすることを目指しています。
具体的な施策:
- 処遇改善の継続と制度の簡素化: 民間企業の給与動向を踏まえた処遇改善を継続するとともに、複雑だった処遇改善加算制度を一本化し、事務負担の軽減と分かりやすい給与体系の構築を進めています。
- 「ミドルリーダー」育成事業の新設: 園内で研修を企画したり、地域の他の園に助言したりできる中核的な人材(ミドルリーダー)を育成する事業が新たに始まります。これは、保育士に明確なキャリアパスを示し、現場主導で保育の質を高めていくための重要な取り組みです。
- 支援の重点化: これまで待機児童対策として都市部に集中していた「保育士宿舎借り上げ支援」などの補助を見直し、その財源をミドルリーダー育成など全国的な質の向上に資する事業に再配分します。これは、国の政策が完全に「量から質へ」と転換したことを示しています。
- 保育士・保育所支援センターの機能強化: 地域の人材確保の拠点である支援センターに、就職マッチング件数などの目標(KPI)を設定させ、成果に応じた支援を行うことで、より戦略的な人材確保を進めます。
意図3:デジタル技術の活用を「当たり前」の業界へ

今回の予算案では、国が主導して全国規模のデジタルプラットフォームを構築することに大きな予算が割り当てられています。これは、保育業界のDX(デジタルトランスフォーメーション)を強力に推進する国の姿勢を示しています。
こども家庭庁の狙い: デジタル技術の活用を標準化することで、保育士の事務負担を抜本的に削減し、その分の時間を子どもと向き合う時間に充てることで保育の質を向上させること、そして保護者の利便性を高めることを目指しています。
具体的な施策:
- 保育業務施設管理プラットフォーム: 自治体への給付費請求や監査対応といった行政手続きをオンラインで完結させるシステムです。将来的には、このシステムの利用が公的給付を受けるための必須条件となる可能性が高く、業界全体のデジタル化を促すことになります。
- 保活情報連携基盤: 保護者が施設を探し、入園を申し込むまでの一連の手続きをオンラインで完結できるシステムです。
- 現場へのICT導入支援の拡充: 各施設へのICT導入補助も継続・拡充されます。新たに、先進的なICT活用事例を共有する「保育ICTラボ事業」も創設され、施設間のノウハウ共有を促進します。
DXの導入には初期コストや職員研修といった課題もありますが、国の主導で進められる以上、デジタル化への対応はもはや選択肢ではなく、すべての施設にとって必須の経営課題となります。
意図4:社会の変化に対応し、地域に不可欠な存在へ

少子化や人口減少、児童虐待の増加といった社会課題に対し、保育施設がより積極的な役割を果たすことを国は期待しています。
こども家庭庁の狙い: 保育施設が単に子どもを預かるだけでなく、地域の子育て支援の拠点(ハブ)として多機能化し、同時に子どもの安全を徹底的に守るセーフティネットとしての役割を担うことを求めています。
具体的な施策:
- 人口減少地域での多機能化支援: 過疎地域などの保育所が、学童保育や子育て相談、高齢者との交流拠点といった多様な役割を担うためのモデル事業を新たに開始します。これは、保育所を地域の存続に不可欠な社会的インフラと位置づける考え方です。
- 虐待防止対策の強化: 虐待の通報義務化などを盛り込んだ改正児童福祉法の施行に合わせ、自治体の専門人材活用や職員研修などを支援する事業を新設し、虐待の未然防止と早期対応体制を強化します。
- 安全対策設備の導入支援: 睡眠中の乳幼児を見守る「午睡センサー」や「AI見守りカメラ」など、子どもの安全を守るための設備導入への補助を拡充します。
- 多様なニーズへの対応強化: 病児保育の広域連携をICTシステムで支援したり、医療的ケア児の受け入れ体制を手厚く補助したりするなど、様々な家庭の状況に応じた支援をきめ細かく行います。
まとめ:こども家庭庁が描く保育業界の未来像
令和8年度予算概算要求は、こども家庭庁が保育業界に対して明確なビジョンを持っていることを示しています。それは、以下のような未来像です。
- すべての保育施設が、地域の子育て支援のハブになる。
- すべての保育士が、専門職としてキャリアを築き、正当に評価される。
- すべての業務が、デジタルを前提に効率化され、保育の質向上に集中できる。
- すべての家庭が、多様なニーズに応じた支援を受けられる社会基盤となる。
この変化は、保育施設の経営者や職員にとって、これまでのやり方を見直し、新たなスキルを習得する必要があるなど、決して簡単なものではありません。しかし、これらの変化に対応していくことが、今後の保育業界の発展と、地域社会における施設の価値を高めることにつながっていくでしょう。
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/