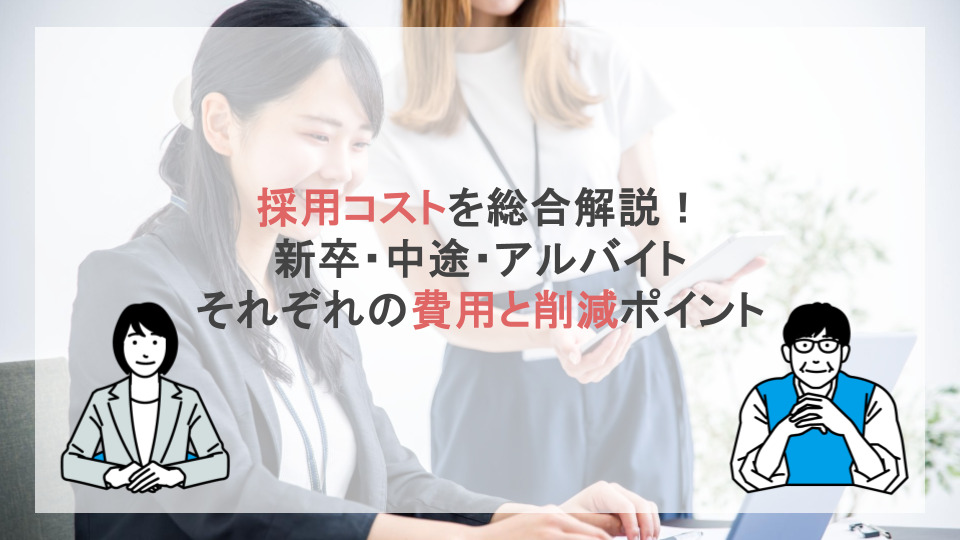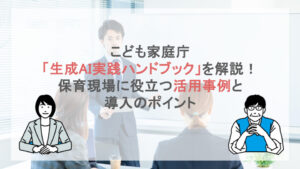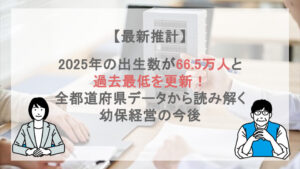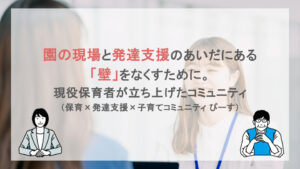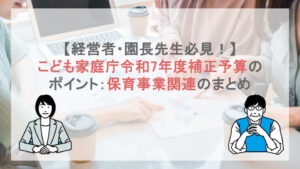企業が人材を採用する際に発生するコストは多岐にわたります。本記事では、新卒採用・中途採用・アルバイト採用のそれぞれにおけるコストの違いや具体例を交えつつ、削減のためのポイントを詳しく解説していきます。戦略的に採用コストを管理し、最適な人材を獲得するための方法を一緒に探っていきましょう。
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/
1. 採用コストとは?基礎概念と採用単価の位置づけ
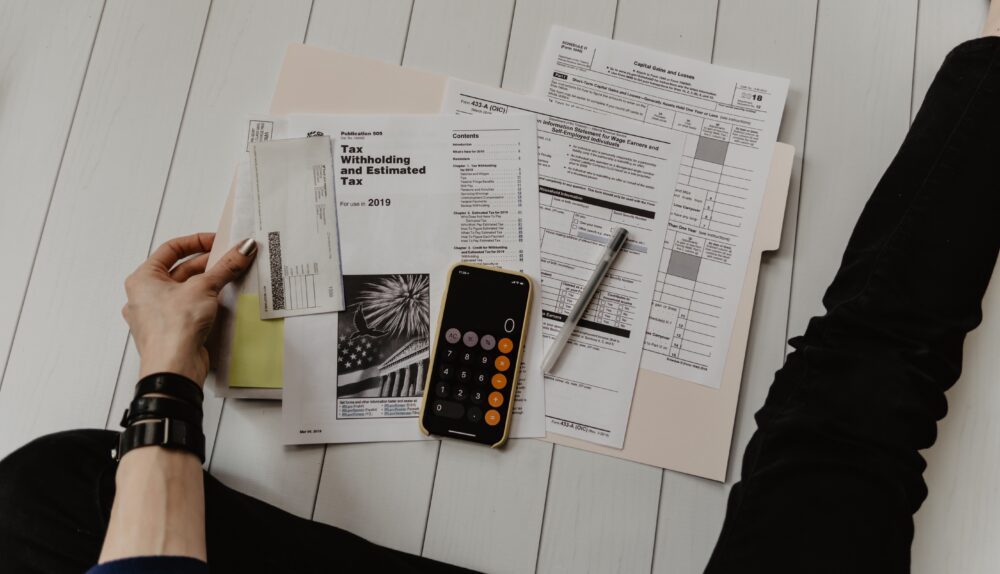
まずは採用コストの基礎となる概念や、採用単価をどのように位置付けるかを整理していきます。
採用コストとは、企業が新たに人材を獲得するときに必要となる費用の総称です。求人広告や人材紹介会社への手数料といった外部に支払う費用だけでなく、面接や選考にかかる担当者の工数、各種事務手続きに必要な時間や労力などの内部的なコストも含まれます。これらのコストを正確に把握し管理することで、人材採用の効率化や戦略的な採用活動に結びつけることが可能です。
1-1. 外部コストと内部コストの違い
外部コストとは、求人広告費や人材紹介会社への成功報酬、説明会や採用イベントの参加費など、社外へ支払われる費用を指します。たとえば、大手求人媒体に掲載するときの広告掲載費や、エージェントによる紹介手数料などが代表的です。求める人材のレベルや採用規模によって変動が大きいため、定期的に見直す必要があります。
一方の内部コストは、採用担当者や面接官の人件費、応募者への連絡にかかる時間、書類の準備・審査など、企業内部で発生する費用です。特に採用担当者が担当する業務範囲が広いほど、時間的な負担がかさみコストも大きくなりがちです。内部コストを可視化することで、採用フローのどの部分に多くの工数が要しているかを明確に把握できます。
両方のコストを正しく区別し、現実的な予算編成や改善策を打ち出すことが、採用活動を円滑に進めるうえで欠かせません。外部コストが大きくなりすぎていないか、また内部コストが非効率になっていないかをチェックし、最適なバランスを模索する姿勢が重要です。
1-2. 採用単価とその算出方法
採用単価とは、1人の採用に要したコストのことを指し、総採用コストを採用人数で割ることで算出できます。この値を求めることで、採用活動の効率性を客観的に把握しやすくなります。採用の成果や課題を数値化して比較する際にも便利な指標です。
たとえば、年間の採用コスト総額が1,000万円で、その年に10名を採用したとします。すると採用単価は100万円となり、この数字は過去実績や他社事例と比較して高いか低いかを判断できる材料になります。新卒・中途・アルバイトなど雇用形態によっても異なるため、区分ごとに算出・分析するのがおすすめです。
数値を見たうえで、広告費に偏っているのか、人件費が増えすぎているのかなど原因を掘り下げることが重要です。採用単価を用いて分析することで、改善すべきポイントを具体的に洗い出し、予算配分の最適化につなげられます。
1-3. 採用コストが高騰する背景
採用コストが近年高騰傾向にある主な要因としては、少子高齢化や人材需給のミスマッチによる採用難が挙げられます。特に新卒採用の領域では、学生数の減少や売り手市場化が進んでおり、企業側の競争が激化しています。
中途採用でも即戦力を求める企業が多く、好条件での採用活動を展開せざるを得ない状況がコスト増を招きます。さらにIT化の進展に伴い、高度なスキルを持つ人材に対する需要が増す一方で、供給が追いつかないケースもあります。
こうした市場背景から求人広告費やエージェント費用が高くなり、企業の採用コストが上昇しやすくなっているのです。だからこそ、より効率的かつ的確な採用チャネルとスクリーニングプロセスを確立する必要があります。
2. 採用コストの平均相場:新卒・中途・アルバイト
各雇用形態ごとに発生する採用コストの平均相場と、その背景へとフォーカスを当てます。
新卒、生涯雇用を期待できる若手の確保、中途、即戦力の補強、アルバイト・パート、現場の補助戦力の獲得など、企業は多様な人材を求めています。それぞれの採用方法によって発生するコストの性質が異なるため、平均的な相場を知ることは重要です。
相場を踏まえることで、どの段階や方法に最もコストがかかるのかが明確になり、課題に合わせた予算配分がしやすくなります。特に募集人数やターゲット層ごとに違った戦略を立てることで、採用費の増大を抑えることが可能になるでしょう。
2-1. 新卒採用コストの平均と要因
新卒採用では、大学生向けの合同説明会やインターンシップなど特有の施策が必要となり、その準備や実施にかかる時間と費用が大きくなりがちです。実際の平均コストは1人あたり90万円を超えるケースが多く、近年ではさらに上昇する傾向にあります。これは学生数の減少や、企業同士の採用競争が激化していることも影響しています。
採用担当者が複数の大学を回り説明会を行う場合や、インターンシップの企画・運営を行う場合にかかる人件費など、内部コストも見逃せません。説明資料やプロモーション動画などを作成する場合、制作費用といった外部コストも追加で発生します。
こうした事情から、新卒採用は長期スパンで予算を組む必要があります。早期からインターンを行い企業理解を深めてもらう一方で、ターゲット学生が十分確保できる採用チャネルを見直すなど、効率的な戦略が求められます。
2-2. 中途採用コストの平均と特徴
中途採用の平均コストは1人あたり100万円前後とされるケースが少なくありません。新卒よりやや高めになる理由としては、即戦力の人材に対して高めの年収レンジを提示する場合が多く、さらにエージェントを積極的に利用する企業が増えている点が挙げられます。
エージェントによる成功報酬は採用された人材の想定年収に比例することが多いため、高スキル人材を採用しようとすると必然的にコストが増加します。また、書類選考や面接にかかる担当者の工数も、新卒とは異なり専門的なスキル評価が必要になるため、審査項目が多くなりがちです。
こうした特徴から、中途採用では確実な選考フローとターゲット設定が不可欠になります。自社にフィットしない人材を大量に応募させるよりも、必要なスキルや経験を明確に打ち出すことで、無駄なやり取りを減らすことが大切です。
2-3. アルバイト・パート採用で発生しやすい費用
アルバイトやパートなどの非正規雇用形態では、募集頻度が高い点が特徴です。小売店や飲食店などでは、短期的に数多くの人員を補充する必要が生じる場合もあり、そのたびに求人広告を出すコストが積み重なります。
求人媒体へ掲載する費用がメインの外部コストとなりやすいものの、こまめに募集をかけるため、登録や更新などの作業コストも増えがちです。面接1回あたりの時間は短くても、高頻度で対応する必要があるため、採用担当者の工数も決して小さくありません。
また、採用決定後の研修や教育にかかる内部コストも見逃せないポイントです。短期離職が発生すると再度同じ募集を繰り返すことになるため、出来るだけ長く定着してもらう工夫が、長期的な採用コスト削減につながるでしょう。
3. 採用コストに含まれる主な費用項目

採用コストを理解するためには、どのような項目が含まれるのかをしっかり把握することが不可欠です。
具体的な費用項目を知ることで、あらゆる経費を見逃さずに計上できます。外部コストだけでなく、社内で発生する費用も正確に把握しなければ、実際のコスト全体像をつかむのは難しいでしょう。
ここでは、大きく「外部コスト」「内部コスト」「採用ブランディング関連費用」の3つに分けてその特徴を整理します。どれか一方に注目しすぎると、偏った予算配分になってしまう可能性があるため、バランスを見極めることが大切です。
3-1. 外部コスト(求人広告・エージェント・イベントなど)
外部コストで最も一般的なのが、求人広告費です。大手の求人媒体に掲載する場合、掲載プランによっては高額になるケースも多く、長期掲載を続けるとその分コストがかさんでしまいます。さらにエージェントへの紹介手数料も、中途採用や専門人材の募集では必要な投資となるケースが多いです。
イベントコストとしては、合同企業説明会の参加費や、独自の採用フェアを開催する際の会場費用・運営費用などが代表的です。特に新卒採用ではこういったイベントが多いため、対策を怠ると一気に予算オーバーになりかねません。
どの媒体・イベントをどのくらい利用するかを見極めて、1人あたりの採用単価に見合う費用かどうかを常に検討する姿勢が重要です。採用計画の初期段階で、どの程度の応募数やターゲット層を狙いたいかをはっきりさせ、費用対効果を考慮したうえで運用を行うと良いでしょう。
3-2. 内部コスト(採用担当者の人件費・面接対応など)
内部コストには、採用担当者や経営陣、面接官などが採用にかける時間と人件費が該当します。応募受付や面接調整、進捗管理など、日常的に発生する業務が積み重なると意外に大きなコストとなります。
特に複数の部署が絡む場合、調整コストが増加しがちです。面接官のスケジュール調整や入社手続きの準備など、必要な作業が多岐にわたるため、担当者1人当たりの負荷が高くなることもあります。
これらを削減するには、採用管理システムやオンライン面接ツールを活用し、応募者との連絡や書類管理を効率化することが有効です。煩雑な業務を削減できれば、その分を応募者の質の見極めやスクリーニング精度向上に振り向けることもできます。
3-3. 採用広報・ブランディングにかかる費用
採用広報やブランディングは、近年ますます重要性を増しています。自社の魅力を多角的にアピールし、求職者に「この会社で働きたい」と思わせるための情報発信が、採用成果に大きく影響するからです。
具体的には、企業パンフレットの作成、採用動画、SNS運用、オウンドメディア設計費などが考えられます。一度の制作費用が高額に感じるかもしれませんが、長期的に使い回せるコンテンツになればコストパフォーマンスは悪くありません。
ただし発信内容が求職者のニーズと乖離していると、せっかくのブランディング活動も空振りに終わる可能性があります。自社の強みや魅力を正確にとらえたうえで、適切な媒体や表現方法を選ぶことが鍵となります。
4. 採用コストが高くなる要因と見直しのポイント
採用コストを無駄に膨らませないための原因分析と、見直しに役立つ視点を確認しましょう。
採用コストが高くなる原因は、外部要因だけでなく企業内部の仕組みや運用方法にも潜んでいます。主に採用チャネル選定や要件定義、選考フローの設定など、初期設計段階でのミスや曖昧さがコスト増を引き起こすケースが多いです。
ここでは、代表的な要因である「採用チャネルのミスマッチ」と「採用要件の曖昧さ」について解説し、どのように見直せば効率化できるかを考えていきます。
4-1. 採用チャネルのミスマッチ
使用する求人媒体や募集方法がターゲット人材と合っていない場合、応募者は集まっても質が伴わないという事態になりかねません。ターゲットが異なる複数チャネルを同時並行で利用するとコストは増えますが、効果が薄いチャネルを使い続けても投資対効果は低下する一方です。
また、社内で過去に成功した方法を使い続けるあまり、市場トレンドが変化しているのを見落とすケースもあります。これによりコストだけが膨らみ、欲しい人材はまったく集まらないという結果に陥りやすいです。
定期的に応募者データを分析して、どの採用チャネルが最も質の高い応募をもたらしているのかをチェックすることが大切です。そこから得たインサイトをもとに、予算や労力を最適化する施策を打ち出すと良いでしょう。
4-2. 採用要件の曖昧さや選考フローの不備
採用要件がぼんやりしていると、不要な応募が増加し、人事担当や面接官の工数を無駄に浪費してしまいます。特に中途採用では専門スキルや経験年数の要件を明確にしなければ、選考に時間ばかりかかり最終的に採用コストを押し上げる要因になります。
さらに選考フローに無駄なステップが多い場合、候補者が途中で離脱してしまう可能性も高まります。複数回の面接を必要とする企業もありますが、その目的や評価項目を明確化しないまま実行すると、時間や人件費が増大する一方です。
採用プロセスを絞り込み、各ステップの目的を再確認することで、必要最小限のフローに抑えることができます。結果的に候補者の負担も減り、企業側も本来の重要作業に集中できるため、全体の効率が高まるでしょう。
5. 採用コストを削減するための具体的施策

具体的にコストを抑えながら採用を成功させるための方法や、注目される手段を紹介します。
採用コストの削減は、ただ費用を抑えることだけを目的とするのではなく、効果的な採用につなげるための手段として考えることが重要です。無理に広告費をカットしてしまうと結果的に応募が集まらず、余計にコストがかさむこともありえます。
ここでは、自社採用サイトやリファラル採用、ダイレクトリクルーティングなど、さまざまな施策を取り上げ、その狙いやメリットを整理していきます。
5-1. 自社採用サイト・オウンドメディアの強化
求人広告に依存しすぎると、掲載費用や契約更新費がかさみがちです。一方で自社採用サイトやオウンドメディアをしっかり作り込み、そこに流入を集めることで長期的な広告費を削減できます。
また、自社の魅力やカルチャーを直接的に発信できるため、ブランドイメージを深くアピールできます。写真や動画、実際に働く社員の声などを豊富に掲載することで、求職者が具体的に働くイメージを抱きやすくなるのです。
ただし、サイトやメディアの運営には定期的な情報更新やSEO対策が必要となります。運用コストを正確に見積もったうえで、採用全体のコスト構造における位置づけを検討することが大切です。
5-2. リファラル採用(紹介採用)の推進
リファラル採用は、社内の従業員から優秀な人材を紹介してもらう手法です。外部の求人媒体やエージェントを介さずに採用できるため、コストを抑えやすく、かつ紹介者がお墨付きを与えることでミスマッチが少ないという特徴があります。
紹介が成立した際には、紹介者にインセンティブを支払うケースも多いですが、エージェントの成功報酬よりは低い設定にできる場合が多いです。企業カルチャーをすでに理解している社員が紹介するため、定着率が高いというメリットも期待できます。
ただし、社内のコミュニケーションや周知が不十分だと、思うように紹介が集まらないこともあります。制度設計や報酬設定、紹介後のフォローアップなどを整え、従業員が積極的に動きたくなる仕組みを作ることが重要です。
5-3. ダイレクトリクルーティングの活用
ダイレクトリクルーティングとは、企業側から積極的に候補者にアプローチする採用手法のことです。従来型の「待ち」の採用ではなく「攻め」の姿勢を取ることで、理想に近い人材へ直接働きかけられる点が魅力です。
職務経歴サイトやSNSなどで候補者を探索し、興味を持ってもらえれば高い確率で面接につながります。求人広告費が削減できるだけでなく、競合に先んじて優秀な人材を確保するチャンスも生まれます。
ただし、自社内でリサーチやアプローチを行うリソースが必要です。スカウトメールや面談調整など手間がかかるため、ツールやサービスの活用、また担当者のスキル向上が不可欠となります。
5-4. SNS・ソーシャルリクルーティングの導入
FacebookやX(旧Twitter)などのSNSは、多くのユーザーが日常的に利用しているため、認知度を高める場として有効です。特に若手層にアプローチしたい場合、SNSで企業の日常風景や社員の様子を発信し、興味を引くことが可能です。
今まで企業の公式アカウントが発信する内容に触れる機会がなかった層にリーチできるのも利点です。広告費を一定期間だけ投下してターゲットを絞り込むこともできるため、必要なときに集中して募集をかける方法としても有用です。
ただしフォロー数や投稿内容の質が低いと、せっかくの見込み人材も興味を持たず離れてしまうことがあります。企業のブランディングを意識しつつ、価値のある情報を継続的に発信する運用が求められます。
5-5. 採用プロセス・選考フローの効率化
採用プロセスが複雑になりすぎると、面接官や応募者双方の時間的負担が大きくなり、コスト増の原因となります。例えば、面接回数を減らしたりオンライン面接を導入したりするだけでも、かなりの工数削減が期待できるでしょう。
また、一次面接前に適性検査ツールや簡易テストを取り入れれば、早い段階で候補者を絞り込みやすくなります。時間や場を限定して効率的に選考を行うことで、候補者のモチベーション維持にもつながります。
プロセスを変える際には、内部担当者の負担だけでなく、候補者が受け入れやすい仕組みになっているかどうかも確認しましょう。スピーディーな対応は離脱防止にも直結し、結果的に長期的な採用コスト削減に貢献します。
5-6. 早期離職・内定辞退対策の強化
せっかく採用した人材が早期に離職してしまうと、再び採用活動をやり直すことになり、長期的に見てコストが膨張します。ミスマッチを減らすためには、企業側が実際の業務内容や風土を正確に伝え、求職者の期待値を適切に調整することが重要です。
内定辞退が多い場合は、内定後フォローや条件の明示が不十分である可能性があります。企業の方針や待遇面をしっかり伝えるとともに、業務開始までの不安を解消する取り組みを行うことで、候補者の入社意欲を高められます。
採用後の定着支援として、オンボーディングプログラムやメンター制度を整えるのも有効です。早期離職を防ぐことで、採用活動そのものの負担を大幅に削減できます。
6. 採用コスト削減に役立つサービス・求人媒体
採用コストを最適化するために活用できるサービスや求人サイトを取り上げ、特徴を整理します。
近年、インターネットやSNSの普及に伴い、多種多様な求人媒体や採用支援サービスが登場しています。それぞれの特性を知り、自社が求める人材に合ったチャネルを選択することが大切です。
必要な状況やターゲット層に応じて複数のサービスを使い分けることで、全体のコストを抑えながら効率的に人材を確保できるでしょう。
6-1. Indeedや求人検索エンジンの活用
Indeedのような求人検索エンジンは、求職者が一括でさまざまな求人を検索できる利便性が特徴です。自社の求人情報を登録することで、幅広い層にアプローチしやすくなります。
広告費を最低限に抑えて運用することも可能で、課金方式にはクリック課金や応募課金など複数種類があり、予算に合わせて選べます。費用対効果とアクセス数が見合っているかをチェックしながら、出稿タイミングやキーワード設定を最適化しましょう。
アルバイト募集など短期的な大量採用にも向いていますが、専門人材や即戦力を探す場合は、他の媒体との併用も視野に入れるとよいでしょう。
6-2. Wantedly・Greenなど共感型採用サイト
企業カルチャーやビジョンへの共感を重視する採用サービスとして、WantedlyやGreenが注目されています。求人票には書ききれない社内環境や具体的なプロジェクトの情報を詳しく載せられるため、マッチ度の高い候補者との出会いを促進できます。
こうしたプラットフォームを活用する際は、企業のストーリーや魅力をしっかりと発信することが重要です。テキストだけでなく写真や動画を活用することで、働く雰囲気がより伝わりやすくなります。
広告費自体は比較的抑えられることが多いですが、メッセージのやり取りやスカウトなどの運用には時間が必要です。こまめに更新や応答を行いながら、採用担当者と候補者が気軽にコミュニケーションできる環境を整備しましょう。
6-3. RPO(採用代行)サービスの検討
採用プロセスの一部または全てを外部に委託できるサービスとして、RPO(Recruitment Process Outsourcing)が広がりを見せています。自社のコア業務に集中しながら採用を進められるメリットがあり、専門家のノウハウを活用することで採用効率を高められます。
ただし、完全に業務委託すると自社の文化や雰囲気が正しく伝わりにくい場合があるため、コンテンツづくりや候補者対応の方針はしっかり共有する必要があります。契約形態や費用構造もサービスによってさまざまなので、導入前には比較検討を十分に行うことが望ましいでしょう。
人事部のリソース不足を解消しながら、専門知識を活かした効率的な採用活動を実現できるのが魅力です。特に大量採用や短期間での採用が必要なタイミングで、利用を検討する企業が増えています。
8. まとめ・総括:戦略的な採用コスト管理で最適な人材獲得を目指そう
最後に、採用コストを正しく管理しながら優秀な人材を獲得するための基本方針を振り返ります。
採用コストは、単に支出を抑えること以上に、適切な手段を選択して必要な人材を確保するための投資として捉えるべきです。外部コスト、内部コストいずれも明確に可視化し、自社が望む採用成果につながる形で最適化していくことが求められます。
新卒・中途・アルバイトといった雇用形態ごとの特性を踏まえ、コストバランスを見直すのも大切です。さらに、チャネルや選考フローなどの施策を適正化し、早期離職防止のためのフォローアップまでを含めて総合的にチェックしましょう。
結果として、採用コストを正しく管理し、欲しい人材を着実に獲得できる企業は、長期的にも安定した成長を遂げやすくなります。まずは自社の現状を把握し、効果的な採用戦略を打ち立てることが第一歩となるでしょう。
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/