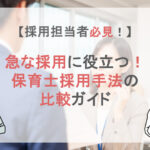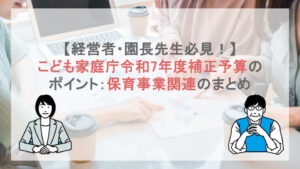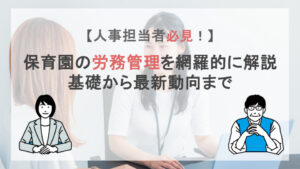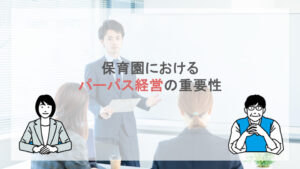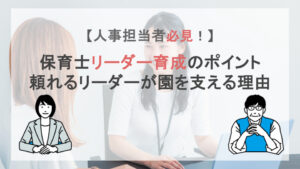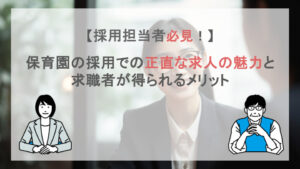人員確保が最重要課題となりやすい幼保業界では、採用活動を効果的かつ効率的に進めるため、採用チームの組成が注目されています。ひとりが採用実務を抱え込むよりも、多方面の役割を複数人で分担しながら取り組むほうが、迅速な意思決定や候補者へのきめ細やかな対応が期待できるからです。
本記事では、採用チームを組成するメリットや具体的な役割分担、必要なリソースの考え方、そしてチームを動かす際のステップを詳しく解説します。採用担当者同士の協力体制を築くことで、優秀な人材の確保と現場の負担軽減を同時に実現できる点は、幼保施設・保育園にとって大きな利点といえます。
最後には、運用上の注意点や成功事例も交え、採用活動を途切れなく前進させるためのヒントを紹介します。これから採用チームを作りたい、または最適化を図りたい方向けに、段階的なアプローチをわかりやすく整理しました。
理事長・園長先生が1人で採用していて手が回らないなど、採用チームづくりのために、課題の整理を一緒にしてみませんか。
\支援実績1000社以上!園の全体最適を考えた採用をサポート!/
\自園と相性のよい人材が長く働いてくれる、保育のカタチの採用支援/
採用チームを組成するメリットとは?

採用には多くのタスクが発生し、1人ですべてを担うのは非効率です。採用チームを組成することで、業務の分散と専門性の向上を図りながら円滑な採用活動を実現できます。
幼保施設・保育園では、求人広告の作成や応募者との連絡、応募書類の整理、面接調整など、採用に関わる業務が多岐にわたります。ひとりでこれらをこなすと、どうしても作業が手薄になりがちです。そこで、異なる専門性や立場を持つ複数のメンバーがタスクを分担することで、対応漏れやミスを減らすことができます。
チーム制を導入すると、採用戦略のアイデアや改善策を複数の視点から検討できる利点も生まれます。現場のリーダーや管理担当者、経営層などが連携すれば、候補者との接点をより質の高いものへと発展させられるでしょう。また、面接官が複数いたほうが評価の公平性も高まり、採用後のミスマッチ防止につながります。
さらに、多様なバックグラウンドを持つメンバーが採用に携わることで、自園や施設の魅力を幅広く発信できます。チームの中で情報を共有し、得意分野を活かして協働することで、施設の認知度向上と候補者の増加に寄与するのです。
採用チームの基本的な役割と構成
採用チームの目的は、施設のビジョンに合った人材を見定め、スムーズに入職まで導くことです。そのために必要な役割を明確化しておくと、それぞれの強みを活かしたチーム運営が可能となります。
採用チームの構成は、幼保施設・保育園が求める人材像や規模感、採用目標などによって異なります。たとえば施設長や園長が採用マネージャー/採用リーダーを兼任し、既存の職員がオペレーターや面接官を兼任するケースなど、複数の形態が考えられるでしょう。どの形態でも明確な役割分担がなされていることが重要です。
近年では、求人媒体の選定やソーシャルリクルーティングなど、さまざまな採用手法が登場しています。それらを適切に取り入れ活用するには、チーム内で情報を更新・共有し合う仕組みが不可欠です。役割が明確であれば誰がどの領域を担当し、どこで協力が必要かが分かりやすくなります。
以下で紹介する5つの基本的な担当を押さえておけば、チームとして採用活動を円滑かつ効率的に進めるための土台を固めやすくなります。
採用マネージャー/採用リーダー
採用チームを統率し、採用計画の立案や予算管理、スケジュール調整など全体の進捗を管理します。幼保施設の運営全体を見渡したうえで、人材の配置や募集活動の方向性を示す役割を担うため、経営方針と採用方針をリンクさせることが求められます。
このポジションは、採用活動が施設全体に与えるインパクトを理解しながら、チームメンバーのモチベーションを高めるリーダーシップを発揮することが重要です。また、外部リソースの活用や、新しい採用ツール導入の可否判断を行う場合もあり、幅広い知見が求められます。
幼保施設・保育園の特有の勤務形態や募集時期、必要資格などを踏まえたうえで、効果的な採用手法を選定する能力も欠かせません。
リクルーター
求人媒体への掲載や求人ページの作成、SNSなどを通じた母集団形成を担うポジションです。施設の魅力や募集要項をわかりやすく伝えるプレゼン力が求められるため、文章やビジュアルのデザイン面まで意識して情報発信を行うこともあります。
幼保施設・保育園の場合は、保護者や地域との関わりが強いことから、信頼感を高める内容を発信することが大切です。応募者増や認知度向上に直結するため、常にターゲットとなる保育士や保育教諭のニーズを把握しておく必要があります。
また、他園との差別化ポイントを打ち出すことも重要です。職員の働きやすさや独自の保育方針など、入職後に候補者が実際に魅力を感じられる点をアピールし、応募から面接へとつなげていきます。
オペレーター/管理担当者
候補者との連絡調整や書類管理など、採用事務全般を引き受ける役割です。複数人のスケジュールを整合させる必要があるため、タスク管理スキルやコミュニケーション能力が求められます。
採用システムやメールツールを活用し、応募者とのやり取りをスムーズにするのも重要な業務です。応募者に対する初期情報の提供や案内の質が高いほど、施設への好印象につながりやすくなります。
チーム内では潤滑油のような存在で、リーダーやリクルーター、面接官など各担当者との情報共有を行い、採用プロセスを円滑に進めるサポートに徹します。
面接官/アセッサー
応募者の保育士としての資質や、施設の理念に対する理解度を面接を通じて判断する大切な役割です。専門的な知識や現場感覚が求められ、適切な質問を行いながら候補者の真の人柄を見極めます。
幼保施設や保育園においては、コミュニケーション能力や協調性、子どもへのまなざしなどが選考の大きな基準となります。面接時に評価ポイントを明確にし、客観的かつ公平な視点で判断することが重要です。
また、応募者に施設の魅力や実際の働き方を伝えることで、候補者自身もイメージを深められます。面接官による適切な説明とアセスメントが、入職後のミスマッチを減らすカギとなるでしょう。
クロージング担当
最終のオファー面談や内定者フォローを行い、採用の成約率を高めることを目的とする重要な役割です。応募者が迷いや不安を感じている場合に、疑問点を解消し、安心感を与えるよう働きかけます。
内定後の手続きや入職準備に至るまでのサポートも担当し、幼保施設・保育園の環境にスムーズに溶け込めるようアシストします。ここでのフォロー体制が充実していると、内定辞退が減り、入職後の定着率向上にもつながります。
特に幼保の仕事は体力や精神面での負担も大きいため、入職前からしっかりとメンタル的な支えを提供できるかどうかが、候補者の安心感を左右します。
適正なチーム人数とリソース管理

採用目標や施設規模に応じたチーム構成が必要です。過不足なくリソースを配分するためには、採用活動における工数の見直しとツールの活用が重要となります。
幼保施設・保育園の採用規模は、年間の募集人数や新卒採用、中途採用の状況によって異なります。少人数の施設の場合、1名が複数の役割を兼任するケースが多いですが、需要が多い時期には人手不足に陥るリスクがあります。
そこで、採用管理システムやコミュニケーションツールを導入し、工数を削減しつつ業務効率を上げる方法が有効です。特に複数のメンバーが同時並行で作業する際には、全員がリアルタイムに情報を共有できる仕組みが欠かせません。
また、季節による応募者数の変動や、急な欠員補充などに備えて柔軟に動ける体制を考えておく必要があります。必要に応じて非常勤やアルバイトスタッフの力を借りるなど、予算と採用効果のバランスを見極めながらリソースを最適化していきましょう。
採用チームをつくる具体的なステップ
採用チームを円滑に機能させるには、目指す採用像を共有し、各メンバーが自分の役割を明確に理解することが欠かせません。ステップごとに準備や手順を確認しましょう。
採用チームを構築する際、まずは採用のゴールと必要な行程を可視化し、チームのメンバーがお互いのタスクを把握しやすいようにします。これによって、どのタイミングで誰が何をするのかを明確化でき、職員同士の衝突や無駄な空き時間を防ぎやすくなります。
次に、コミュニケーションのルール作りや定例打ち合わせの実施など、スムーズな情報連携を行う環境整備が重要です。特に幼保施設・保育園では、新学期前後や年度末など、ピーク時期がはっきりしているため、そのタイミングを狙った採用強化策も視野に入れながら動くことが求められます。
各ステップで必要となるタスクや成果物を細分化して定義しておけば、PDCAサイクルを回す際の振り返りが容易になります。以下の4ステップを意識して実践することで、効果的な採用チームが作りやすくなるでしょう。
ステップ1:採用計画と目標の設定
まずはどのような人材を何名、どの時期に採用したいのかを明確化します。幼保施設の場合、年度始めに合わせた新卒採用や欠員補充が中心となるため、長期的な視点で募集スケジュールを組むとよいでしょう。
施設のビジョンや保育方針を改めて言語化し、いかにして魅力的に発信していくかを議論します。このとき、チーム全員が共通の目標に向かうための指標や達成基準を設定し、進捗を測りやすくすることがポイントです。
KPIとして面接設定数や内定承諾率などを設定することで、採用活動の成果を客観的に把握できるようになります。
ステップ2:キーメンバーの選定と役割分担
採用マネージャー/リーダーを中心に、リクルーターやオペレーター、面接官など必要なポジションを洗い出し、メンバーを配属していきます。できるだけ得意分野や経験を活かせる形にすると、モチベーションを高く保ちやすくなります。
幼保施設で働いた経験がある職員など、現場を知る人材は面接官やフォロー担当に向いているかもしれません。また、ITリテラシーに長けた職員をオペレーターや管理担当者にすると、デジタルツールの導入がスムーズに進むでしょう。
チーム内で複数業務を兼任するときは、普段の業務とのバランスに注意し、メンバーが過負荷に陥らないよう調整します。
ステップ3:コミュニケーション体制の整備
チーム内で定例ミーティングを開き、各メンバーの進捗報告や課題点を共有することで、問題を早期に発見・解決できます。オンラインツールなどを活用して、リアルタイムで情報交換ができる仕組みを作るのも有効です。
また、情報を一元管理できる採用管理システムを導入することで、応募状況や候補者情報を誰でも簡単に把握できるようにします。この仕組みをきちんと運用することで、後から入ったメンバーや兼任者もスムーズに作業へ参加できるでしょう。
さらに、施設全体の職員が採用活動の重要性を理解し、必要に応じて協力できる体制を作ることも大切です。現場の理解や協力が得られれば、面接の際などで実際の保育現場を魅力的にアピールすることができます。
ステップ4:PDCAサイクルで継続的に改善
採用目標や施策の結果を振り返り、計画(Plan)、実行(Do)、検証(Check)、改善(Act)のサイクルを回すことで、チームの完成度を高めていきます。特に幼保業界では、年度進行に合わせて募集のピークや応募数が変動しやすいため、定期的な見直しが不可欠です。
面接方法や応募メディアの選定など、効果が出やすい部分から優先度を設定し、小さな改善を積み重ねていくことが大切です。結果をデータで残し、次年度の採用計画に活かすといった仕組み化も図りましょう。
こうした継続的な取り組みによって採用チームの完成度が上がり、より高い成果を出し続ける組織へと変わっていきます。
採用チーム運用の注意点と成功事例
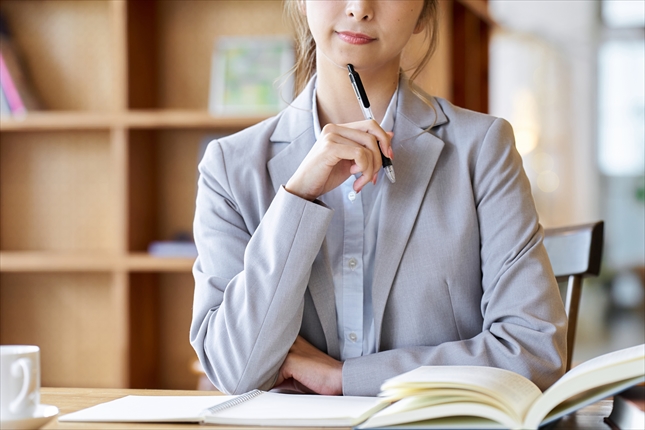
採用チームを運用する際には、チーム内外との連携不足や業務過多に注意が必要です。成功事例をもとに、どのような工夫が成果につながるかを確認しましょう。
チーム内の連携が不十分だと、同じ応募者に対して複数人が同時に連絡を送ってしまったり、逆に連絡漏れが発生したりする恐れがあります。どのポジションが何をしているのかを可視化し、本人不在時に他のメンバーが代理対応できる体制を整えましょう。
一方で、成功事例としては、1人ひとりの得意分野を活かしてメンバーを配置することで、採用活動全体のスピードと質が向上したケースがよく挙げられます。たとえば、SNS発信が得意なリクルーターがこまめに情報を発信し、施設への好意的なイメージを広めるといったアプローチがうまくいった例が存在します。
さらに、内定後のフォローを充実させることで内定辞退を大幅に減らした園もあります。クロージング担当が丁寧なフォローアップを行い、入職までの不安を解消することが、安定した採用成果につながるポイントのひとつです。
まとめ・総括
幼保施設・保育園の採用チームは、施設運営の基盤となる人材を確保し育成するうえで不可欠な存在です。ここまでのポイントを踏まえ、自園の体制に合わせた最適な採用チームづくりを目指しましょう。
採用チームを組成することで、業務を専門的に分担しながら効率よく候補者対応を進めることができます。採用マネージャーやリーダーを中心に、リクルーター、および事務や面接業務を担うポジションを整えることで、採用活動の質を高める仕組みを作り上げられるでしょう。
チームを動かすにはステップごとの計画やコミュニケーションルールが不可欠であり、継続的な改善サイクルも大切です。特に幼保施設・保育園では、応募者との信頼構築やモチベーション形成が成果に直結するため、細やかなフォロー体制を徹底することがポイントとなります。
採用チームがしっかりと機能すれば、施設全体の人材確保だけでなく、新人職員の定着率や職員同士の連携向上にもつながります。この記事を参考に、自園ならではの採用チームの作り方を検討し、より魅力ある組織づくりを実現していきましょう。