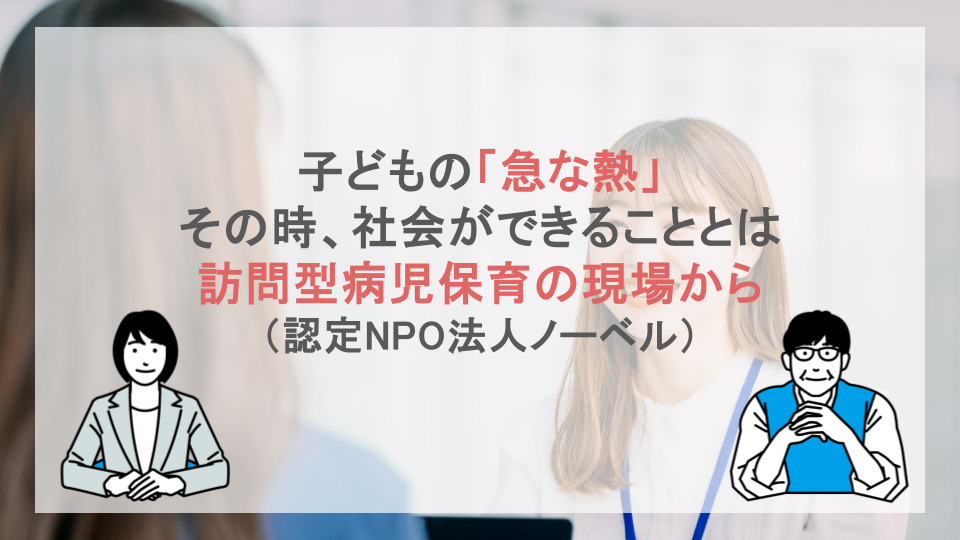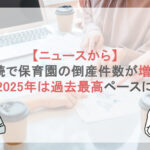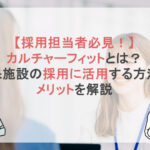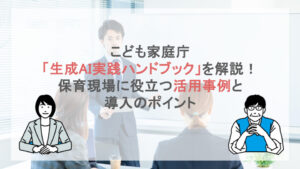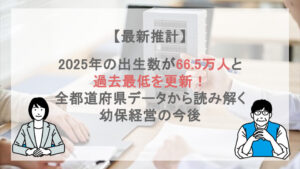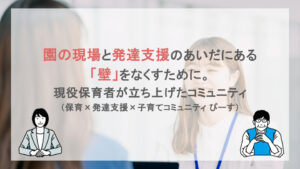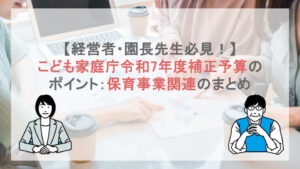1.はじめに:社会課題としての「病児保育」

集団保育の現場では、感染症の拡大を防ぐため、また体調不良のお子さんを手厚く看護するため、37.5度以上の発熱がある場合は預かることが難しいのが現実です。
保護者は仕事を調整し、急いで迎えに向かう。しかし、誰もが簡単に仕事を休めるとは限りません。一方で、保育園側も、心苦しいと思いながらも集団の安全を守るために判断を下さねばなりません。
内閣府の調査でも、子どもの病気の際に「仕事を休んだ」「(預け先が)見つからず困った」という声は常に上位に挙がります。特に都市部では、病児保育施設が不足し、冬季の感染症シーズンには予約が殺到します。
この「子どもの病気」と「仕事」の板挟みは、個々の家庭の問題ではなく、保育園や地域、社会全体で向き合うべき共通の課題となっています。
こうした中、保育園や施設での「集団保育」とは異なるアプローチで、この課題に取り組む「訪問型病児保育」の存在が注目されています。
今回は、大阪市に拠点のある、認定NPO法人ノーベルさんを取材させていただきました。
2.訪問型病児保育のパイオニア「認定NPO法人ノーベル」とは
大阪市に拠点を置く「認定NPO法人ノーベル」は、2009年に設立された、関西における訪問型病児保育のパイオニアの一つです。
その設立の背景には、「女性が子育てを理由にキャリアを諦めざるを得ない」という社会課題がありました。特に「子どもが病気になった時の預け先がない」という切実な声に応えるため、営利企業ではなく、社会課題解決を使命とするNPOとしてスタートしました。
ノーベルの大きな特徴は、「当日朝8時までの予約に100%対応」するという体制です(※利用条件あり)。子どもの急な発熱は予測ができません。その「いざ」という時に必ず駆けつけるセーフティネットとして、これまで累計2万5千件を超える無事故での保育実績を積み重ねています。
その活動は「子育てこそ、みんなで。」というビジョンのもと、子育ての負担を家庭だけに負わせず社会全体で支えよう活動しています。
3.「自宅で、1対1で」 ノーベルが実践する病児保育の現場

訪問型病児保育は、通常のベビーシッターと何が違うのでしょうか。それは「病児」に特化した専門性です。
ノーベルでは、保育スタッフが現場に出る前に、徹底した研修が行われます。子どもの病気の基礎知識、症状別の対応方法、薬の知識などを学ぶ約10時間の座学研修に加え、指導スタッフが同行する実務研修を最低4日間実施。さらに、現場デビュー後も月1回のスタッフ研修や、保育がない日にも「熱性けいれんの対処法」「嘔吐物の処理」など、具体的なことも学ぶ時間を取り、スキルアップにつなげています。
実際の保育では、スタッフが利用者の自宅を訪問。まず保護者から症状や服薬状況などを丁寧に引き継ぎます。日中は、お子さんの病状と生活リズムに合わせ、体調に配慮した遊びや食事、服薬のサポートを行います。
集団保育と違い、1対1だからこそできるきめ細かなケア。保育中は、保護者が安心して仕事に集中できるよう、午睡中などにスタッフからお子さんの様子がメールで報告されます。一日の終わりには、詳細な保育記録と共に、保護者へ無事にバトンが渡されます。
また、ノーベルの取り組みは病児保育に留まりません。2025年10月からは、各家庭の状況を伺い、その家庭に合ったサポートを提案し実行するサービス「まるサポ(子育て家庭のまるごとサポート)」も開始し、子育て家庭を包括的に支える活動へと広がっています。
4.保育園とNPOが「連携」する意味

「病児保育」は、保育園運営にとっても密接なテーマです。
ノーベルのような訪問型病児保育は、保育園にとって「敵対」するものではなく、むしろ「協働」できるパートナーとなり得ます。
例えば、保育中に発熱したお子さんを、保護者がすぐに迎えに来られないケース。ノーベルでは、保育園へのお迎えから、かかりつけ医への受診代行、そしてその後の自宅保育までを一貫してサポートする体制も整えています。
これは、保育園にとっては「発熱したお子さんを長時間預かり続ける」という現場の負担を軽減し、他の園児の保育に集中できる環境づくりに繋がります。また、保護者にとっても「病児保育」という選択肢があることは、園への安心感や信頼感にも寄与します。
保育園がすべてを抱え込むのではなく、こうした専門性を持つ外部のNPOと地域のリソースとして連携し、セーフティネットを共有していく。それは、地域全体で子育てを支える一つの形と言えるでしょう。
5.保育士の専門性が活きる「もう一つのキャリア」

ノーベルで活躍する保育スタッフには、保育士資格や看護師資格を持つ人、そして自身の子育て経験が豊富な人が多く在籍しています。
集団保育の現場で培った「子どもの発達に関する知識」や「安全管理のスキル」は、病児保育という1対1のケアの現場で、そのまま専門性として活かされます。
あるスタッフは「集団保育では多くの子を同時に見守るやりがいがあった。今は、病気で不安な子どもとじっくり向き合い、保護者の方から『本当に助かった』と直接感謝されることに、新たなやりがいを感じている」と語ります。
また、その働き方の多様性も特徴です。週1回のWワークから、週5日の正社員まで、個々のライフスタイルに合わせて活躍の場が提供されています。20代から60代まで幅広い世代が、これまでの経験を活かし、プロフェッショナルとして働いています。
保育士のキャリアは、保育園の中だけにあるのではありません。その専門性を、集団保育とは異なる「1対1のケア」という形で社会に還元する。訪問型病児保育は、保育士にとっての「もう一つのキャリアパス」としても、重要な役割を担っています。
6. まとめ:病児保育が「特別な選択」でなくなる社会に向けて
子どもの急な発熱は、誰にでも起こりうることです。その時、保護者が仕事を諦めたり、保育園が過度な負担を背負ったりするのではなく、地域社会が「当たり前のインフラ」として支える。
認定NPO法人ノーベルの取り組みは、一つの実践的なモデルケースです。
保育園、保護者、そしてノーベルのような専門機関がそれぞれの役割を全うし、しなやかに連携していくこと。それこそが、「子育てこそ、みんなで。」を実現する鍵となるのではないでしょうか。