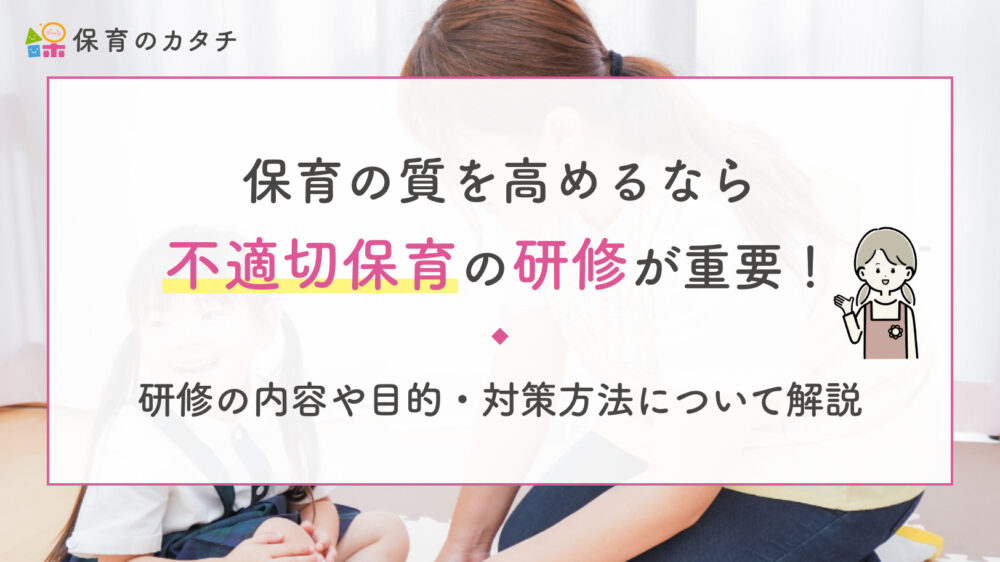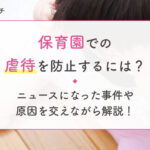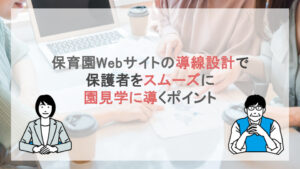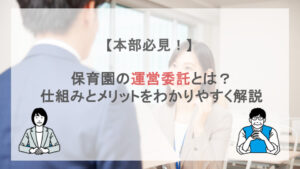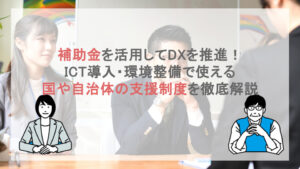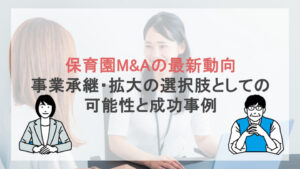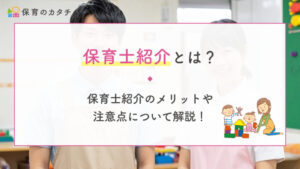近年、「不適切保育」に関するニュースや記事で、子どもに対する虐待や事件が取り上げられています。そんな不適切保育ですが、「不適切保育とは何か」「不適切保育に関する研修はないのか」と思う方は多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、「不適切保育の研修」について解説します。また、不適切保育の内容や不適切保育の対策方法も併せて紹介します。
この記事を読めば、不適切保育ついて理解できるので、不適切保育に関して詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
\支援実績1000社以上!園の全体最適を考えた採用をサポート!/
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/
保育士の採用をするなら保育のカタチがおすすめ
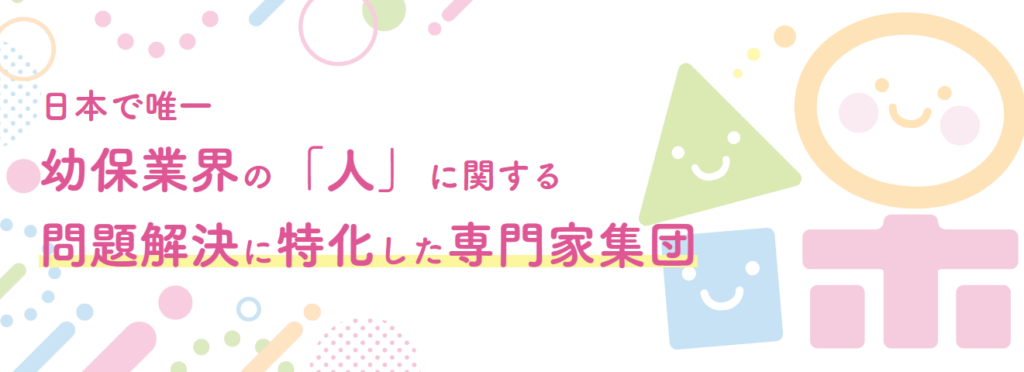
引用元:保育のカタチ
保育士の採用をするなら保育のカタチがおすすめです。
保育のカタチは日本で唯一、幼保業界の「人」に関する問題解決に特化した専門家集団です。採用から社員教育、それらの仕組み化まで幅広く取り組んでおり、人手不足の保育業界の中で、幼保施設にとって最善のパートナーが見つかるようなお手伝いをしています。
採用がうまくいかず悩んでいる方はぜひ一度保育のカタチにご相談ください。
| 住所 | 〒550-0004大阪府大阪市西区靱本町1-7-22 SKKビル201 |
| 許可番号 | 厚生労働大臣許可番号有料職業紹介事業:27-ユ-303764 労働者派遣事業:派27-304996 |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員、パート |
| 求人施設 | 保育園、幼稚園、認定こども園、病児保育、事業内保育、学童保育、託児所など |
| 対応エリア | 全国 |
| 連絡手段 | 電話番号:06-6210-5326 |
\支援実績1000社以上!園の全体最適を考えた採用をサポート!/
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/
不適切保育に関する研修の目的
不適切保育の研修の目的は、不適切な保育をあらかじめ防止することです。不適切保育に関する研修をするのは、不適切保育を未然に防止するために有効な手段です。また、不適切保育が発生した場合の適切な対応方法も研修内容で扱っています。
不適切保育は、園や個人が不適切な保育に関して、どのような対応が該当するのかを認識していない場合があります。不適切保育の研修では、不適切保育に関する理解を深められるため、園の方針を考え直す機会としても活用することが可能です。
不適切保育による事件や事故は、社会的に強く否定される事象です。しかし、不適切保育を防止するための訓練を設けている施設は多くありません。そのため、不適切保育に関する研修は、子どもの権利や命を守るためにも大切な取り組みといえます。
以下の記事では、保育業界の社会問題を詳しく解説しています。ぜひ、参考にしてみてください。
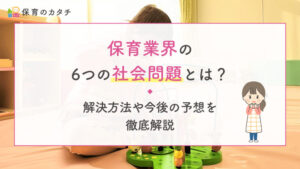
不適切保育の研修内容
ここでは、不適切保育の研修内容を紹介します。不適切保育の研修を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
- 不適切保育の理解
- 不適切保育の実例紹介
- 不適切保育の対応方法
- 不適切保育に関するグループワーク
それぞれ順に紹介します。
不適切保育の理解
まずは、不適切保育に関する理解が必要です。不適切保育の研修では、不適切保育の定義や不適切な保育が生じる背景に関して理解を深めます。不適切保育に関する知識や背景を学んだうえで、実例の紹介や対応方法の議論に進みます。
こども家庭庁では、不適切な保育に関して「虐待等と疑われる事案」と定義されました。この定義をもとに、職員一人ひとりの認識の問題や職場環境の問題に関して考え直すのが有効です。不適切保育に関する正しい理解は、行動を見つめ直したり、議論をしたりするうえで重要な研修内容となっています。
不適切保育の実例紹介
不適切保育の研修では、実例を紹介することもあります。実例紹介では、実際にニュースで報道された事件や保育園事故の裁判例を取り上げます。実際に起こった不適切保育は、どのような社会的評価を受けたのか具体的に議論することが可能です。
また、実際に園で問題になった事象があれば、より有益な議論ができます。不適切保育の原因は、園の方針や環境によってさまざまです。実例の紹介は、自身の言動や園の方針を振り返るうえで効果的な研修内容といえます。
以下の記事では、保育園で実際に起きた死亡事故について解説しています。実例について詳しく知りたい方は、参考にしてみてください。
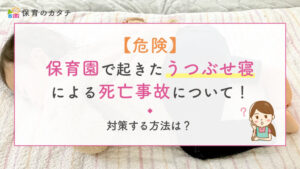
不適切保育の対応方法
研修では、不適切な保育を防ぐことだけでなく、発生した場合の対応方法を学ぶことにも意義があります。不適切保育が発生した場合、子どもへのケアや保護者への説明が必要です。不適切保育の発生時は、適切な対応が求められるため、研修内容に含まれています。
また、不適切保育による大きな事故や事件が発生した場合、警察や報道機関への対応も求められます。事件や事故は、未然に防ぐに越したことはありません。しかし、発生した場合を想定して、職員や園として対応方法を理解しておくことが重要です。
不適切保育に関するグループワーク
研修では、職員同士でのグループワークも重要です。グループワークでは、不適切保育の実例を検討したり、園児への接し方を議論したりします。グループワークでの議論は、ただ知識を深めるだけでなく、現場での対応にも活かすことが可能です。
また、不適切保育には、あいまいな基準があるのも事実です。保育における価値観や判断基準の共有により、不適切保育に関する判断力や対応力を養うことが可能です。グループワークは議題も多いため、積極的な活用をおすすめします。
\支援実績1000社以上!園の全体最適を考えた採用をサポート!/
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/
不適切な保育の種類
ここからは、こども家庭庁で定められている不適切保育のガイドラインについて紹介します。不適切保育の基準が理解できるため、保育の現場で働いている方や職員を指導する立場にある方は、ぜひ参考にしてみてください。
- 身体的虐待
- 性的虐待
- ネグレクト
- 心理的虐待
それぞれ順に紹介します。
身体的虐待
| 外傷として残るような暴力 | ・打撲傷 ・骨折 ・頭部外傷 ・内臓損傷 ・刺傷 ・切傷 |
| 命の危険のある暴力 | ・首を絞める ・殴る/蹴る ・投げ落とす ・ご飯を押し込む ・肉体的に拘束する ・布団蒸しにする |
1つ目は、「身体的虐待」です。身体的虐待とは、外傷の残るような暴力や命の危険のある暴力のことをいいます。職員による子どもに対する身体的虐待は、具体的な例として以下が挙げられます。
引用元:こども家庭庁「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」
上記のような、外傷の残るような明らかな傷害や外傷を生じさせる恐れのある行為は、身体的虐待として不適切保育に当てはまります。また、異物を飲み込ませるなど、意図的に病気にさせるような行為も身体的虐待とされます。
性的虐待
2つ目の不適切保育の行為は、「性的虐待」です。性的虐待とは、子どもに対して性的な刺激を与えたり、性的な行為をさせたりすることです。具体的な性的虐待の例としては、以下のような行為が挙げられます。
| 性的な刺激 | ・下着のままで放置する ・必要のない場面で裸や下着の状態にする ・わいせつな言葉を発する ・ポルノグラフィーを見せる ・性的な話を強要する |
| 性的な行為 | ・子どもの性器を触る ・子どもに性器を触らせるまたは仕向ける ・子どもへの性交 ・性的暴力 ・性的行為の要求をするまたは仕向ける |
引用元:こども家庭庁「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」
上記のように、子どもに対して性的な刺激をあたえたり、行為をしたりするのは不適切保育です。直接、体に刺激を与えなくても、性的な行為をするよう仕向けたり間接的にわいせつな会話を聞かせたりする行為は、性的虐待として認められます。
ネグレクト
こども家庭庁で定義されている3つ目の基準は、「ネグレクト」です。ネグレクトとは、職員が子どもの健康に対する意識が欠けていたり、子どもの安全への配慮を怠っていたりする言動や態度のことを意味します。ネグレクトの具体例は、以下のとおりです。
| 健康への配慮を怠る | ・適切な食事を与えない ・必要な情緒的欲求に応えない ・泣き続ける子どもを長時間放置する ・長時間おむつや汚れている服を変えない ・必要なコミュニケーションを取らずに保育をする |
| 安全への配慮を怠る | ・故意に車の中に放置する ・体調不良の子どもに適切な看護をしない ・別室などに閉じ込める/外に締め出す ・第三者による虐待を放置する ・職員等の子どもに対する不適切な指導を放置する |
引用元:こども家庭庁「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」
上記のような行為に加え、職務上の義務づけられていることを著しく怠ることもネグレクトに含まれます。ネグレクトは、目立った外傷がないため、発見が遅れることもあります。しかし、子どもに対する配慮を著しく怠っている場合は、虐待として認められる行為です。
心理的虐待
子どもに対する虐待として定められている4つ目の行為は、「心理的虐待」です。心理的虐待とは、子どもを精神的に傷つける行為です。心理的虐待は目に見えませんが、本人が辛いと感じたり、ストレスを感じたりする、子どもに対して心理的な傷を負わせるような行為は心理的虐待とされています。具体的な例は、以下のとおりです。
・言葉や態度で脅かす
・他の子どもと差別的な扱いをする
・子どもを無視する
・子どもに対して拒否的な態度を示す
・子どもに侮辱的なことを言う
・子どもの失敗を執拗に責める
・自尊心を傷つけるような言動をする
・子どもに孤立的な扱いをする
・感情のままに𠮟責をする
・傷つける言葉を繰り返し言う
引用元:こども家庭庁「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」
上記のような行為は、心理的虐待として認められています。上記の行為以外に、子どもがドメスティックバイオレンスを目撃している場合も、精神的なダメージを負うことから心理的虐待とされています。
上記以外にも、児童の福祉や権利を保障する「児童福祉法」があります。以下の記事では児童福祉法について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
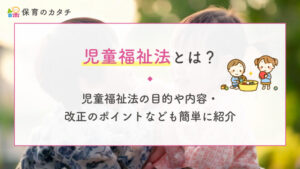
不適切保育の対策方法
ここでは、不適切保育の対策方法を紹介します。職員や幼保施設が不適切保育を防止するためには、どうする必要があるのでしょうか。不適切保育の対策をしたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
不適切な保育に関するガイドラインをもとに園での対応を策定する
施設側は、不適切保育の対策として、ガイドラインをもとに対応を策定しましょう。不適切保育への対応を策定し共有することで、事件や事故を未然に防いだり、早めに対処できたりする可能性が高まります。
職員にとっても、基準や方法が明確であれば対応しやすいでしょう。不適切な保育に関するガイドラインは、こども家庭庁のホームページに掲載されています。詳しく知りたい方は、ホームページを参照してください。
セルフチェックシート(振り返りシート)を活用する
不適切保育の対策として、普段の言動を振り返ることは効果的な方法です。全国保育協会では、人権擁護のためのセルフチェックシートが公開されています。セルフチェックシートの目的は、「子どもの人権擁護」に関して意識を高めることです。
セルフチェックシートを活用して、「子どもの権利守る保育」「子ども尊重する保育」を実践できているか振り返りましょう。施設側は、セルフチェックシートを活用して、職員に自身の保育を見直す機会を設けるのも有効な対策方法です。
定期的なセミナーへの参加をする
不適切保育の対策として、定期的なセミナーへの参加も効果的です。セミナーでは、外部講師による講義を受けたり、フィードバックを受けたりすることが可能です。保育に精通した講師の講義は、不適切保育に関して考える貴重な機会となるでしょう。
不適切保育に関するセミナーは、各自治体や民間企業でも開催されています。不適切保育を防止するために、積極的な参加をおすすめします。
まとめ
この記事では、不適切保育の研修について解説しました。不適切保育の研修では、子どもを尊重する保育ができているかどうかを再確認できます。研修は、不適切保育を未然に防いだり、発生時の対応を学んだりする方法として効果的です。
また、不適切保育のガイドラインに関しても解説しました。不適切保育の対策は、子どもの命や権利を守るために重要です。この記事を参考に、個人や施設として、不適切保育について考え直しましょう。
\支援実績1000社以上!園の全体最適を考えた採用をサポート!/
保育士の採用をするなら保育のカタチがおすすめ
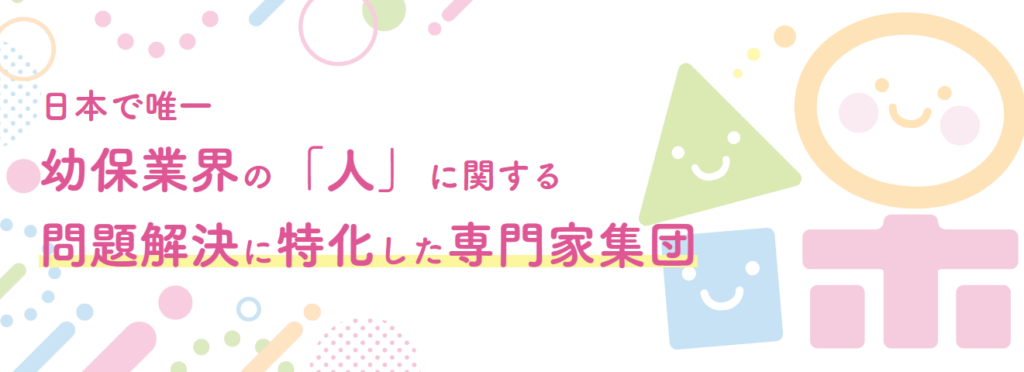
引用元:保育のカタチ
保育士の採用をするなら保育のカタチがおすすめです。
保育のカタチは日本で唯一、幼保業界の「人」に関する問題解決に特化した専門家集団です。採用から社員教育、それらの仕組み化まで幅広く取り組んでおり、人手不足の保育業界の中で、幼保施設にとって最善のパートナーが見つかるようなお手伝いをしています。
採用がうまくいかず悩んでいる方はぜひ一度保育のカタチにご相談ください。
| 住所 | 〒550-0004大阪府大阪市西区靱本町1-7-22 SKKビル201 |
| 許可番号 | 厚生労働大臣許可番号有料職業紹介事業:27-ユ-303764 労働者派遣事業:派27-304996 |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員、パート |
| 求人施設 | 保育園、幼稚園、認定こども園、病児保育、事業内保育、学童保育、託児所など |
| 対応エリア | 全国 |
| 連絡手段 | 電話番号:06-6210-5326 |
\支援実績1000社以上!園の全体最適を考えた採用をサポート!/
\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/